医師への軌跡
医師の大先輩である大学教員の先生に、医学生がインタビューします。
滋賀にいながら世界に目を向けられる医師を育てたい
辻 喜久
滋賀医科大学医学部 臨床教育講座 准教授

医学で世界へ出ていく
坂井(以下、坂):先生のこれまでのご経歴を聞かせてください。
辻:はい。僕は高校卒業後、文系の学部に進学して哲学や心理学の勉強をしていました。でもそれらは、面白いけれど生きた人間につながっている感じがしなかった。そんな時、嗜眠性脳炎の治療に携わった医師の本を読んだのです。主人公がリルケの詩を引用して患者さんの心情を表現する場面に「文学や哲学が生きる世界がある!」と感動し、医学部入学を決意しました。
医学部ではサッカーに熱中し、おまけに試験勉強嫌いで成績はとても悪かったのですが(苦笑)、興味のあることは勉強していました。卒後は京大と倉敷中央病院で内科・消化器内科の研修を受けました。研修医時代は、急性期疾患、特に重症膵炎の症例を非常に多く経験させていただきました。また、この時期に書いた急性膵炎の論文が米国消化器病学会雑誌の表紙に取り上げられ、これがきっかけでメイヨー・クリニックに留学しました。渡米中に東日本大震災が発生し、米国の医療グループに参加して南三陸町に派遣されました。
帰国後は京大に戻り、大学のプログラムでブータンに行ったり、倉敷中央病院に重症消化器疾患チームのリーダーとして異動になったりと、色々な経験をさせていただきました。一方、僕がやりたい放題している間、家族はアメリカに残されたり、帰国後も僕が単身赴任したりと置いてけぼりで。そのことへの反省もあり、もう少し家族のそばで働きたいなと思っていた時、今のポストのお話を頂きました。以前から教育にも興味があって、学生や研修医を集めて教えていたこともあり、大学教員の職に就くことにしました。
清水(以下、清):震災の時はどんなご経験をされましたか?
辻:あの時は、どんなに医療が進んでも、診断の基本は「手と口」だと痛感しました。いくら最新の機器を使いこなせても、電気のない避難所では意味がないんです。また、余震の直後には、不調を訴える人が増えることも印象的でした。例えば「喉が痛い」とだけ訴える患者さんも、その背景には不安が隠れている。そんな方々のお話をじっくり聞いたり、ときには子どもの前で手品を披露したりして、心に寄り添うよう努力しました。こうした経験を若い医師にも伝えたいと考えたことも、今の仕事につながっていると思います。
地域に寄り添い、世界を見る
坂:地域を見る目と、国内外問わず広く外を見る目の両方を身につけるには、どうしたらいいでしょうか。
辻:地域と世界って、相反するようで、実は共通点があるものです。僕は外に出たとき、どこに行っても変わらない共通点をまず探し、次に違いに注目して持ち帰るようにしています。また、外にいるときは内のこと、内にいるときは外のことを考える、双方向の視点も大切ですね。
これはブータンで胃の内視鏡検査をした時の話ですが、ブータンでは早期の胃がんの発見率が悪かった。絶食等の検査前処置が不十分で、がんが胃の中のものに紛れてしまっていたんです。絶食や消泡剤の服用を徹底する日本の検査法は、医師たちが胃がんの早期発見のために尽力してきた結果なのだと、海外にいながら日本の医療について考えるきっかけになりました。
清:学生時代にやっておいてほしいことはありますか。
辻:まず、自分の内面ととことん向き合ってください。魂の震えるような経験をしたとき、「なぜこんなに心が動いているんだろう」と内省することは、将来患者さんを理解するときに必ず活きてきます。勉強に限らず色々なことを経験して、自分のものにしてほしい。そして、滋賀から世界を見られるような、地に足のしっかり着いた医師が、一人でも多く育ってくれたらと、楽しみにしています。
辻 喜久
滋賀医科大学医学部 臨床教育講座 准教授
2001年、高知医科大学卒業。2010年、京都大学にて医学博士。京都大学医学部附属病院、倉敷中央病院、米国メイヨー・クリニックなどを経て、2016年より現職。
坂井 有里枝
滋賀医科大学 医学部 4年
外向きの志向を強く持つと、地域のことは忘れがちになってしまう自分に悩んでいました。しかし双方向の観点を忘れずに持つことで、より可能性が広がることを学びました。
清水 彩永
滋賀医科大学 医学部 3年
地元である滋賀に残るか、外に出ていくか決めなければと焦っていましたが、自分を見つめ直すことが大切だという先生の言葉を伺って、少し気持ちが楽になりました。
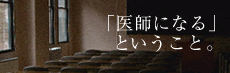


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:辻 喜久先生
- Information:Winter, 2018
- 特集:学校保健 医師は学校で何ができるか
- 特集:学校保健の全体像
- 特集:case study①学校に出向いて見守る学校医
- 特集:case study②地域と密接に関わる学校医
- 特集:学校保健において医師ができること
- 特集:学校保健に関わるにはどうしたらいいの?
- 「食べる」×「健康」を考える②
- 同世代のリアリティー:臨床心理士 編
- 地域医療ルポ:神奈川県横浜市中区|ザ・ブラフ・メディカル&デンタル・クリニック 明石 恒浩先生
- チーム医療のパートナー:看護師(緩和ケア・在宅)
- レジデントロード:産婦人科 小元 敬大先生
- レジデントロード:耳鼻咽喉科 田中 亮子先生
- 医学教育の展望:医学教育を国際基準で評価し、質を高めていく
- 医師の働き方を考える:チームで負担も喜びもシェアしながら、大好きな栃木県で在宅医療に従事する
- 大学紹介:東北医科薬科大学
- 大学紹介:国際医療福祉大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医師会の取り組み:東京都医師会における学生・若手医師支援活動
- 学会の取り組み:日本整形外科学会の女性医師支援
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 入会のご案内
- FACE to FACE:大塚 勇輝×中村 薫

