
Interview【日本医学会会長に聴く】(前編)
医学という広大な知の体系を見つめつつ、
一人の人間として命と向き合う
移植医療の課題を乗り越えるために
――門田先生は、2017年より日本医学会の会長を務められています。先生ご自身は、どのようなきっかけで研究の道に進まれたのでしょうか?
門田(以下、門):肝臓移植に関心を持ったのがきっかけです。我々が学生の頃は、先輩に紹介してもらった病院に実習に行き、医師の手伝いをするといったことを学生が自主的にやっていました。その時に出会った肝硬変の患者さんに大きく影響されたような気がします。その患者さんは私と年の頃はそう変わらないような人でした。体のどこが痛むというわけでもなく、本人は病識がないものだから、調子の良い時には夜中に抜け出して酒を飲みに行くなんていう破天荒な人で、結果的に実習中に亡くなってしまいました。そんな患者さんの姿を見ていて、肝硬変や末期の肝不全をどうしたら助けられるのかと思ったことが始まりでした。1960年代後半のことで、この頃にはアメリカで肝臓移植の成功例が報告されるようになってきていた。日本は臓器移植の分野では海外に大きく後れをとっていたけれど、1968年に札幌医大で日本初の心臓移植が行われたことで、社会的にも臓器移植に関心が高まっていた時期でした。それで、「よし、自分は肝臓移植をやっていくぞ」と心に決めたんです。
――国内で臨床で肝臓移植に取り組んでいるチームはほとんどない時期でしたよね。
門:そうでしたね。だから色々な課題に直面しました。臓器移植で特に問題になるのが、拒絶反応です。今でこそ様々な免疫抑制剤がうまく使われるようになったけれど、当時の薬は今ほどの効果もなく、副作用も強かった。そこで我々は、免疫抑制剤を使わずに臓器移植の拒絶反応を予防する方法を研究することにしたのです。
――移植医療の課題を乗り越えるために、免疫に関する研究が必要だったんですね。
門:はい。もちろん人で実験することはできないから、ラットで何度も移植手術を行い、免疫学的エンハンスメントという考え方を応用して拒絶を抑制することができないか、実験を繰り返しました。最初はラットの肝臓を入れ替える移植手術をやっていたんだけど、どんなに移植しても全部失敗で、1年くらいはやれどもやれども成果が出ないという日々が続いた。我々は、免疫学的エンハンスメントについて研究したいのに、その手前のラットの移植手術の手技が安定しない。この方法では無理だと諦め、心臓移植に切り替えたことで、ようやく研究が前に進み始めた、ということもありました。
――やはり、一朝一夕に結果が出るものではないのですね。
門:そうですね。移植の場合は特に、ドナーとレシピエントのラットの組み合わせによって、成功するか否かが大きく左右されます。私の場合、方法を変えて色々と試行錯誤しているうちに、偶然相性のいい組み合わせに出会って、免疫学的エンハンスメントの導入に成功した。研究というものは運による部分も大きいと思う。けれど、今の日本の学術研究環境は、期限付きのポストが多く、研究資金にも制限が多い。日本医学会としては、研究者が短期間での結果に振り回されず、試行錯誤しながらじっくり研究に取り組めるよう、政治に対してもっと強く意見を表明していかなければと思っています。

Interview【日本医学会会長に聴く】(後編)
大切なのは想像力
――移植医療には、医学的な課題はもちろん、倫理的な課題も多いと思います。
門:医師という仕事は、命という、人間にとって最も重要な問題に直接関係するものです。臓器移植の場合は特に、臓器を提供する側ともらう側、その命のやり取りの間に立って、目の前の患者さんの命を救うため努力する。さらに、そんな医師自身もいつ患者になるかわからず、いつかは死ぬ運命にある。一人の人間として、自分の命や他人の命について真剣に考えるのと同時に、医学という非常に大きな体系を見渡す広い視野を持つ。そんな医師を育て、磨く環境が必要ですね。
――先生ご自身は、どこで視野を拡げ、医師として磨かれたと感じますか?
門:昔は、がんの患者さんには病名告知はほとんどしなかった。家族には必ず言うけれど、本人には言わないという時代が長かったのです。それを見ながら、「本人が除け者にされるのは絶対におかしい、もしこれが自分だったら許すだろうか」と考えたりするうちに、患者と自分が常に交錯する、相手を見ると同時に自分のことも見ている、そんな感覚がいつの間にか身についていったように思う。
医学部であれ、研究所であれ、病院であれ、人の生命に関係する場所で働きながら、常に自分と相手を入れ替えて考える。結局は、みんな死ぬ存在であり、同じところに行くんだということを強く感じる。医師という仕事はそういうものです。
医学の道を歩むということ
――学術研究に携わる意義と、研究者の使命について、ご意見をお聞かせください。
門:学術的に物事を見るというのは、今日・明日はもちろん、自分の人生というスパンでもなく、子孫のこと、そして地球全体のことを考えて、何が正しく、何が間違っているのかを突き詰めて考えることだと思う。実社会を動かしていく立場の人が、目の前の成果を追わなければならないということは理解できるが、学術に関わる者は、長い目で見たときの社会や地球の利益を擁護するために、もっと意見を発信していく必要があります。
人間は、自分で自由に考えることによって、自分自身を超越していくことができる存在です。自分の人生の範囲よりずっと先のことまで考えるのが、知や学術を担う者の、社会に対する責務でしょう。そして、若い人たちがそれを考え、突き詰めていくことができる環境を提供していくことが大切だと考えています。
医学部に入ってきた学生には、医学部でやりたいこと、医師としてやりたいことが明確でなく、成績優秀だから医学部に来たという人も一定数いるでしょう。我々の立場からすると、医学の道を選んで「何を為したいのか」ということを、本当は大学受験の前に、自分の友人や家族と一緒に考えてほしい。もちろん、それを考えずに医学部に来てしまったから駄目というわけではありません。今からでも遅くないから、研究でも臨床でも、自分が為したいことについて、自分でしっかり考えてもらいたいです。

門田 守人先生
Morito Monden
1970年 大阪大学医学部卒業
1994年 大阪大学第二外科教授
2007年 大阪大学理事・副学長
2012年 がん研究会有明病院院長
2018年4月現在 日本医学会会長、堺市民病院機構理事長、
がん研究会理事・名誉院長、大阪大学名誉教授。
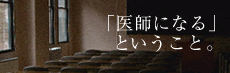


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:淺村 尚生先生
- Information:Spring, 2018
- 特集:医師と研究
- 特集:基礎研究に携わる医師 鈴木 一博先生(大阪大学免疫学フロンティア研究センター 免疫応答ダイナミクス研究室)
- 特集:臨床研究に携わる医師 田中 里佳先生(順天堂大学医学部 形成外科学講座)
- 特集:臨床研究に携わる医師 田代 泰隆先生(九州労災病院 整形外科・スポーツ整形外科)
- 特集:社会医学研究に携わる医師 辻 真弓先生(産業医科大学医学部 産業衛生学講座)
- 特集:日本医学会会長に聴く 門田 守人先生(日本医学会 会長)
- 「食べる」×「健康」を考える③
- 同世代のリアリティー:薬剤師 編
- チーム医療のパートナー:看護師(緩和ケア・急性期)
- 地域医療ルポ:香川県木田郡三木町|松原病院 松原 奎一先生
- レジデントロード:麻酔科 長谷川 源先生
- レジデントロード:救急科 太田 美穂先生
- 医学教育の展望:医療におけるコミュニケーション教育
- 医師の働き方を考える:産業医として、子育て中の医師として、 日本社会の働き方改革に貢献したい
- 日本医科学生総合体育大会:東医体/西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医師会の取り組み:受動喫煙の防止
- 地域医療の現場で働く医師たち 第6回「日本医師会 赤ひげ大賞」表彰式開催
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 日本医師会とドクタラーゼについて
- FACE to FACE:鈴木 あみ×西原 麻里子

