
医師とAI(前編)
2016年に実施された転移性乳がんの診断コンテストにおいて、人工知能の誤診率は7.5%、病理医の誤診率は3.5%だったところ、人工知能と医師の診断を併用した場合には、誤診率が0.5%まで減少したという報告がありました。
医師とAIがうまく協働することは、より良い医療の提供につながると言えるでしょう。ここからは、医師とAIの協働の可能性と、推進していく上での課題について、日本医師会の学術推進会議の報告書 に基づいて解説します。
AIと人間、それぞれの限界
人工知能の限界としては、まず確定診断ができないことが挙げられます。正解とされる診断も明確でない上に、治療方針の決定に際して、多くの要素を勘案しなければならず、分野特化型の人工知能がどんなに進化したとしても、医師が持つ「総合力」をカバーすることはできないでしょう。加えて、特定分野における人工知能の判断の精度がいかに上がったとしても、それによって生じた結果を引き受け、責任を取ることはAIにはできません。たとえば自動車の「自動運転」においても、事故が起きた際の責任の所在が導入に向けた大きなハードルになっています。
一方で、人間の医師の抱える困難として、現在の医学・医療においては扱う情報や知識の量が多くなりすぎて、すでに一人の人間で扱えるレベルではないという指摘があります。2003年にNEJMに掲載された、米国のカルテ分析による医療の質の評価に関する論文*によれば、後から検証して「正しい」と言える臨床を行ったカルテ記載は全体の50~80%にとどまるとされています。また2016年発表の別の論文では、米国における死亡例の約1割が医療の質の問題が原因とされ、死亡原因の上位3番目にあたるという指摘がされています。
さらに「医師の働き方改革」が進み始め、医師個人の自己犠牲を前提とした「いつ、どのような状況であっても患者の治療を最優先に」というあり方にも変化が生じています。扱う情報の量、そして労働時間の両面で、従来の働き方には限界が来ている状況です。
*参考:New England Journal of Medicine 2003; 348:2635-2645 June
医師とAIの協働
そんな時代を生きる我が国の医師も、「AIによる診断補助を用いたいと思うか?」という調
査*に対し、四分の三以上が肯定的に回答しており、医師のAIに対する期待も小さいものではありません。ただし効果的な協働のためには、医師が自らの役割を見直す必要もありそうです。
身体を持たないAIと違い、人間は視覚だけでなく聴覚や嗅覚、触覚といった五感を持っています。それらの多元的な情報を統合して判断する力こそが、人間である医師の強みなのではないでしょうか。AIの時代の到来とともに、医学生の学習スタイルや評価の基準も変わっていくのかもしれません。
*日経メディカル
「医師3064人に聞く 人工知能によって業務内容が変わる診療科は?」
https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/series/1000research/201701/
549709.html
(2017年1月9日、最終閲覧日:2019年9月26日)
画像診断における医師とAIの協働のかたち
医師とAIの協働が進みつつある分野の一つに、病理・放射線等の画像診断が挙げられます。医用画像の大部分がデジタル化されていること、画像認識をはじめとする既に確立した人工知能関連の技術が応用できることなどの条件から、最も実用化に近いと言われることもあります。現在、若手医師が中心となって取り組んでいる病理画像診断支援AIの開発事例に沿って、どのような協働が想定され、どのように開発が行われているのかを見てみましょう。
AIが学習を重ね、判断力を向上させるために必要なのは、大量の症例画像と、それに対する専門家の判断(正解)です。診療に使われるデータは各医療機関で厳格なセキュリティのもとに管理されていますから、複数の大学や民間医療機関が連携しなければ、大量のデータを学習素材として活用することはできません。さらに、画像データに対して「正解」を決めるためには、病理医としてのトレーニングを受けた多くの医師の力が必要です。画像認識に関する機械学習の技術が進歩しても、実際の臨床に応用するためには、多くの越えなければならないハードルがあり、医師の関与も欠かせません。
そして、どんなに機械学習が進んだとしても、機械が精密検査をして細胞レベルで病変を確認することはできないので、医師が「実際に検査・手術してみたらどうだったのか」という結果をフィードバックしなければ、最終的な答え合わせができません。画像診断のAIを開発するにあたっても、画像だけで学習が完了するわけではなく、その後の細胞レベルの検査や、手術結果などの実臨床と紐づいたデータが欠かせないのです。
こうして学習を積み重ねたAIは、同様に学習を積み重ねた人間の医師とともに、同じ画像を見ながらそれぞれの判断を出し合うことができるようになるでしょう。AIは人間と違って忙しさや疲れで見逃しをすることはないですし、医師はカルテの記載や外科医の話などを総合的に勘案しながら画像を見る視点を持っています。下の想像図のように、医師とAIが合同カンファレンスをして、共に学び合っていく――そんな協働の形が想定されているのです。
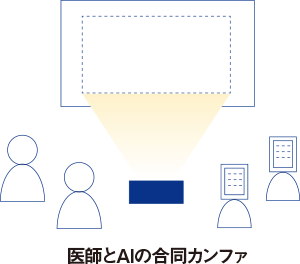

医師とAI(後編)

(無題)
人間とAIの共同作品
人間とAIは今後どのような社会を築いていくのでしょうか?それは私たちの取り組みにかかっています。
さて、ここまでは医師の側の「医療に役立つ人工知能」という視点で考えてきましたが、患者の側から考えてみると、また違った景色が見えてきます。
医師は、患者から得た情報を一旦単なるデータに置き換え、医学というデータベースに蓄積された類似症例と比較参照して診断を行います。この立場からすると、活用可能か否かは別として、参照可能なデータは多ければ多いほど良いでしょう。しかし患者の身体的データは、本人にとっては他人に知られたくないプライベートなものです。患者は治療のために、自らの身体的データを医師に開示しますが、それは医師の人間性に対する信頼あってのものだと言えます。「医学の発展のために必要だから」という理由だけでは、患者の心理的障壁をクリアするのは困難でしょう。そもそも多くの人は、巨大な組織・構造は個人の尊厳を軽視するのではないかという警戒心を持っています。フランスではかなり多くの人が、ビックデータをもとにした人工知能の診断を受けることすらあまり望んでいないというアンケート結果も出ています*。その結果からは、例え人工知能の診断が高確率で正しいとしても、人々は人類全体の叡智の発展のために「部分的なデータ」として扱われることを嫌悪し、自らと同じ死すべき肉体を持つ、人間の医師による診察を望んでいることが見て取れます。
一方で我々は、人間の不完全性も認識しており、「自分が受けた診断は正しいのか」という不安も覚えます。ただ、目の前の医師が信頼できない場合も、多くの患者は医学の効用自体を否定することなく、別の医師による診察を求めます。データベースではなく、個別のインターフェースに問題があると考えるのです。
医師は「医学」全体に対し、その知的水準向上の一翼を担う専門家として奉仕する一方、患者には一個人として向き合うことを求められます。医師はいわば、客観的な学問・データを「人間的に」出力するインターフェースであり、患者は科学的であることと人間的であることを両立させている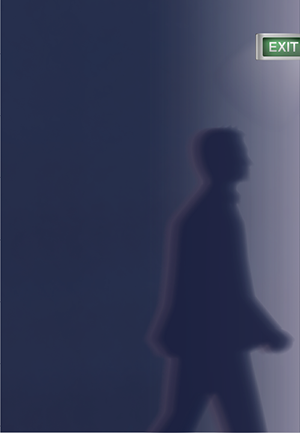 (それこそがまさに「人間的」かもしれませんが)と感じられる医師を信頼します。
(それこそがまさに「人間的」かもしれませんが)と感じられる医師を信頼します。
医学は人工知能と同じく、「知的好奇心」や「探究心」によってその発展を支えられてきたと言えますが、科学と人間性の両立という観点では、両者は異なる道筋を歩んできました。人工知能を支えたコンピューターの進歩が軍事技術の発展とともにあったのに対し、医療は原則的には、人間を病による苦痛から解放することを目的とし、世俗的要求と距離を置くこともしばしばありました。
今後、医療分野において人工知能が大きな役割を果たし始めると、医療のパラダイムそのものも大きく変質していくと考えられます。その時代を見据え、人間である医師が、同じ人間を診察し治療するということの意味を、改めて捉え直す必要があるのかもしれません。
*Becker's Health IT & CIO Report "35% of patients still wary of AI-enabled and wearable digital health solutions, study finds: 4 things to know"
(2019年6月24日、最終閲覧日:2019年9月26日)
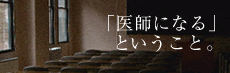


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:髙山 真先生
- Information:Autumn, 2019
- 特集:AI時代に医師は何ができるのか
- 特集:AIの発展・進化の歴史
- 特集:技術予測年表
- 特集:医師とAI
- 同世代のリアリティー:食物栄養学科の学生 編
- チーム医療のパートナー:療育に関わる専門職【前編】
- 地域医療ルポ:秋田県鹿角市|大里医院 大里 祐一先生
- レジデントロード:総合診療科 羽田野 貴裕先生
- レジデントロード:精神科 佐久間 健二先生
- レジデントロード:形成外科 中山 大輔先生
- 医師の働き方を考える:共に留学経験を得て、家族の絆を深めた
- 日本医師会の取り組み:成育医療
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:北海道大学「免疫学」
- 第6回 医学生・日本医師会役員交流会 開催報告
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- FACE to FACE:古川 紀光 × 玉井 葉奈

