
妊婦と医療・保健の関わり
70年ほど前まで、日本ではお産は自宅で行われることが一般的でしたが、今では病院・診療所で出産する人がほとんどです。妊娠は「病気」ではありませんし、妊婦は「患者」ではありませんが、今日のお産は、医師が何かしらの形で介入することがほとんどです。また、妊娠から出産・産後の期間を母子が健康的に過ごすためには、行政などによる保健的な支援も重要です。
多くの場合、医師が妊婦と最初に関わるのは、「妊娠診断」の段階です。ここでは、妊娠しているか、異所性妊娠ではないか、胎児が正常に育っているか、などを診ます。妊娠診断ができ、分娩予定日が確定できたら妊婦は妊娠届出書を役所に提出し、母子健康手帳の交付を受けます。行政的には、ここからが母子保健のスタートです。
妊娠前から産後までを広くサポート
現在、胎児の生育限界とされている妊娠22週以降から生後7日までの期間を広く「周産期」ととらえ、母子を総合的に診ていくことが一般的になっています。妊娠中や産後は、母子共に突発的な異常事態が起こりやすく、また母体がもともと持っていた疾患の病勢が進行してしまったり、新たにかかった疾患が重症化しやすかったりといったリスクがあります。そのため、産科・小児科の他、各診療科が連携して母子を総合的に診ていく必要があるということは、皆さんもご存知でしょう。
しかし、妊娠や出産にまつわる医療や行政の働きかけは、「女性が妊娠してから」ではなく、もっと以前から必要とされています。まずは、「子どもを望む人が、知識を持って安全に妊娠に至り、出産できる」ように、ひいては「自らの性別や、将来子どもを望むと望まざるとにかかわらず、誰もが自分の体や妊娠の仕組みについて知識を持てる」ようにしなければなりません。そのためには、学校医や産婦人科医が地域の学校と連携し、学童期から適切な健康教育を行うことが不可欠です。
また、産後の母親や家族へのフォローも、周産期とされる「生後7日」を超えて、継続的に行っていく必要があります。2019年に改正された母子保健法でも、「市町村は出産後1年を経過しない母子に『産後ケア事業*』を行う」という内容が盛り込まれました。核家族化が進むなかで、親族から距離的に離れている、あるいは社会・心理的背景から親族を頼れない、という妊産婦が少なからず存在しています。母子が孤立しないよう、妊娠・出産・子育てを「家庭の問題」ではなく「地域の問題」として支えていく仕組みを作る必要があるのです。
本特集では、「『お産』を取り巻く医療と保健」と題して、思春期から産後の育児期までの広いスパンで「お産」をとらえ直し、「お産」を支えるために必要な様々な仕組みについて検討します。将来、産婦人科に進もうと考えている人も、そうではない人も、「『お産』を支える」とはどういうことで、医師として何ができるのか、一緒に考えてみませんか?

*産後ケア事業…出産後1年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助を行う事業のこと。
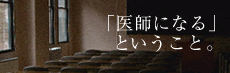


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:柳沢 正史先生
- Information:Spring, 2020
- 特集:「お産」を取り巻く医療と保健
- 特集:「産みたい人が産みたいときに産み、育てる」ための支援
- 特集:妊娠から分娩までの流れ
- 特集:分娩の流れと様々な対応
- 特集:産後の母子のフォローアップ
- 特集:おわりに~周産期医療体制のこれから~
- 同世代のリアリティー:新聞記者 編
- チーム医療のパートナー:看護師(認知症看護)
- 地域医療ルポ:広島県豊田郡大崎上島町|ときや内科 釈舎 龍三先生
- レジデントロード:防衛医科大学校 西井 慎先生
- レジデントロード:自治医科大学 増田 卓哉先生
- レジデントロード:産業医科大学 田渕 翔大先生
- 医師の働き方を考える:これからの医師に求められるのは、人の話を聴く心構え
- 日本医師会の取り組み:介護保険制度の今後と医師の役割
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:名古屋大学「地域における専門職連携教育 つるまい・名城IPE」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- FACE to FACE:Sopak Supakul ソパック・スパグン(パック)× 後藤 郁子

