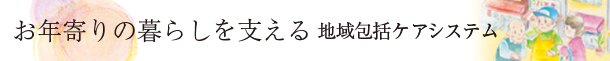
地域包括ケアを支える取り組み SCENE01
高齢者や家族を支える(東京都板橋区)(前編)
高齢者が地域で暮らし続けるためのサポートの事例として、東京都板橋区における取り組みを紹介します。
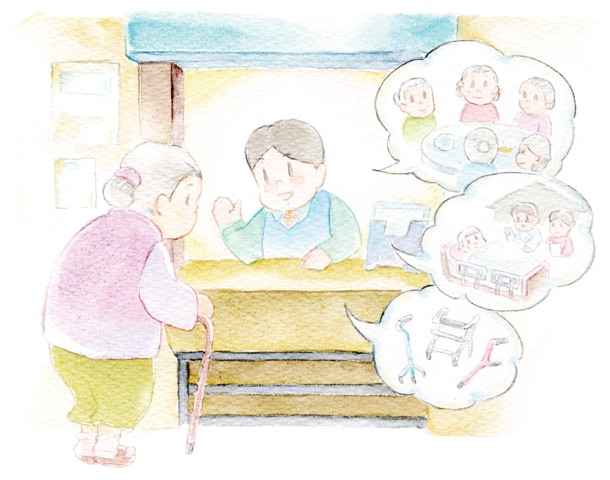
高齢者の相談を総合的に受け付ける
高齢者が、疾患や障害を持ちながらも自宅で暮らしたいと思ったとき、どのような支援が必要となるでしょうか。多くの高齢者は、在宅医療を受けたい、介護サービスを利用したいと思っても、どうしたらいいのかわからないでしょう。地域包括ケアを実現するためには、まずは高齢者が気軽に相談できる窓口が必要です。そして相談を受けた窓口は、在宅療養ができるようにするための環境を整えたり、必要な介護サービスが提供されるようにしたり、介護予防の取り組みを行う地域団体を紹介したりする役割を担う必要があります。
東京都板橋区には、地域包括ケアを推進する代表的な2つの窓口があります。1つ目は板橋区医師会在宅医療センターで、医師会内に設置されています。医療に関する相談を一手に引き受ける療養相談室を開設しており、例えば地域住民から、「がん末期の親が在宅での療養を希望しているが、どうしたらいいか」という相談を受けたら、看取りまで担うことのできる医療機関や訪問看護ステーションに依頼し、療養のための環境を整えます。
2つ目は、板橋区おとしより保健福祉センターです。こちらは区の施設で、介護や生活支援・介護予防についての相談を受けています。親が認知症だが、介護する子が精神障害を抱えているといった、介護サービスだけでは支援できない困難事例に対応するなどしています。
これら2つの窓口が、互いに連携しながら、高齢者からの相談を、医療、介護、生活支援・介護予防を担う各機関へとつないでいく役割を担っているのです。
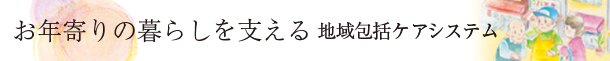
地域包括ケアを支える取り組み SCENE01
高齢者や家族を支える(東京都板橋区)(後編)
板橋区医師会在宅医療センター
 板橋区医師会在宅医療センターは、板橋区の中でも高齢化率の高い高島平地域に設置された在宅医療連携拠点です。同じ建物内に、医療・介護従事者や一般市民から医療的相談を受ける「療養相談室」と、市民から介護・福祉の相談を受ける「高島平地域包括支援センター」が設置されており、情報を共有しながら、総合的な相談窓口として機能しています。
板橋区医師会在宅医療センターは、板橋区の中でも高齢化率の高い高島平地域に設置された在宅医療連携拠点です。同じ建物内に、医療・介護従事者や一般市民から医療的相談を受ける「療養相談室」と、市民から介護・福祉の相談を受ける「高島平地域包括支援センター」が設置されており、情報を共有しながら、総合的な相談窓口として機能しています。
「療養相談室では、病院やケアマネジャーから、在宅医や訪問看護ステーションの紹介をお願いされることが多いです。またケアマネジャーからは、点滴導入にあたってどんな準備をしたらいいか、通院のタイミングはいつがいいかなど、医療的な知識についての相談もあります。家での介護状況を細かくお聞きし、必要があれば訪問もして、医療の知識をフル活用しながら調整を行います。」(塩原さん)
「高島平地域包括支援センターは、地域の駆け込み寺的存在です。住民から直接相談を受けることが多く、内容は介護保険のこと、生活のことなどがメインです。必要に応じて区の福祉事務所などと連携しながら、必要なサポートを提案します。また、地域の高齢者サロンなど、予防的な活動を支援するのも地域包括支援センターの役割です。例えば、みんなで集まってご飯を食べる『ランチクラブ』を、ボランティアと共に開催しています。同じ建物に療養相談室があることで、医療的な相談が来た際にもすぐに療養相談室につなぐことができるのは利点だと思います。」(横塚さん)
写真:在宅看護部長の井上多鶴子さん(中央)、療養相談室の塩原未知代さん(左)、高島平地域包括支援センターの横塚義和さん(右)
板橋区おとしより保健福祉センター
板橋区おとしより保健福祉センターでは、作業療法士・理学療法士・保健師など様々な専門職が、総合的な高齢者支援を行っています。
「当センターでは、相談支援業務だけでなく、地域包括ケアの推進・介護予防・認知症対策・介護普及など、様々な取り組みを行っています。相談支援では、主に地域の包括だけでは対応できないような困難事例に対し、個別に対応を行います。例えば、老老介護や認認介護、介護家族による虐待、介護家族に障害がある…などの事例があります。そうした場合、職員が訪問し、地域包括支援センター(包括)や健康福祉センター、民生委員などと情報を共有しながら、生活が送れるように様々なサポートを行います。成年後見人制度の活用や、虐待がある場合は緊急の手段として、一定期間の入院や施設入所による分離を支援することもあります。介護予防・認知症対策では、要介護認定を受けていない高齢者約10万人に調査票を送り、チェックシートを記入してもらいます。運動機能や口腔機能が落ちてきた方には、包括と連携しながらアドバイスをしたり、機能向上のための講座を紹介したりしています。介護普及については、センター内で介護用品を500点ほど常設展示しています。これだけの介護用品をいつでも気軽に見られる所は他の区市町村にはないと思います。またセンター内に介護実習室があり、そこでご家族の方や介護サービス事業所のみなさんを対象に、介護の実践的な講習を行ったりもしています。今後は、地域の医療・介護関係者と顔の見える関係を築き、横の連携を取りながら、区全体の地域包括ケアシステムの構築がうまくいくように、様々な取り組みを行っていきます。」(永野所長)


(右)所長の永野護さん(右から3番目)と、おとしより保健福祉センターのみなさん



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:近藤 豊先生
- Information:April, 2015
- 特集:お年寄りの暮らしを支える 地域包括ケアシステム
- 特集:地域包括ケアシステムとは
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE01 高齢者や家族を支える(東京都板橋区)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE02 病院と地域をつなぐ(北海道函館市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE03 在宅医療を支える(福岡県宗像市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE04 医療・介護従事者をつなぐ(山形県鶴岡市)
- 特集:対談 地域包括ケアを担う一員として医師に求められることとは?
- 医学教育の展望:地域と共に医師を育てる仕組みを作る
- 同世代のリアリティー:自治体で働く 編
- チーム医療のパートナー:みさと健和病院 作業療法士
- チーム医療のパートナー:三重県立こころの医療センター 作業療法士
- 地域医療ルポ:滋賀県東近江市|小串医院 小串 輝男先生
- 10年目のカルテ:消化器内科 山田 哲弘医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 長島 多聞医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 橋本 神奈医師
- 医師の働き方を考える:信念と広い視野を持てば、働き方は選択できる
- 大学紹介:昭和大学
- 大学紹介:日本大学
- 大学紹介:神戸大学
- 大学紹介:山口大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- 医学生の交流ひろば:5
- FACE to FACE:山田 舞耶×金 美希

