大学紹介
神戸大学
【教育】時代を先見し、進化し続ける教育カリキュラム
神戸大学 医学部附属病院 総合臨床教育センター長 苅田 典生
 神戸大学は、開放的で国際性に富む固有文化の下、「真摯・自由・協同」の精神を発揮し、人類社会に貢献するため普遍的価値を有する「知」を創造するとともに、人間性豊かな指導的人材を育成することを使命としています。その中で医学部医学科は、高い倫理観を有し高度な専門的知識・技能を身につけた医師(医療人)の養成とともに、旺盛な探究心と創造性を有する「科学者」としての視点を持った医師及び医学・生命科学研究者の育成を目指しています。
神戸大学は、開放的で国際性に富む固有文化の下、「真摯・自由・協同」の精神を発揮し、人類社会に貢献するため普遍的価値を有する「知」を創造するとともに、人間性豊かな指導的人材を育成することを使命としています。その中で医学部医学科は、高い倫理観を有し高度な専門的知識・技能を身につけた医師(医療人)の養成とともに、旺盛な探究心と創造性を有する「科学者」としての視点を持った医師及び医学・生命科学研究者の育成を目指しています。
神戸大学では10年以上前からPBLを取り入れるなど、常に先進性を求めて教育改革を進めてきました。現在は、医学教育認証評価に向けて大幅な教育カリキュラム改革を断行しています。臨床教育では多数の関係病院との連携を深めてクリニカルクラークシップの充実を図り、卒業後の臨床研修にスムーズに移行できるよう環境整備を行っています。また、卒業試験を知識偏重の評価法から臨床推論や基本技能を問う形式に改めるなど、学生の評価方法も進化しつつあります。
本学は、社会に貢献する臨床医だけではなく、ノーベル賞学者山中伸弥博士をはじめ、卓越した研究者を輩出しています。リサーチマインドを持った医師を育成するために、学生は初年次から継続的に基礎医学教室に出入りし、最先端の生命科学研究に参加することが可能ですし、在学中あるいは臨床研修期間中に大学院への入学を可能とする基礎研究医育成プログラムも始まりました。
社会のニーズに応える医師を養成するためには、時代の変化に機敏に対応する柔軟な教育システムが必要です。そのためカリキュラム委員会を設置し、教育システムのきめ細かな評価改良を続けています。本学の教育は、常に時代の先を見通しながら変化し続けています。
【研究】シグナル伝達研究の伝統と発展
神戸大学 大学院医学研究科 副研究科長 的崎 尚
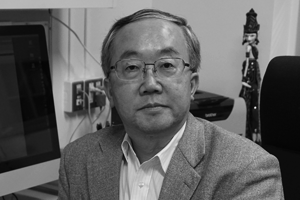 本学において、1980年代に成し遂げられた西塚泰美博士らによるプロテインキナーゼCの発見は、生命科学の教科書を書き換えた画期的な成果です。その後も、1990年代の低分子量Gタンパク質の発見、インスリンのシグナル伝達機序の解明に代表されるように、本学にはシグナル伝達研究の潮流とも呼べる確固とした実績があります。近年では、2つのグローバルCOEを中核とした研究により、がん、メタボリックシンドローム、感染症、神経筋疾患などいわゆる“シグナル伝達病”の病因・病態の解明に国際的に評価の高い成果をあげてきています。さらに最近では、「構造」「機能」「病態」「創薬」「材料」という膜科学の5つの分野を配置した「膜生物学・医学教育研究センター」を研究科内に発足させました。前2分野では、シグナル伝達の場としての生体膜の構造・動態の基本原理や新たな細胞シグナル伝達系を、細胞・組織・器官レベルで解明しようと試みます。一方、後3分野では、上述した“シグナル伝達病”の病態と細胞シグナル伝達系の異常に関する研究、さらに創薬やドラッグデリバリーシステムの開発などの応用的展開、iPSや膜工学技術といった先端技術の利用による医療デバイスの開発などを行います。これら5分野間でシームレスな研究を展開し、研究の進展レベルに即した機動的な共同研究体制を構築することで、世界最高水準の「膜生物学・シグナル伝達医学」の研究拠点形成を目指しています。
本学において、1980年代に成し遂げられた西塚泰美博士らによるプロテインキナーゼCの発見は、生命科学の教科書を書き換えた画期的な成果です。その後も、1990年代の低分子量Gタンパク質の発見、インスリンのシグナル伝達機序の解明に代表されるように、本学にはシグナル伝達研究の潮流とも呼べる確固とした実績があります。近年では、2つのグローバルCOEを中核とした研究により、がん、メタボリックシンドローム、感染症、神経筋疾患などいわゆる“シグナル伝達病”の病因・病態の解明に国際的に評価の高い成果をあげてきています。さらに最近では、「構造」「機能」「病態」「創薬」「材料」という膜科学の5つの分野を配置した「膜生物学・医学教育研究センター」を研究科内に発足させました。前2分野では、シグナル伝達の場としての生体膜の構造・動態の基本原理や新たな細胞シグナル伝達系を、細胞・組織・器官レベルで解明しようと試みます。一方、後3分野では、上述した“シグナル伝達病”の病態と細胞シグナル伝達系の異常に関する研究、さらに創薬やドラッグデリバリーシステムの開発などの応用的展開、iPSや膜工学技術といった先端技術の利用による医療デバイスの開発などを行います。これら5分野間でシームレスな研究を展開し、研究の進展レベルに即した機動的な共同研究体制を構築することで、世界最高水準の「膜生物学・シグナル伝達医学」の研究拠点形成を目指しています。
一方、将来の研究医を目指す学生の教育にも研究科全体で取り組んでおり、文部科学省の支援を受け平成24年に発足した「基礎・臨床融合による基礎医学研究医の養成プログラム」などにより、学部学生の時期からの研究活動から卒後の博士課程における研究までを一貫してつなぐ制度改革を行うなど、研究医の育成に注力しております。
【学生生活】求めよ、さらば与えられん
神戸大学 医学部 4年 城間 京香
私は高校生の時に、地元の沖縄でドクターヘリを飛ばすためのボランティアスタッフとして、募金や広報活動のお手伝いをしたことがあります。その時の体験がきっかけで救急医療に興味を持ち、災害救急で有名な神戸大学に入学しました。
印象深いカリキュラムとして、基礎配属実習が挙げられます。これは2年後期から3年前期にかけて、自分の関心に沿った研究室に配属されるものです。私は細胞生物学教室に配属されて、細胞膜の不要になった成分を消化するための仕組みであるオートファジーについて研究しました。診療科としては救急を志望していますが、臨床で積んだ経験を将来何らかの形で発表したいと考えているので、とても良い機会でした。
神戸大学では4年生からチュートリアル授業が始まります。一つの診療科に対してそれぞれ1週間の授業期間が準備されています。例えば月曜日に「21歳男性が腹痛を訴えて来院した」という症例が示され、チューターの指導のもとグループで話し合いをして、考えられる病名や行うべき検査を考えます。水曜日になると検査の結果をチューターに教えてもらったうえで診断を行い、金曜日には今後の治療方針や追加の検査についての発表をした後に先生から答えが発表されます。グループで真剣に議論し、各々が役割分担して調査を行ったうえで発表する、という一連の流れを通して、各診療科への理解が深まります。
山も海もあり、その多様な気候と風土から兵庫県は日本の縮図と呼ばれ、多くの統計結果が日本全体の統計結果と同じ傾向を示すため、様々な症例やデータを集められるそうです。都心部にも出やすく、求めさえすれば多様な刺激を受けられる環境こそが、この大学の魅力だと思います。
※医学生の学年は取材時のものです。


〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1
078-382-5111



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:近藤 豊先生
- Information:April, 2015
- 特集:お年寄りの暮らしを支える 地域包括ケアシステム
- 特集:地域包括ケアシステムとは
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE01 高齢者や家族を支える(東京都板橋区)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE02 病院と地域をつなぐ(北海道函館市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE03 在宅医療を支える(福岡県宗像市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE04 医療・介護従事者をつなぐ(山形県鶴岡市)
- 特集:対談 地域包括ケアを担う一員として医師に求められることとは?
- 医学教育の展望:地域と共に医師を育てる仕組みを作る
- 同世代のリアリティー:自治体で働く 編
- チーム医療のパートナー:みさと健和病院 作業療法士
- チーム医療のパートナー:三重県立こころの医療センター 作業療法士
- 地域医療ルポ:滋賀県東近江市|小串医院 小串 輝男先生
- 10年目のカルテ:消化器内科 山田 哲弘医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 長島 多聞医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 橋本 神奈医師
- 医師の働き方を考える:信念と広い視野を持てば、働き方は選択できる
- 大学紹介:昭和大学
- 大学紹介:日本大学
- 大学紹介:神戸大学
- 大学紹介:山口大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- 医学生の交流ひろば:5
- FACE to FACE:山田 舞耶×金 美希

