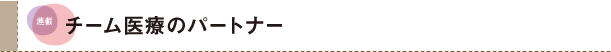
看護師(感染管理)(1)
患者さんと職員を感染から守る

――お二人は感染管理を専門にされていますが、感染管理の仕事とはどのようなものなのか教えていただけますか?
杦木(以下、杦):患者さんと職員を感染から守るために院内の感染状況をすべて把握し、組織横断的に感染対策を行っています。感染発生時にはもちろん即時対応しますが、感染のない状態がベストなので、感染を起こさないように対策することが主な仕事となります。
日々の仕事としては、院内の感染症の発生などのデータ収集や、病棟のラウンドをしています。また、院内感染が生じたり耐性菌が出現したときには電話対応や現場に出向いて指導することもあります。他にも週に一度、感染対策チーム(Infection Control Team, ICT)や院内感染対策室のメンバーでラウンドやミーティングもしています。他の分野の看護師と違って、患者さんを直接ケアする仕事ではないところが特徴かもしれません。
――ラウンドではどのようなことを行っているのですか?
杦:感染対策の一番の基本は手洗い・手指衛生なのですが、それらをきちんと実行できているか、院内の環境衛生が保たれているかというところを見ています。
窪田(以下、窪):輸液ポンプやカテーテルなどの医療器具が装着されている患者さんの場合、器具が入っている部位に感染が起こっていないかどうかや、器具の管理がうまくできているかを観察します。
杦:ICTチームのラウンドでは、病棟はもちろん、院内のすべての施設の環境と、そこで働く人たちの手指衛生のチェックを行います。
――本当に色々なところや人を見るんですね。
窪:はい。「多岐にわたる」というのが感染管理の特徴ですね。感染管理は、医師だけがやればいい、看護師だけがやればいい、というものではなく、清掃業者さんや、院内のカフェのスタッフに至るまで、あらゆる職種の方々と一緒にやらなくてはいけないものですので。
杦:以前、院内のコンビニで額に冷却シートを貼って働いている人を見かけたので、声をかけて検査を受けてもらったところ、インフルエンザだと判明したことがありました。コンビニは職員の多くが利用する場所なので、そこで働く人にも正しい知識を身につけてほしいと考え、今では年に一度研修を行うようにしています。
感染管理に関わるきっかけ
――お二人はどうして感染管理をご自身の専門にしようと思ったのでしょうか?
杦:感染対策が必要という認識が世の中に広まり、看護の世界でも感染管理の認定看護師制度が始まりました。その頃手術室にいた私は、感染管理の大切さを実感していたこともあって、感染管理認定看護師になろうと決めました。
窪:私の場合、HIVの患者さんがいる病棟に配属されたことがきっかけです。当時、世間では「HIVは怖い」という印象が強く、偏見も根強くありました。医療者が患者さんに処置をするときも、過剰な防護服を着用したりしていて、それを見て傷つく患者さんもいらっしゃいました。そうした状況を見ていて、感染管理に対する正しい知識を持ち、周りに広めていく重要性を強く感じたんです。また、当時は感染対策を全国の病院で等しく行えるようにするための研修が始まった頃でもあり、そのことからも院内全体にしっかり感染対策の知識を広める方法に興味を持っていました。
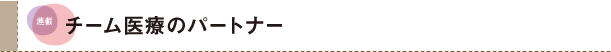
看護師(感染管理)(2)
多職種とのコミュニケーション
――仕事をするうえで難しさを感じたことはありますか?
杦:実際に現場で多職種を指導することがこんなに大変だとは、やってみなければわからなかったです。感染対策は、まずは予防が第一で、「やらなかったら大変なことになる」ものの、行ったことに対する効果が見えにくい面があります。「忙しいから」といって省略されてしまいがちだけれど、本当に大切な基本の「き」の部分を習慣付けてもらうにはどうしたらいいかを考え続けています。感染症やその予防についての情報も更新され続けていますし、今も日々理解を深め、学んでいる途上です。
窪:一旦働きかけるとよくなりますが、時間が経つとまたおろそかになって…という繰り返しになってしまって。重要性を理解してもらうことと、それを継続的に遵守してもらうことは、常に課題ですね。
――多職種と協働する際、どのような工夫をしていますか?
杦:こちらのやり方を一方的に押し付けるのではなく、誠意をもって、伝えたいことを丁寧に説明するようにしています。
窪:「これやってください」ではなくて、相手の意見もしっかり聞いたうえで、「こうしたらどうでしょうか?」と提案するように心がけています。
――どのようなときに仕事のやりがいを感じますか?
杦:耐性菌が広まってしまった際、病棟や医師と連携して、みんなで団結して収束につなげられたときなど、多職種とうまく協力して成果があがったときはやりがいを感じます。また、これまで手指衛生にあまり協力的ではなかった人が、声かけなどを繰り返していくことで取り組むようになってくれると嬉しいですね。
窪:私は今、医療器具からの感染について重点的にサーベイランスを行っています。例えば尿路感染について、どんな人に感染が生じやすいかデータをとって調べていくと、最初は膀胱留置カテーテルを長期間使用している患者さんに多いことがわかりました。そこで病棟スタッフに感染対策を指示し、そうした感染を防ぐことはできたのですが、次にデータをとってみると、今度はカテーテルを抜いた後に排尿障害が生じている患者さんに感染が多いことがわかりました。このように、次々にデータを可視化して必要な対策を把握し、スタッフや医師の間で共有して感染が減っていくと、やりがいを感じます。また、感染が生じたと思われる患者さんについて、医師や病棟看護師に伝え早期に対応したことで大事に至らずに済んだときは嬉しいですね。
医学生へのメッセージ
――最後に、医学生へのメッセージをお願いします。
杦:授業で「感染症への標準予防策」を習うと思いますが、それをきちんと実践してほしいです。卒業したての頃はきちんとやっていても、周りの雰囲気に飲まれて、だんだんおろそかになってしまう先生は多いですね。
窪:初心を忘れずに、継続してほしいです。現場の人が実践してこその感染対策ですから。
 杦木 優子さん(写真左)
杦木 優子さん(写真左)
国立国際医療研究センター病院
感染管理認定看護師
窪田 志穂さん(写真右)
国立国際医療研究センター病院
感染管理認定看護師



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:中野 弘康先生
- Information:Spring, 2019
- 特集:医師とダイバーシティ
- 特集:ダイバーシティってなに?
- 特集:医学生から見た「ダイバーシティ」
- 特集:他者を知る 対話する
- 同世代のリアリティー:家政系学生 編
- チーム医療のパートナー:看護師(感染管理)
- 地域医療ルポ:宮城県本吉郡南三陸町|歌津八番クリニック 鎌田 眞人先生
- レジデントロード:消化器内科 山内 陽平先生
- レジデントロード:心臓血管外科 細田 康仁先生
- レジデントロード:放射線科 塚原 智史先生
- 医師の働き方を考える:様々な背景を持った人が活躍できる環境を整えたい
- 日本医師会の取り組み:有床診療所の役割
- 日本医師会の取り組み:日本医師会ワールドメンバーズ ネットワーク(JMA-WMN)
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医科学生総合体育大会:東医体/西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:埼玉医科大学「臨床入門1年 小中学校教育体験実習」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- ドクタラーゼについて
- FACE to FACE:田中 ジョン 寛顕 × 永井 久子

