
「産みたい人が産みたいときに
産み、育てる」ための支援(前編)
学校や職場、地域で性知識を啓発
このページでは、「産みたい人が産みたいときに産み、育てる」を支援するためにどのような働きかけが必要で、そこに医療者はどのように関わることができるのかについて考えていきましょう。こうした働きかけがなされるのは、医療機関に限ったことではありません。学校や職場・地域においても、医療者が役割を担うことがあります。
まずは性別や将来子どもが欲しいか否かにかかわらず、すべての人が自分の体や性知識、妊娠の仕組みについて学ぶ機会を作る必要があります。望まない妊娠や性感染症の蔓延を防ぎ、産みたい人が「いつ産みたいか」などを考えられるようになるためにも、正しい知識を持つことは必須だからです。
そのためにはまず、学童期からの啓発が重要です。今の日本は、全国的には性教育が充実しているとは言いがたい状況ですが、学校医や産婦人科医、助産師、保健師などの専門家が学校と連携し、出張授業を行うなどの取り組みが各地域で行われ始めています。
次に重要な役割を果たすのが、職場や地域単位での啓発です。学校を卒業すると、性に関して正しい知識を得たり、日常的に相談できる機会がさらに少なくなります。特に女性は、月経に伴う不調などを抱え込んでしまったり、ときには将来の不妊につながるような疾患を、知らずに放置したりしてしまいがちになります。最近は、社員の健康増進に力を入れる企業も増えていますが、産婦人科領域のことが顧みられることはあまり多くありません。産業医などが産婦人科領域の十分な知識を身につけ、積極的に関わっていく必要があります。また、非正規雇用や自営業・フリーランス、または専業主婦などの人たちに対しても、地域で知識を啓発していくことが望ましいでしょう。
医療機関にできること
さて、ここまで主に啓発活動について考えてきました。多くの人が十分に知識を持ち、適切なタイミングで医療機関にかかれるようになったら、医療機関はどのようなことに注力すべきでしょうか。
月経痛や月経前症候群(PMS)、子宮内膜症などの一般的な婦人科診療や、妊婦への妊娠・出産に関する教育はもちろん重要です。また最近では、小児・若年世代のがんに付随する「妊孕性*の温存」というトピックに注目が集まっています。集学的治療の進歩によってがん患者の生存率が改善する一方、性腺機能不全や妊孕性の低下などが生じて治療後のQOLに影響することが問題となり、妊孕性温存療法の重要性が広まりつつあります。原疾患を悪化させたり、治療を遅れさせたりしないことが大原則ではありますが、近年は様々な技術革新が起こり、より多くの人が妊孕性温存療法に臨みやすくなっています。
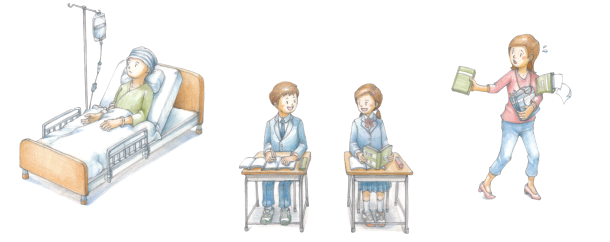
*妊孕性…妊娠する能力のこと。

「産みたい人が産みたいときに
産み、育てる」ための支援(後編)
キャラクター紹介
医師と助産師のキャラクターが、記事の重要なポイントを案内してくれます。
医師 助産師


学校

発達段階に応じた性教育
現在、都道府県医師会が中心となり、地域での学校保健や健康教育活動を展開しています。性教育についても、各学校や地域の実情に合わせて行うことが望ましいのですが、産婦人科を専門とする学校医はあまり多くはありません。そのため、地域の医師会や産婦人科医会と教育委員会や学校現場が連携し、学校に産婦人科医を「協力医」として派遣するなどの取り組みが行われています。
 月経不順や月経痛など、思春期の女性の体調に関わる問題についても、専門知識を持つ医師が、もっと学校現場に入っていけるような仕組みができると良いですね。
月経不順や月経痛など、思春期の女性の体調に関わる問題についても、専門知識を持つ医師が、もっと学校現場に入っていけるような仕組みができると良いですね。
 地域の助産師会と連携し、助産師を学校に招いて性教育を行っている自治体もあるようです。
地域の助産師会と連携し、助産師を学校に招いて性教育を行っている自治体もあるようです。
職場・地域

女性特有の健康課題解決
女性の社会進出が進む一方で、多くの職場では月経不順や月経痛、月経前症候群などの女性特有の健康課題が重視されていません。そこで現在、国や各自治体、医療や教育現場、職場や家庭、地域などが一丸となって女性の健康推進に取り組むことを目指す「ウィメンズ・ヘルス・アクション」などの活動が行われており、賛同する企業や自治体も少しずつ増えています。
 産婦人科の知識を持つ産業医などの存在も、今後ますます求められていくのではないかと思います。
産婦人科の知識を持つ産業医などの存在も、今後ますます求められていくのではないかと思います。
 産婦人科は「妊娠した人が行く所」というイメージが強く、受診をためらってしまう若い女性も多いようです。もっと気軽に医療機関に相談できる環境を作りたいですね。
産婦人科は「妊娠した人が行く所」というイメージが強く、受診をためらってしまう若い女性も多いようです。もっと気軽に医療機関に相談できる環境を作りたいですね。
医療機関

知識の啓発と的確な診療・ケア
妊孕性の温存
若年がん患者には、がんの治療前に妊孕性の低下についての説明やカウンセリングを行い、妊孕性温存療法の選択肢や適応などについて、迅速な情報提供をすることが推奨されています。そのためには、原疾患の主治医や生殖医療を提供する医師、看護師や薬剤師、心理士などの多職種が連携して、患者さんの自己決定を支援していく必要があります。2017年には日本癌治療学会による「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」が発刊され、現在各地域で「がん・生殖医療連携ネットワーク」が立ち上がり始めるなど、若年がん患者への妊孕性温存のアプローチは少しずつ進んできています。
不妊治療
妊娠を望んでいる健康な男女が避妊をせず性交しているにもかかわらず、一定期間妊娠しないことを「不妊」と言います。不妊の原因は、男性側、女性側、あるいはその両方にあり、複数の因子が重なっている場合や、どこにも原因が見つからない場合があります。
男性側もしくは男女両方に原因があるケースは全体の48%とされ、男性も並行して不妊検査を行う必要があります。しかし、男性不妊症に関する一般の認知度は十分ではないため、啓発が必要です。
不妊治療を行う場合、患者の経済的負担に加え、多くの場合、女性側に身体的にも精神的にも負担がかかりやすくなります。治療を行っても、必ずしも妊娠に至らないこともあります。そのため、精神的なケアも必要となります。
男女共に、加齢により、自然に妊娠する力は少しずつ減っていきます。しかし、例えば全身性エリテマトーデスなどは、妊娠可能年齢の女性が罹患しやすいとされています。産婦人科以外の医師も、このような疾患を診る際は、患者のライフプランや妊娠・出産のタイミングにも配慮して治療計画を立てる必要があります。
 月経異常や性感染症などの知識はもちろん、風しんワクチンやHPVワクチンなどの接種の必要性なども、医療機関と地域社会が協力して、幅広い世代に啓発していく必要があります。特に風しんは、流行を防いで先天性風しん症候群を予防することが重要です。抗体保有率が低い世代の男性に、原則無料で抗体検査や予防接種を受けられるクーポンを配布するなどの対策が講じられていますが、利用率は低いため、利用を促すアプローチが必要です。
月経異常や性感染症などの知識はもちろん、風しんワクチンやHPVワクチンなどの接種の必要性なども、医療機関と地域社会が協力して、幅広い世代に啓発していく必要があります。特に風しんは、流行を防いで先天性風しん症候群を予防することが重要です。抗体保有率が低い世代の男性に、原則無料で抗体検査や予防接種を受けられるクーポンを配布するなどの対策が講じられていますが、利用率は低いため、利用を促すアプローチが必要です。
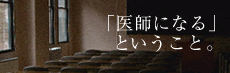


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:柳沢 正史先生
- Information:Spring, 2020
- 特集:「お産」を取り巻く医療と保健
- 特集:「産みたい人が産みたいときに産み、育てる」ための支援
- 特集:妊娠から分娩までの流れ
- 特集:分娩の流れと様々な対応
- 特集:産後の母子のフォローアップ
- 特集:おわりに~周産期医療体制のこれから~
- 同世代のリアリティー:新聞記者 編
- チーム医療のパートナー:看護師(認知症看護)
- 地域医療ルポ:広島県豊田郡大崎上島町|ときや内科 釈舎 龍三先生
- レジデントロード:防衛医科大学校 西井 慎先生
- レジデントロード:自治医科大学 増田 卓哉先生
- レジデントロード:産業医科大学 田渕 翔大先生
- 医師の働き方を考える:これからの医師に求められるのは、人の話を聴く心構え
- 日本医師会の取り組み:介護保険制度の今後と医師の役割
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:名古屋大学「地域における専門職連携教育 つるまい・名城IPE」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- FACE to FACE:Sopak Supakul ソパック・スパグン(パック)× 後藤 郁子

