授業探訪 医学部の授業を見てみよう!【前編】
産業医科大学「スポーツ傷害と整形外科」
スポーツで起こりやすい怪我を動画で学ぶ!
主に膝と肩の関節について、解剖図やレントゲン写真を見ながら、仕組みや可動域を理解します。また実際にゲームのプレイ中に選手が大怪我を負った動画などを見て、どのような傷害が起こるかを学びます。
実際の診療を動画で見られる!
問診や診断のやり方を、実際の診療の動画を見ながら学びます。例えば診断方法ではラックマンテスト*1、治療方法では徒手整復*2の仕方などを、エビデンスに基づき学んでいきます。
先輩医師の数多くがスポーツドクターとして活躍!
内田先生が診療科長を務める産業医科大学若松病院スポーツ整形外科は、様々なプロスポーツチームからの信頼を得ています。在学時にこの講義を受け、スポーツ整形外科を志した産業医科大学卒業生も数多くいます。
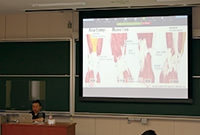


(写真中央)内田先生が実際に診察をしている動画を見て学びます。
(写真右)産業医科大学若松病院スポーツ整形外科チームの皆さん。
*1ラックマンテスト…前十字靭帯損傷の程度を判定する診断方法
*2徒手整復…手技によって関節の脱臼や骨折を元通りにする治療法
授業探訪 医学部の授業を見てみよう!【後編】
INTERVIEW 授業について先生にインタビュー
卒業後の日常の診療に役立ち夢を持って医師を目指せる授業にしたい
「スポーツ傷害と整形外科」は4年生の必修科目の一コマとして設けられている授業です。2006 年に指名を受けて開講して以降、現在まで受け持っています。
一般の整形外科が、元の生活に戻ることを最終的なゴールとするのに対し、スポーツ整形外科の患者となるアスリートには、より高いレベルの柔軟性や安定性、敏捷性の回復が求められます。
私は産業医科大学を卒業後、日本で初めてスポーツ整形外科を設けた関東労災病院で研修を行いました。その後、27年間 J リーグのチームドクターを務めました。講義においては、そうした自身の経験も交えながら話をしています。
産業医科大は、卒業生のほとんどが産業医になる大学です。私も2年間産業医の経験がありますが、産業医という仕事は、患者となる社員の家庭での姿やこれまでの人生など、様々な背景を想像しながら診療にあたる必要があります。そのためには包括的な知識が要求されますし、また患者さんを自分一人で診ることができるか、あるいは専門の医師に診てもらったほうが良いのかという判断もできなければなりません。 これらはスポーツドクターの仕事にも共通する特徴なので、産業医としての基礎を学んでいる本学の卒業生は、スポーツドクターとしても厚い信頼を得ています。将来スポーツドクターになりたいという人はぜひ産業医科大へ来てもらいたいですね。
とはいえ、本学の学生たちは様々な診療科の産業医の道に進むので、産業医の日常の診療にも役立つような授業を心がけています。どの科に進むにせよ、若い頃は患者さんが教科書です。常にリスペクトし、謙虚に学ぶ姿勢を持った医師になってほしいです。
 内田 宗志先生
内田 宗志先生
産業医科大学若松病院 整形外科 准教授(診療教授)
学生からの声
不安に寄り添える医師になりたいです
 5年 上前 晃平
5年 上前 晃平
僕が以前、スポーツ整形外科に通院した際、通常のリハビリより苦しかったものの治療後は不安なく競技に復帰できたのですが、授業を受けてその理由がよくわかりました。当時の治療とこの授業を受けた経験をもとに、患者さんの不安に寄り添える医師になりたいです。
患者さんの背景への想像を大事にします
 6年 彌富 健太
6年 彌富 健太
授業を通して、スポーツ整形外科は復帰を見越して医療の選択をしていかなければいけないということを知りました。医師は患者さんを診る際は病気の診療だけを重んじるのではなく、患者さんの背景にまで思いを巡らせることが大事なのだと学びました。
スポーツ整形外科の重要性を学びました
 5年 兼田 大暉
5年 兼田 大暉
プロスポーツの世界においても医師や医療従事者が大事な役割を果たしていることを知って、視野が広がりました。授業では実際に起きた試合中の重大な事故の映像を見ることもあり、アスリートを守るという重要な任務を背負った診療科なのだと実感しました。
他科の治療にも学びを活かしたいです
 5年 張 大暁
5年 張 大暁
スポーツ整形外科は復帰後に患者さんが120%くらいの能力を獲得できるように治療するという言葉が印象に残りました。他科の治療でも、単に病気が治るかというだけでなく、患者さんが元の日常生活にどれくらい戻ることができているかを考えることが重要だと感じました。
※取材:2021年5月
※取材対象者の所属は取材時のものです。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:河村 朗夫先生
- Information:Summer, 2021
- 特集:「専門医」がわかる 国民に信頼される専門医制度をつくるために
- 特集:専門医には何が求められるのか
- 特集:専門医を養成する仕組み
- 特集:専門研修プログラムをどのように選ぶか
- 特集:専門医のソノサキ
- 特集:専門医への道のり 内科系
- 特集:専門医への道のり 外科系
- 同世代のリアリティー:コロナ禍で入社して 編
- チーム医療のパートナー:栄養サポートチーム
- Blue Ocean:岩手県|畠山 翔翼先生・畠山 彩花先生(岩手県立中央病院)
- 医師の働き方を考える:家族と共にスウェーデンで医師として生きる
- 日本医師会の取り組み:薬事における日本医師会の役割
- 日本医師会の取り組み:医師の働き方改革と地域医療
- 日本医科学生総合体育大会:オンライン東西医体座談会
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:産業医科大学「スポーツ傷害と整形外科」
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- FACE to FACE:天野 将明 × 田邉 翼

