大学紹介
旭川医科大学
【教育】道北・道東の医療を担う人材の育成
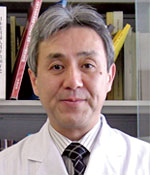
教育センター長 教授 千石 一雄
本学では、グローバル化する医療に対応するため、国際的に貢献できる医療技術と知識を有し、その基盤に立脚し地域医療の核としても活躍できる医療人や研究者の育成を教育の目標としています。この目標を実現するためには、生涯に亘り学習する習慣を身につけることが必要です。
学びを動機づけ、自学自習の習慣形成を養うため、1年次より一般教養科目の課題に対し小グループによるチュートリアル教育を取り入れ、問題抽出、解決能力、自学自習の涵養を進めています。
医療人として重要である、高い生命倫理観、豊かな人間性を育成するためリベラルアート教育にも力を入れており、また、1, 2年次には医学科・看護学科合同で「早期体験実習I, II」として介護や養護施設の体験実習を行い、病める人を思い遣る心の涵養、医学を学ぶモチベーションの向上、チーム医療の実践、コミュニケーション能力の向上を目指します。
また本学は北海道、特に道北・道東地域の医療の中核を担う人材の育成が使命の一つであり、初年次より地域医療を担っている現役の講師を招聘し「地域医療学」の実践講義を展開するとともに、地域に密着した医療の現場を学ぶ機会を用意しています。3年次後期より臨床・基礎の各講座に学生を配属し、実践的な医学英語教育や最先端の医学研究を体験し、国際的視野を持つ医療従事者の育成にも重点を置いています。4年次には臓器別講義と並行し、臨床症例課題に対する医学チュートリアルを開講し臨床推論の知識を養い、4年後期からは本学病院を中心にクリニカルクラークシップを主体とする充実した臨床実習を行い、十分な医学知識と高い実践的臨床能力を身につけます。この臨床能力を担保するために、卒業時にアドバンスOSCEの導入を計画しており、現在トライアルを実施しています。
【研究】幅広い研究への門戸が開かれています

旭川医科大学教育研究推進センター長
教授 船越 洋
本学では教養・基礎・臨床共に活発に研究活動を行っており、そこに医学科の学生が学部生時代から参加することで、卒業までに研究の基礎を学ぶ機会があります。
臨床に即した研究としては、(1) 次世代医療を担う高度情報通信機器を活用した遠隔医療実用化研究により、1997年には世界に先駆けて三元遠隔医療を旭川市立病院、本学眼科医局とハーバード大学間を結んで成功し、その成果は旭川医大方式(三次元(3D))による隣国、中国の4医療機関と本学を結ぶ「中日遠隔医療プロジェクト」として2011年に実りました(本学吉田学長が2011年9月文部科学大臣賞を受賞)。
さらに (2) 文部科学省の橋渡し研究プロジェクトとして整形外科教室の「ゆるむことのない新規人工関節」、呼吸器センターの世界初の「フルカラー蛍光内視鏡」、寄生虫学講座による「エキノコックス症診断キット開発」等の臨床研究や、内科学講座血管再生チームによる心血管系の再生医療を目指した研究も進行中です。
基礎研究は、教養の生物学教室では生殖工学の先端研究を、生命科学科においてアルツハイマー病の研究が行われており(過去にNature誌に掲載)、基礎講座では生化学、解剖学、薬理学、病理学講座などで日本トップレベルの先端研究が進められています。
また、教育研究推進センターでは活発な神経再生研究が行われており、HGFのALSへの治療効果の基礎研究成果が東北大学病院で臨床相I相の治験へと発展しています。さらに多くの神経難病への治療効果に対する神経再生研究が進行中で、プロジェクトには医学科の1~4年生9名が参加するなど、臨床から基礎の教室まで医学科学生や若い医師達に研究への門戸が開かれています。
本学では米国、ヨーロッパをはじめとした海外の先端研究室との研究交流も行われています。
【学生生活】地域に根差したアットホームな雰囲気
旭川医科大学医学科5年 早坂 太希、同4年 福山 秀青、
同1年 フェアウェザー 未央 ジューン、看護学科1年 遠藤 ゆきの
早坂:旭川医大は「地域医療を支える」という使命を負っていると感じます。僕は、「地域医療を考える会(CIK)」という勉強会に参加しており、いくつもの地域の病院に実習に行かせていただいたのですが、どこの病院も「地域の医学生を育てる」という意識があって、よく面倒を見て下さいました。
フェ:以前は北海道外からの学生が多く、卒業すると地域を離れる人も多かったと聞きますが、最近はAO入試や地域枠の人数も増え、1年生は約7割が道内の出身者です。地域の高校との連携にも力を入れていて、私の出身校では、半年に一度くらい旭川医大の先生による授業や講演会が開催されていました。入学前から大学にはお世話になっており、卒業後も地域に残って恩返しする…そんなマインドの学生も多いです。
遠藤:私も高校生の時に旭川医大のイベントに参加し、そこで出会ったフェアウェザーさんと放送部つながりで盛り上がったんです。入学式の時に再会して、この大学には放送部が無いね…って話をしているうちに、じゃあ作ろうかってことで放送研究会を作ってしまいました。
福山:僕は今CIKの代表をしているんですが、地域医療に関して我々学生が発信していく必要性を感じています。うちの大学は学生支援課が学生の活動を応援してくれる雰囲気があり、こうやって放送研究会もできた。何か一緒に発信していければいいなと思って、今日も呼んでみたんです(笑)。
早坂:道内の出身者が多く、地域で医師を育てていくという文化、アットホームな雰囲気はとてもいいと思います。けれど他の大学からも離れていて、交流する機会も少ないので、もっと他大学や他学部と交流するよう取り組んでいきたいですね。
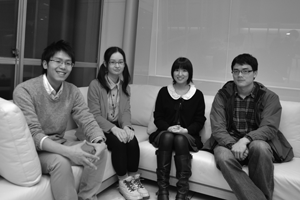

〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1-1-1
0166-65-2111



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:石本 崇胤先生
- 特集:地域の救急医療を支えるしくみ
- 特集:救急医療機関の役割分担と搬送手段
- 特集:救急医療を支える様々な搬送手段
- 特集:医学生が取材!救急医の役割とやりがい
- 特集:自己完結型のセンターで、あらゆる救急医療を担う
- 同世代のリアリティー:職場の人間関係 編
- NEED TO KNOW:医療者のための情報リテラシー
- チーム医療のパートナー:理学療法士
- 地域医療ルポ:茨城県常陸太田市里美地区|大森医院 大森 英俊先生
- 先輩医師インタビュー 田原 克志 (医師×医系技官)
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 石澤 香野医師
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 竹下 有美枝医師
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 黒田 暁生医師
- 医師会病院の運営~板橋区医師会病院~
- 日本医師会の取り組み:日本医師会医学図書館
- 医師の働き方を考える:子育て支援が医局を活性化する
- 医学教育の展望:1年生から症例に学ぶ
- 大学紹介:旭川医科大学
- 大学紹介:北里大学
- 大学紹介:大阪大学
- 大学紹介:久留米大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- DOCTOR-ASE COMMUNITY サークル・医学生の活動紹介
- BOOK-書評-
- 日本医師会の取り組み:Q&A about JAPAN MEDICAL ASSOCIATION

