大学紹介
大阪大学
【教育】大阪大学医学部の卒前教育
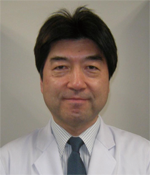
医学部医学科教育センター 和佐 勝史
緒方洪庵が開いた適塾が大阪大学医学部の源です。われわれの使命は、高度な倫理観と探究心をもち、世界の医学・医療をリードするスペシャリストを育成することにあり、そのための最先端の基礎医学および臨床医学を習得できる教育体制が整っています。
1年次から名誉教授や臨床系教授による医学序説を開講し、歴史的な研究成果をあげた経緯や最先端の臨床医学の講義を聞くことができます。3年次では二つの特色あるプログラムを用意しています。選択必修科目では、ゲノム科学や癌生物学など10の研究分野から一つを学生が選び、最先端の知識を身に付けます。また基礎医学講座配属では、4か月間希望する基礎医学講座に配属され研究に専念します。この期間に英文医学雑誌に掲載されるような研究成果を挙げる学生がたくさんいます。4年次から臨床医学の講義、実習が開始されます。臨床実習では附属病院と関連基幹病院において、先進医療と同時に臨床医として必要な態度、知識、技術を習得します。また、海外の提携校への短期臨床留学も可能です。
将来、研究者を目指す学生に対しては、「MD研究者育成プログラム」を実施し、世界をリードする研究能力と国際的視野を備えた医学研究者を養成することを目指します。1・2年次は希望者全員が参加し、基礎医学系教室の研究紹介や教室体験などで、医学科で実施されている研究を実体験できます。3年次からは特定の基礎医学教室または附属研究施設に所属し本格的な研究を開始します。具体的には、研究手法・論理的思考力・情報収集能力・プレゼンテーションやディスカッション能力を養います。また、学会発表や海外留学も積極的にサポートし、奨学金制度も準備しています。
【研究】世界をリードするイノベーションの創出
大阪大学大学院医学系研究科長・医学部長 米田 悦啓

世界をリードする独創的な医学研究・生命科学研究を追求し、もって先進医療に貢献することを使命としている。「地域に生き世界に伸びる」をモットーとして、「世界に通じる」医学・生命科学の創造を推進するため、その基盤となる基礎医学研究の振興を図っている。特に、インターロイキン6研究や自然免疫研究に代表される免疫学、オルガネラネットワーク研究に代表される分子細胞生物学、iPS細胞、組織幹細胞の臨床応用を目指した再生医学、高次脳機能解明を目指した神経科学など、世界トップレベルを行く研究分野が数多くある。今後も、幅広い分野で世界トップレベルの基盤研究を継続的に推進していくことが最も重要であると考えており、その継続的な基盤研究推進のためには、基盤研究を革新的なイノベーション創出につなげ、社会に見える形で貢献することが重要である。つまり、革新的なイノベーション創出の努力は、必ず次の基盤研究推進の強力なエンジンになると考えている。このような観点から、1つのイノベーションとして「創薬」をテーマに掲げている。日本発の革新的な医薬品創出を目指した取り組みを開始しており、大阪大学の基盤研究の成果を難病治療薬の開発につなげ、臨床応用を可能にする拠点を学内に整備し、基盤研究成果がシームレスに臨床治験にまで進むことのできる体制を確立することができればと考えている。さらに、医学研究・医療上の種々の課題解決のため、医学と歯学・薬学・工学・理学・情報科学などの異分野融合による新しい学際的研究領域の創成とその医学研究・先進医療への応用展開を進めている。また、医学研究・生命科学研究のキーテクノロジーの一つである生体分子イメージングのための施設・組織の整備を進めており、学内の他の研究施設との緊密な連携を通して、国内唯一の生体分子イメージング研究拠点の構築を目指している。
【学生生活】研究マインドと「ちょうどよさ」
大阪大学医学部4年 原田 昭和 、
同5年 長谷川 然

長谷川:私は慶應義塾大学の理工学部に入学しましたが、阪大医学部に毎年10人前後の編入枠があることを知って、3年次に阪大医学部へ編入してきました。現役と浪人の比率は1:1くらい。女性は全体の2割くらいですかね。他の大学と比べるとちょっと少ないのかな、と思っています。
原田:「研究マインドを持った医師を育てる」ということを多くの先生が言っています。臨床をやる時も、常に研究の意識を持つことが大事だということだと思います。阪大には「MD研究者育成プログラム」というものがあって僕も参加しているんですが、これは入学時から研究室に参加して基礎研究の手法や基本的な思考能力、医学英語などを習得するプログラムで、各学年で基礎研究に関心のある学生10人ほどが参加しています。
長谷川:早いうちから国試に向けて熱心に勉強する私大医学部と比べると、国試向けの勉強に対するコミットメントは強くはないのかなと感じます。やりたいことをやりたい時にやる雰囲気があって、それが人によって国試の勉強であったり、部活であったり、恋愛であったりする。そういう、各々の主体性に任せるところが阪大の良さなのかな。
原田:阪大は教養の授業が難しいと言われています。何と言っても教養の授業を受けるキャンパスが離れている関係で再履修が事実上不可能なので、単位を落とすこと≒留年ということになってしまいます。5人以上の留年者を出す授業もちらほら…。
長谷川:京都大学と比べられることが多いですが、京大は先生も放任主義で学生も変わった人が多いというイメージ。阪大は真剣にやる学生には先生もしっかりサポートしてくれるし、学生の雰囲気も真面目過ぎず軽過ぎず、「ちょうどいい」感じなんです。
原田:阪大吹田キャンパスの周りには、飲めるお店が全くと言っていいほどないんです。最寄り駅を利用するのは病院に来る患者さんが主なので、あまり飲食店ができないんですよ。飲む時には電車で30分以上をかけて梅田まで出て行くことがほとんどです。僕は京都の河原町あたりで遊んだりしています。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
06-6879-5111



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:石本 崇胤先生
- 特集:地域の救急医療を支えるしくみ
- 特集:救急医療機関の役割分担と搬送手段
- 特集:救急医療を支える様々な搬送手段
- 特集:医学生が取材!救急医の役割とやりがい
- 特集:自己完結型のセンターで、あらゆる救急医療を担う
- 同世代のリアリティー:職場の人間関係 編
- NEED TO KNOW:医療者のための情報リテラシー
- チーム医療のパートナー:理学療法士
- 地域医療ルポ:茨城県常陸太田市里美地区|大森医院 大森 英俊先生
- 先輩医師インタビュー 田原 克志 (医師×医系技官)
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 石澤 香野医師
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 竹下 有美枝医師
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 黒田 暁生医師
- 医師会病院の運営~板橋区医師会病院~
- 日本医師会の取り組み:日本医師会医学図書館
- 医師の働き方を考える:子育て支援が医局を活性化する
- 医学教育の展望:1年生から症例に学ぶ
- 大学紹介:旭川医科大学
- 大学紹介:北里大学
- 大学紹介:大阪大学
- 大学紹介:久留米大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- DOCTOR-ASE COMMUNITY サークル・医学生の活動紹介
- BOOK-書評-
- 日本医師会の取り組み:Q&A about JAPAN MEDICAL ASSOCIATION

