大学紹介
久留米大学
【教育】久留米大学のユニークな医学教育
医学教育学 教授 神代 龍吉
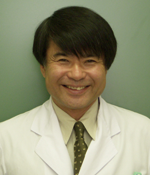
久留米大学ではコアカリキュラムのほかにユニークなものがいくつかあります。
1.選択制セミナー(1~4年生)
医学部の各講座が用意するメニューから一つを選び、週1回放課後に半年間、講義や実習体験をします。学年の域を越えて自主学習にいそしみ、学年間の交流も生まれます。「USMLE Step 1 Biochemistry」、「心電図セミナー」、「救急医療の実際」、「真の地域医療を求めて医学生は大学の外へ」など20のメニューがあります。「真の地域医療~」は学生が一般家庭を訪問し、その家の健康や医療に関する問題や悩みを取材する実習です。
2.医療科学(1~4年生)
様々な分野の講師が、医師となるうえで大切なことを話しに来ます。「JICAによる海外支援」、「献体」、「なぜ人に生まれてきたのか」(高僧による講話)、「医事紛争」、「遺伝カウンセリング」、「医療安全」、「医療経済」など多岐にわたっています。
3.医師国家試験に対する手厚い指導(6年生)
①卒前医学教育総括講義:6年生の9月から2か月間、国家試験を意識した総括講義を毎日5コマずつします。日本医師会長(本学出身の横倉義武氏)の講話もあります。毎週、確認テストが組まれています。②国試予備校指導の導入:予備校講師の個人指導と模擬試験受験料を大学が負担し、教材購入も援助しています。国試浪人者にも密に連絡をとり激励会を開催します。③成績低迷者学習会:6年次の12月からは成績が伸びない学生さんに教室を開放し自主勉強会をする場所を提供しています。
久留米大学では、「良き臨床医を育てる」という理念の下、手厚く、親切な指導体制を取っています。
【研究】肝炎、肝疾患の撲滅を目指して
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 井出 達也
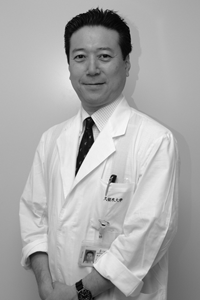
本学は九州のほぼ中央に位置し、筑後川沿いにあります。古くは日本住血吸虫症の研究が行われ、また肝疾患の多い地域として、その基礎から臨床まで幅広く研究されてきました。当消化器内科は肝胆膵・消化管すべての分野で基礎および臨床研究が行われていますが、今回は肝炎関連の研究について述べます。1970年代後半に小学校での大流行をはじめとするA型肝炎の流行がみられましたが、そのことを契機にウイルス肝炎の研究が活発に行われるようになりました。糞便中のウイルスの排泄状況が明らかにされ、分離したウイルスをもとにワクチンが作られました。またA型肝炎が貝などで濃縮されることも解明しました。B型肝炎では核酸アナログという経口抗ウイルス剤を用いた初めての治験で中心的な役割を担い、また核酸アナログの耐性ウイルスが治療前から微量に存在する事を初めて報告しました。B型肝炎ウイルスの遺伝子変異も治療効果に重要なことからその研究も行っています。一方、C型肝炎では1980年代後半からインターフェロン治療に取り組み、基礎及び臨床研究を行ってきました。いまではインターフェロン治療を受けた患者は2000名を超えていますが、1990年代からPCR (polymerase chain reaction)法をいち早く取り入れ、患者血清中にあるC型肝炎ウイルスの遺伝子解析を行っています。とくにウイルスの複製に必要な遺伝子の変異が治療効果に関わる重要な因子であることを解明しつつあり、臨床への応用が期待されます。
患者さんの臨床的データを解析する臨床研究も重要ですが、基礎研究によってさらに多くのことが明らかにされ、病態解明や治療への応用が進歩します。肝疾患も未だ不明なことが山ほどあり、その解明に向かって日々研究の毎日です。
【学生生活】OB・OGとのつながりが強く、チームプレイが得意
久留米大学医学部医学科3年 二見 俊人

久留米大の特色は、なんと言っても長い大学の歴史に裏打ちされたOB・OGとのつながりの強さでしょうね。ほとんどの学生が何らかの部活に所属しており、病院実習に行った先でも「君は何部?ならあいつは知ってる?」と聞かれるほど、縦のつながりが強いんです。僕も30~40歳の先輩の家に呼ばれてバーベキューをしたりします。
キャンパスの隣を流れているのは久留米大生の心のオアシス、筑後川です。休日には自転車で筑後川沿いをサイクリングする学生も多いんですよ。自然に溢れたアットホームな雰囲気だから勉強に集中できますし、逆に買い物をしたい時なんかは電車に30分乗れば福岡市の天神まで行けるという利便性も久留米大の良い所だなと思っています。
僕自身はバスケットボール部の主将を務めています。久留米大バスケ部は西医体で7年連続1回戦負けという状況なので、全員が一丸となって1勝を目指しています。練習は3時間を週に3日です。自分が練習のメニューを決めておきながら言うのも変ですが、はっきり言って練習はきついです。でも練習後のビールの味は格別ですよ(笑)。
久留米大生が飲む時は歩いて20分くらいの距離にある文化街という歓楽街に行くことがほとんどです。昭和の雰囲気が残っている町並みはノスタルジックで、かなり気に入ってる場所の一つですね。
久留米大の先生は意欲のある学生に対してはとても協力的なので、やる気のある学生は1年生の頃から研究室に出入りしています。試験期間になるとみんなの結束力が高まるので、学生同士で分からない内容を教え合ったりします。人によって得意な分野と不得意な分野があるので、それを補いながらみんなで勉強するんです。国試はチーム戦だと先輩からよく聞くんですが、久留米大生は低学年の時からチームプレイを大事にしているんだなと感じます。そうやって日頃から培ったチームワークで国試を突破して、自分もOB・OGの仲間入りをしていくんですね。




- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:石本 崇胤先生
- 特集:地域の救急医療を支えるしくみ
- 特集:救急医療機関の役割分担と搬送手段
- 特集:救急医療を支える様々な搬送手段
- 特集:医学生が取材!救急医の役割とやりがい
- 特集:自己完結型のセンターで、あらゆる救急医療を担う
- 同世代のリアリティー:職場の人間関係 編
- NEED TO KNOW:医療者のための情報リテラシー
- チーム医療のパートナー:理学療法士
- 地域医療ルポ:茨城県常陸太田市里美地区|大森医院 大森 英俊先生
- 先輩医師インタビュー 田原 克志 (医師×医系技官)
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 石澤 香野医師
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 竹下 有美枝医師
- 10年目のカルテ:糖尿病・代謝内科 黒田 暁生医師
- 医師会病院の運営~板橋区医師会病院~
- 日本医師会の取り組み:日本医師会医学図書館
- 医師の働き方を考える:子育て支援が医局を活性化する
- 医学教育の展望:1年生から症例に学ぶ
- 大学紹介:旭川医科大学
- 大学紹介:北里大学
- 大学紹介:大阪大学
- 大学紹介:久留米大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- DOCTOR-ASE COMMUNITY サークル・医学生の活動紹介
- BOOK-書評-
- 日本医師会の取り組み:Q&A about JAPAN MEDICAL ASSOCIATION

