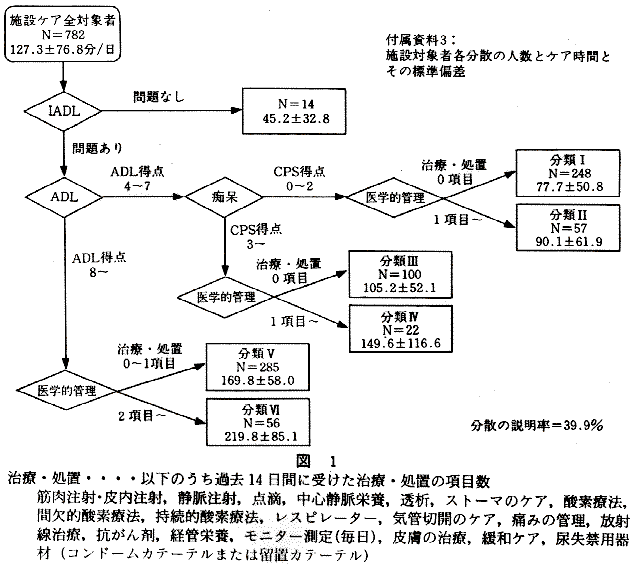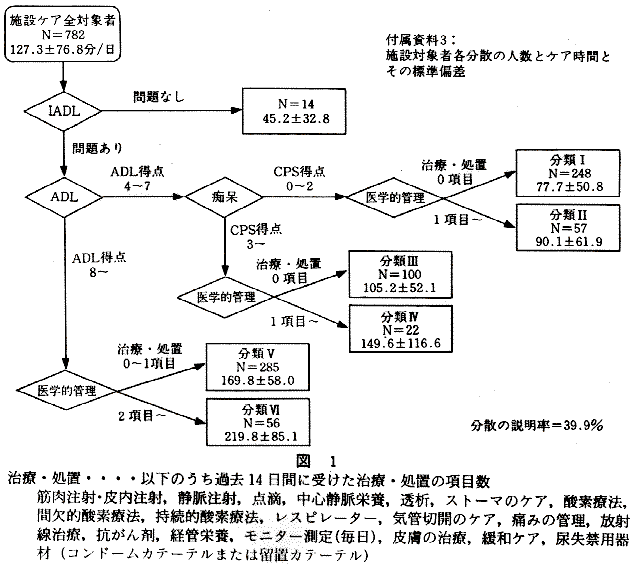
日医ニュース 第870号(平成9年12月5日)
日医の「要介護度総合分類」、その方法と有効性
介護保険法が施行されて、いよいよ実務を開始する場合に、一番重要なのは、「どのように要介護認定を行うか」である。
先般、厚生省の「平成8年度モデル事業」の報告会が開かれ、そこで提示された「要支援・要介護認定分類案」については、1)各分類の状態像がわかりにくいこと 2)医療面が反映されていないことなど、多くの問題点が浮上した。そこで、日医総研では、池上直己慶大医学部教授を主任研究員とする日医介護プロジェクト委員会に、「よりわかりやすい」新たな分類法の開発を委託した。このほど、その中間報告がまとまったので紹介する。
−日医の「要介護度総合分類法」について−
介護保険では、介護と医療が一体的に提供できることが必要で、日医介護プロジェクト委員会が開発した分類法は、この目的をクリアしながら、しかも、きわめてシンプルなところに特徴がある。まず、現場の実態を踏まえて、要支援・要介護を決める「IADL(手段的日常生活能力)」、「ADL(日常生活動作)」、「痴呆の状態」、これら3つのアセスメント項目によって、要介護者の状態像を明確に規定し、さらに、それとは独立的に、もう1つの指標である「医学的管理の必要性が中程度以上であるかどうか(分類IとII、分類IIIとIVの分岐点となる)」を評価し、6つに分類する(表1)。なお、「痴呆の状態」の判定尺度にはCPS(認知行動評価尺度)を用いる。
IADLは「問題あり・なし」に二分され、ADLおよび痴呆はスコア化されている。医学的管理は―基本的には要介護者の全例に必要と考えられるが−ここでは一応、アセスメント項目として各種の医療処置を列挙し、「0(零)」「1つ以上」「2つ以上」にスコア化した(表2)。
これまでは、どちらかというと介護だけの狭い視点での分類法が提案されてきたが、この分類では、「医学的な管理」という指標も入れたので、「総合分類法」と呼ぶことにした。
−樹形モデル解析の使い方−
(1)樹形モデル解析図の見方
樹形図(図1)の左側には、IADL、ADLなど指標となる状態像と、分岐の方向を決める「スコア」が示されている。この「スコア」は、施設でのタイムスタディの結果に基づいて決めたものである。
実際にケアに要する時間(ケア時間)は、それぞれ分類の「囲み」のなかに(例えば、分類Iの要介護者のケア時間は77.7プラスマイナス50.8、分類IIのそれは90.1プラスマイナス61.9のように)示されている。平均値でみると、ケア時間は比較的増えていることがわかる。また、「囲み」のなかのNは実際に調査した症例数を示しており、分類IはN=248、分類IIはN=57である。
この「要介護度総合分類」により、老人病院、老人保健施設、特別養護老人ホームの入院・入所者782人の「ケア時間」の相違の39.9%が説明できる。また、在宅ケアを受けている第一段階の調査対象者181人の「ケア時間」の相違の36.0%も説明できる。この数字が「説明の分散率」で、分岐させるときの合致率を示しており、30%以上あれば高い説明率と考える。厚生省の報告書には、「分散の説明率」が示されていないため、要介護者が各分類にどの程度分布するかが明らかでない。
(2)在宅介護のケア時間
施設でサービスを受けている要介護者については、図1のように比較的きれいなデータが得られた。しかし、在宅で介護サービスを受けている要介護者の場合(表は省略)は症例数が少なく(N=181)、特に、分類IIIはN=7、分類IVはN=2と、かなりかぎられている。そのため、施設介護のケア時間と比較すると、かなりのバラツキが認められる。
一般的にいって、在宅ケアのタイムスタディの決定はかなりむずかしく、「ケア時間」を検討する場合は、1)家族の存在、2)インフォーマルな介護サービスを受けているかどうかなど、いろいろな要素が加わってくることを考慮に入れなければならない。何千例と集めて調査した厚生省の研究報告でも、在宅要介護者のケア時間については明確な結果が出ていないように思う。このようなことはあるが、施設サービスである程度実証されれば、日医介護プロジェクト委員会の「要介護度総合分類」は、十分使用に耐えられるのではないかと考えている。
−今後の対応について−
厚生省では、11月から12月にかけて、全国416地域(902市区町村)において、平成9年度のモデル事業を行うことにしている。日医としては、この際に、同一対象者に対して、「日医総合分類」の36項目のアセスメントも実施してもらって、両者の結果を比較したいと考えている。ただし、日医の分類の方は予算が付いていないので、市町村や地域医師会の理解と協力に期待することになる。このようにして、在宅サービスの症例数も増やし、現場の意見を通じて改善しながら、日医総合分類の有効性を実証し、その制度化に向け努力していきたいと考えている。
表1 要介護度総合分類の状態像
| 分 類 | 状態像 |
|---|---|
| 分類I | IADL(家事や金銭管理の能力)が低下 ADL介助はあっても、部分的援助に限られる 痴呆による問題はあっても、軽度である |
| 分類II | 分類Iと同じだが、医学的管理が中程度以上 |
| 分類III | IADL(家事や金銭管理の能力)が低下 ADL介助はあっても、部分的援助に限られる 痴呆による問題が中程度以上ある |
| 分類IV | 分類IIIと同じだが、医学的管理が中程度以上 |
| 分類V | IADL(家事や金銭管理の能力)が低下 ADL介助が中程度以上必要 痴呆による問題は問わない |
| 分類VI | 分類Vと同じだが、医学的管理が中程度以上 |
注:下線は当該分類の特徴
表2 要介護度総合分類の分岐項目と基準
| IADL (7分類) |
ADL (ADL得点) |
痴呆 (CPS尺度) |
医学的管理 (処置数) |
|
|---|---|---|---|---|
| 対象外 | 問題なし | |||
| 分類I 分類II |
問題あり 同上 |
4−7 4−7 |
0−2 0−2 |
0 1つ以上 |
| 分類III 分類IV |
同上 同上 |
4−7 4−7 |
3−6 3−6 |
0 1つ以上 |
| 分類V 分類VI |
同上 同上 |
8−15 8−15 |
問わない 問わない |
0−1 2つ以上 |