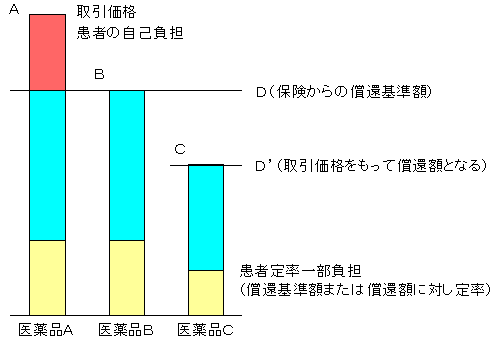
日医ニュース 第880号(平成10年5月5日)
国民が納得できる結論を
医療保険福祉審議会制度企画部会の経過報告
「診療報酬および薬価基準制度の見直し」について協議を続けていた、医療保険福祉審議会制度企画部会(金平輝子部会長)は、今国会への法案提出を断念した。当初は、本年3月の法案提出を目指して審議に入ったものの、厚生省が提案した「日本型参照価格制度」に議論が集中し、意見の集約が困難となったためである。そこで、委員である糸氏英吉副会長にその経緯について語ってもらった。
| 医療改革の基本的な方向づけ |
平成12年を目途に検討がすすめられている医療保険制度の抜本改革は、医療提供体制と医療保険の両面にわたった幅広いものになっている。
そのうち、医療保険福祉審議会制度企画部会では、診療報酬体系の見直し、薬価制度の改革、老人医療制度に関する事項、これに関連する医療保険制度のあり方などの基本的な方向を審議し、その結果を踏まえて、国会に法案を提出することになっている。
この部会は、昨年の11月に第1回の会合が開催されてから、4月中旬までに15回行われている。
第1回から第4回までは「診療報酬体系の見直しについて」、第5回からは「薬価基準制度の見直しについて」が主な議題となり、論議が進められてきた。
診療報酬体系については、「医療費の増大と医療関連コスト」「定額払いと出来高払い」「病院・診療所の機能分担」「患者のアクセスの問題」「技術料の問題」「現行の診療報酬の内容」などさまざまな角度から意見が出された。
経済学者からは、主に財政面から、いかにして医療費の無駄をなくし、コスト減をはかってゆくかという意見が出された。しかし、その論点には限界があり、しかも、彼らは生身の患者に対面する医療の現場を知らないという大きな欠点がある。
そこで、医療担当者としては、「患者さんの命にかかわる問題を経済面からの議論だけで済ませて、果たして本当に国民が幸福になれるか、安心して医療にかかることができるか」という意見を強調し、特に、急性期に定額払い制を導入すれば、医師の選択の幅が狭められて、ベストな治療が行えなくなる可能性があると指摘しておいた。
第5回の会合からは、薬価基準制度の議論に入った。これは現行の薬価基準制度を廃止し、新制度を導入することになった場合に法改正が必要になり、その時間的な制約を受けてのもので、短期間の間に何度も会合がもたれた。
議論の前提として、現行の薬価制度は、保険からの償還価格と実購入価格の薬価差が認められ、それが医療機関の収入に繋がり、薬が多用され、医療費を圧迫しているという厚生省側の認識がある。
厚生省は、現行制度に代わる日本型参照価格制度の導入を提案してきた。これはドイツをはじめヨーロッパで施行されている制度を基本にしたものである。
日医としては、終始一貫、この制度の導入に関しては反対し続けてきた。その理由は、のちほど詳細に述べる。
これに対し、他の委員は最初の頃こそ日本型参照価格制度の導入に積極的であったが、議論を進めるうちに、新制度導入で必ずしも薬価が下がるかどうかわからないこと、薬価の設定の仕方が不透明なこと、先発品、後発品の格差など製薬企業は日本特有の問題を抱え、新制度のもとでもその問題が解消されないことなどが認識され、現在では、日本型参照価格制度の導入には慎重な意見が多数を占めるにいたっている。
| 問題の多い日本型参照価格制度 |
厚生省は、わが国の医療費に占める薬剤費比率が、度重なる薬価引き下げにもかかわらず、ほとんど下がらない原因として、薬価差をあげている。このため、制度企画部会では、薬価基準制度を廃止して、薬価差が生じない新たな仕組みとして「日本型参照価格制度」を導入することの検討を行った。
この件について、私は、会合のたびに、繰り返し次の理由をあげて反対を主張してきた。
1)購入価格で請求すると従来の価格競争はなくなって医薬品の低価格化がおこらなくなり、高値安定となる。
2)購入価と請求価との突合整理等事務関連コストが大幅に増大する。
3)自由価格化により一物多価となり、同一品目でも価格にバラつきが生じ、患者が医療機関、医師を信用しなくなる。
4)医薬品の質と安全性に対する医師の信頼性が先発品に高く、後発品に低い現状では、参照価格制度を設定しても価格競争のインセンティブ(動機づけ)は働かず、低価格化よりむしろ高価格化の可能性が大きい。
5)償還価格以上の医薬品を処方すると、患者負担は大幅に増加するばかりか、保険診療と自由診療との二重負担、すなわち混合診療を是認することになる。
6)ブランドによる独占市場のなかでは、当然、償還価格はブランド価格に埋没する可能性が大きく、参照価格による低価格化は期待できない。
7)同種同効医薬品のグルーピングと償還価格を公定することになるが、その不確実性とその当否をチェックするシステムが不明である。
さらに、この制度を導入した場合、患者さんにとっては、自己負担額が必ず増え、医薬品価格とその品質安全性との因果関係の情報が不足しているので選択に困惑するだろう。また、同じ薬でも医療機関によって自己負担額が一定しないことなどが原因で、医療機関のみならず、医療システム全体に対する不信感が増大することは避けられない。
一方、医療機関にとっては、技術料の大幅な引き上げが担保されないかぎり、薬価差問題は解決されないし、むしろ医薬品費は増大するため、次は医療機関に対し医薬品費用の予算枠がはめられ、処方制限を強制されることになる。
以上の観点からも、この制度導入は断じて許されるべきものではない。今後、さらに検討が続けられることになっているが、日医としては、対策を提出して委員の理解を求めてゆくつもりである。
日本型参照価格制度
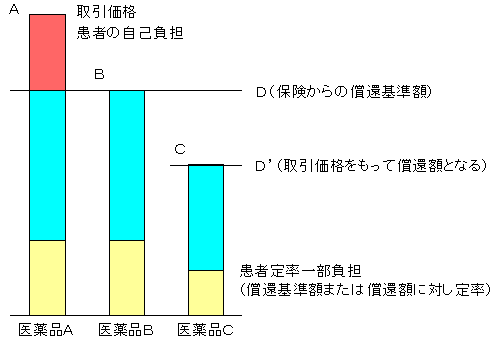
| 意見を羅列しただけの整理案 |
厚生省は、3月27日、制度企画部会のそれまでの検討内容をまとめた、「診療報酬体系のあり方についての整理」を公表したが、それについて納得しがたい点がいくつかある。
まず、医療費の伸び率を今後5%〜6%と予測をしているが、9月の健保法改正以降、被用者保険はマイナス成長になっており、実際には、1.5%くらいの伸びになっている、老人医療も、極端に低下しており、厚生省の見込みはおかしいのではないかと思う。
医療費の無駄の排除ということで、高額医療機器の導入、大病院への外来集中、高齢者の社会的入院、過剰な検査・薬剤使用について書いてあるが、これをもう少し慎重に分析していただきたい。高額医療機器によって早期に重大な疾患が発見され、社会的入院は、介護保険でかなりおさえられる。過剰な検査や投薬に対する批判があるが、医師が患者に十分な検査をして、しっかりとした診断をすることは当然である。
また、医療サービスを自由価格にしろという議論がある。しかし、公定価格であったからこそ、世界のなかでも対国内生産費で最低の医療費で抑えることができたのだと思う。市場原理が許されるならば、おそらく国の保険制度は根底から崩壊してしまうだろう。
それから、医療を総額予算制で縛ることが、果たして国民にとって幸せなことかどうかという問題がある。少なくとも医療の本質の部分については、人の命や健康というものを財政で縛るべきではない。総額予算で枠をはめることは、医療提供者にとっても自由の束縛になり、患者さんも受けるサービスが制限される。そのことが、QOLや生存権にまで影響を及ぼすので、総額予算制に対しては反対である。
急性期医療にも定額制を入れようという主張もあるが、急性期医療は予測困難なことが多い。臨機応変に医療を行っていくという立場上、出来高払いが機能的にも財政効果の面においても必要不可欠な制度であると思う。
出来高払い即悪という観念が定着しているが、出来高払いでも医療費を節減できると考えている。結果は必ずレセプトで請求しなければ支払いはされず、支払基金、保険者のチェック機能が働く。そういう意味でも、財政的な効果も十分にある。
この整理案は、いままで出た意見を羅列したものにすぎず、今後、引き続いて議論していかなければならないと考えている。
もっとも重大な問題は、与党医療保険制度改革協議会の案で、医師の技術料の個別評価を特定療養費制度の枠の拡大によって解決しようとしていることである。すなわち、技術料の分野にも自由診療と保険診療との混合評価を持ち込むことになり、医療費の際限のない拡大につながるもので、公的保険制度の基盤を危うくすることになる。
制度企画部会の協議結果が、国民医療に重大な影響をもたらす医療保険制度の抜本改革にむすびつくことを考慮すると、私は医療担当者として、また、委員のひとりとして、もっと慎重でなければならないと思う。まだ意見の集約もできない状態で法案を提出するのは、明らかに時期尚早である。審議に十分な時間をかけ、国民が納得できるような結論を導き出すのが、われわれ委員の責務と感じている。
日医としては、これからも医療を受ける国民の側に立って、できるかぎりの努力を続けていきたい。