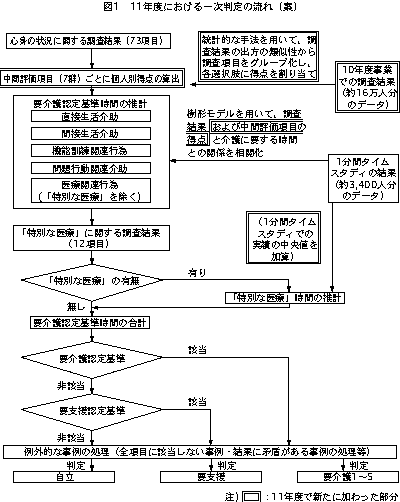
日医ニュース 第906号(平成11年6月5日)
|
|
|
一時判定について |
「介護保険制度の概要」シリーズの12回目は,平成10年度モデル事業の調査結果を 踏まえて変更される要介護認定の一次判定方法について解説する.次回は二次判定について触れる.
1.一次判定における要介護認定基準
要介護認定基準時間等を定めた厚生省令は,医療保険福祉審議会老人保健福祉部会の審議(諮問・答申)を経て本年4月30日公布された(表1).「要介護1」は30分以上50分未満,以後,20分きざみで判定される.
| 直接生活介助 | 身体に直接触れて行う入浴,排せつ,食事などの介護等 |
| 間接生活介助 | 衣服等の洗濯,日用品の整理等の日常生活上の世話等 |
| 問題行動関連介助 | 徘徊,不潔行動等の行為に対する探索,後始末等の対応 |
| 機能訓練関連行為 | えん下訓練の実施,歩行訓練の補助等の身体機能の訓練およびその補助 |
| 医療関連行為 | 呼吸管理,じょくそう処置の実施等の診療の補助等 |
| 要支援 | 5分野を合計した要介護認定等基準時間が30分未満であって ・要介護認定基準等時間が25分以上 または ・間接生活介助,機能訓練関連行為の2分野の要介護認定等基準時 間の合計が10分以上 |
| 要介護1 | 5分野を合計した要介護認定等基準時間が 30分以上50分未満 |
| 要介護2 | 5分野を合計した要介護認定等基準時間が 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 5分野を合計した要介護認定等基準時間が 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 5分野を合計した要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 5分野を合計した要介護認定等基準時間が 110分以上 |
2.一次判定の流れと判定方法の変更
本年度の一次判定の流れは図1のとおりである.
一次判定のコンピューターシステムは「樹形モデル」と呼ばれ,訪問調査の項目ごとに選択肢を設け,調査結果に伴って高齢者を分類してゆき,「1分間タイムスタディ・データ」に基づき,心身の状態に最も近い高齢者のデータを探し出して,認定基準時間を推計するシステムである(図2).
前年度のモデル事業で判明した問題を改善するための主な変更点は次のとおりである.
1. 中間評価項目の導入
樹形図(モデル)の特性として,分岐点に現れない心身の状態を示す73項目の調査結果は,基準時間の推計に勘案されないので,「中間評価項目」の導入によって調査結果を必ず推計値に影響させる.
中間評価項目とは,73項目についてモデル事業対象者約16万人のデータを用い,同様な傾向(例:項目aで「全介助」のとき,項目bでも高い頻度で同時に「全介助」となる場合は,この2項目を同一グループとする)をもつ項目ごとに,「第1群(麻痺・拘縮に関連する項目)」「第2群(移動等に関する項目)」等の7グループに分類するもの.
2. 「直接生活介助」の分割
介護に要する割合の大きい「直接生活介助」を「整容」「入浴」「排泄」「食事摂取」「移動」の5分野に分け,「間接生活介助」「問題行動関連介助」等と合わせ,計9つの樹形図を用いて基準時間を推計.
3. 「特別な医療」の加算
「特別な医療」12項目ごとに実際に提供されていた時間の中央値を加算.
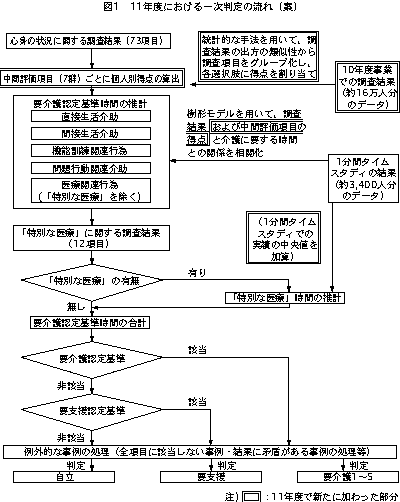
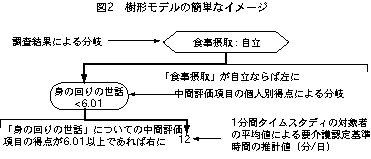
※「一分間タイムスタディ・データ」について
介護サービスの程度の必要性を判断するため,特養,老健等の3,403名の高齢者について48時間にわたり,どのような介護サービスがどれぐらいの時間行われたかを調査したもの.実際の介護時間を示すものではない.
(「要介護認定その1」は平成10年8月5日号,「その2」は9月5日号に掲載)
 日医ニュース目次へ
日医ニュース目次へ