「介護保険制度の概要」シリーズの13回目は,「二次判定の位置づけ」および「主治医意見書」について解説する.
前回,10年度モデル事業で判明した問題を改善するための一次判定方法の変更点について説明したが,これをもって問題点がすべて解決したわけでない.コンピュータによる一次判定方法は,その基礎となる「1分間タイムスタディ・データ」が,特養,老健等の施設入所者を対象としているなど,データに一定の限界があることが避けられない以上,介護認定審査会における二次(最終)判定の役割が重視される.
このため,介護認定審査会においては,一次判定を原案として,主治医意見書,訪問調査の特記事項,ならびに要介護度区分別の状態像を踏まえて,二次判定が行われることになる.
主治医意見書(意見書)は二次判定重視を受けて見直され(図1参照),これにより,意見書から大雑把な要介護度の絞り込みが可能となった.このように,意見書は,介護認定審査会に対してきわめて重要な要介護認定にかかわる情報を提供する役割をもつことになり,意見書の内容が不備なく記載されていることが重要となる.主な変更点は,次のとおりである.
(1)「心身の状態に関する意見」欄
・大まかな要介護度判定の目安となる「障害老人(寝たきり度)」および「痴呆性老人」の「日常生活自立度」判定の導入.
・毎日の日課についてどの程度判断できるかを問う認知能力,また,本人の要求や意思,緊急の問題等を表現したり伝えたりする能力を評価するなどの「理解および記憶」の追加.
・利き腕,体重,身長の追加.
(2)「介護に関する意見」欄
・「医学的管理の必要性」では,訪問診療,訪問看護などのチェック項目に短期入所療養介護や訪問栄養食事指導等を加えるとともに,「特に必要性の高いもの」に下線を引く.
(3)その他
・「傷病に関する意見」欄の「検査所見及びレントゲン所見」削除.
※意見書の詳しい説明は,「主治医意見書 記入マニュアル」(日医雑誌 付録, 平11.6.15)参照.
図1.主治医意見書(案)
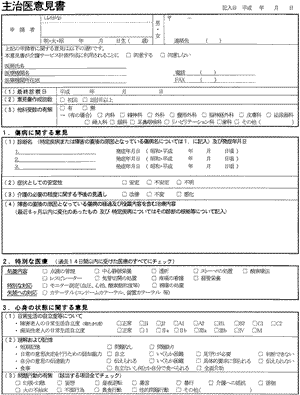 |
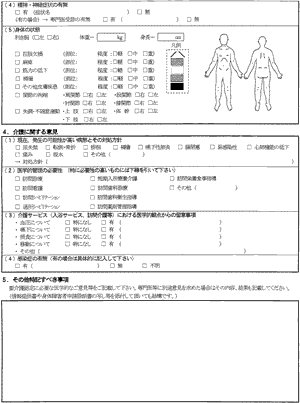 |
 日医ニュース目次へ
日医ニュース目次へ
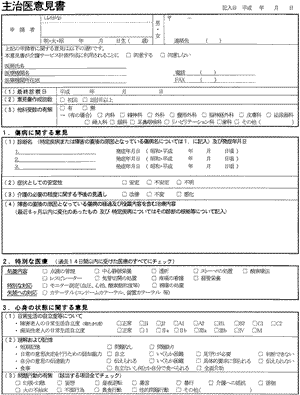
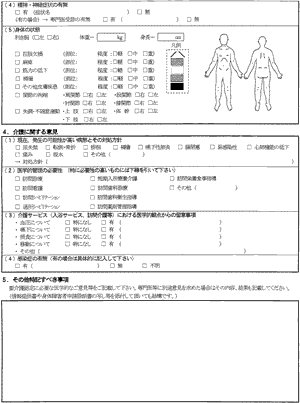
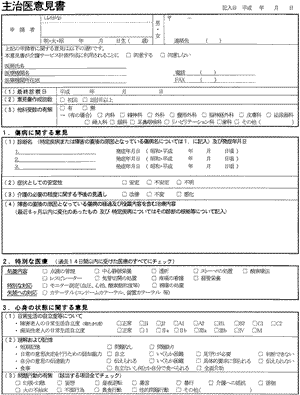
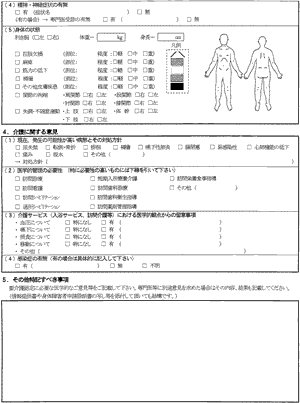
 日医ニュース目次へ
日医ニュース目次へ