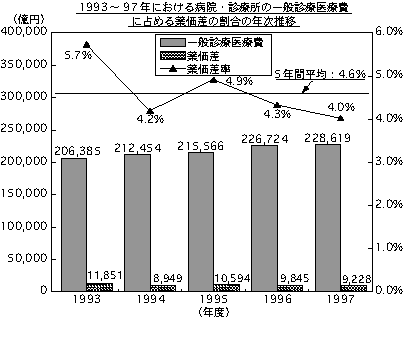 |
日医ニュース 第919号(平成11年12月20日)
|
社会保険診療報酬の引き上げ所要率を提示 |
| 日医は,十一月二十六日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)総会において診療報酬の引き上げを要望した.医科の引き上げ所要率は三・六%(物価人件費二・六%,技術革新一・〇%)となっている.また,同じく十二月一日の総会でも,「薬価制度抜本改革に関わる診療報酬改定要望について」を提出し,技術料適正評価分四・五%の補填を要望した.そこで,中医協の委員でもある菅谷忍常任理事に,要望の趣旨と引き上げ幅の算定根拠について聞いた. |
前回の平成十年四月のマイナス改定ならびに昨今の経済不況の影響を受けて,この二年間,医療機関は厳しい状況のなかで,経営を行ってきた.
特に,診療報酬だけに頼って経営基盤を維持しなくてはならない民間の医療機関は,新たな設備投資を控えたり,人件費を削減したりと支出を押さえることで,ようやくこの状況を乗り切ってきた.
この状況が続けば,医療の質を落とさざるを得ず,患者さんである国民にその影響が出かねない.そうなることを避け,すべての国民が安心して医療を受けられる体制を確保するためにも,来年四月の診療報酬の引き上げの実施は不可避であるということで,今回,中医協に要望を提出した.
| 診療費3.6%要望 |
| 薬価差解消分4.5%要望 |
| 社会保険診療報酬の引き上げ要望について |
| 平成十一年十一月二十六日 |
| 中央社会保険医療協議会 |
| 会長 工藤敦夫殿 |
| 中央社会保険医療協議会委員 |
| 糸氏英吉 |
| 菅谷 忍 |
| 櫻井秀也 |
| 横倉義武 |
| 木村佑介 |
|
注:診療報酬引き上げ所要率の欄の上段の数値は,病院,診療所,および平均における経費の構成比率を示す. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民により良い医療を提供するための診療報酬適正評価に関する要望事項 |
| 平成十一年十一月二十六日 |
| 中央社会保険医療協議会 |
| 会長 工藤敦夫殿 |
| 中央社会保険医療協議会委員 |
| 糸氏英吉 |
| 菅谷 忍 |
| 櫻井秀也 |
| 横倉義武 |
| 木村佑介 |
| 斎藤憲彬 |
| 光安一夫 |
| 漆畑 稔 |
〔医科〕
| I 基本的考え方 |
| II 具体的検討事項 |
二,医療機関機能の明確化および有機的連携の強化に対する診療報酬上の対応
三,地域医療の推進と積極的評価
四,医業経営基盤の安定確保等
五,その他
| 薬価制度抜本改革に関わる診療報酬改定要望について |
| 平成十一年十二月一日 |
| 中央社会保険医療協議会 |
| 会長 工藤敦夫殿 |
| 中央社会保険医療協議会委員 |
| 糸氏英吉 |
| 菅谷 忍 |
| 櫻井秀也 |
| 横倉義武 |
| 木村佑介 |
一,医療費と薬価差の関係をみれば,薬価差は経営原資として医療費に対して四〜五%程度の比重を占めており,もし薬価差をなくせば医療機関は決定的なダメージを受けることは必至である(別紙一).
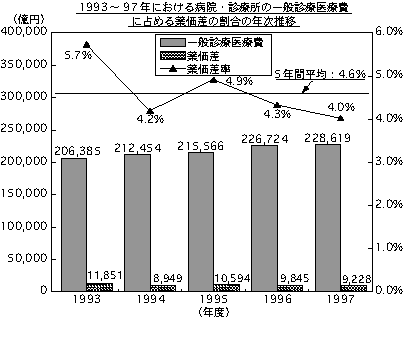 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二,現状では薬剤関連コストと支払われる診療報酬との間に,大きな格差が生じており,薬価差で補填しても,なお補填しきれない部分のあることは別紙二のとおりである.
|
以上により,薬価差解消に伴う補填分として平均四・五%の診療報酬の手当(技術料への転嫁)を強く要望する.
 日医ニュース目次へ
日医ニュース目次へ