 |
第1034号(平成16年10月5日) |
No.12
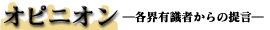
ある医師との会話:「薬販売の規制緩和」
三輪亮寿(弁護士・薬学博士)

「医学と法律の間で話が最近の規制緩和に及ぶと,薬や医療を巡る時代の襞目が見えてくる」と語る薬学博士の三輪亮寿氏.今回はその三輪氏に,薬販売の規制緩和について,30年来の友人である医師の質問に答える形で語ってもらった.
(なお,感想などは広報課までお寄せください)
 |
三輪亮寿(みわりょうじゅ)
弁護士・薬学博士,北里大学・東邦大学客員教授.昭和7年生まれ,東京大学薬学科卒.製薬企業勤務の後,弁護士を開業.専門は医事・薬事法学.著書に「後悔しない医療:インフォームドコンセント法律講座」(法研),「MRSA感染症と抗菌薬治療:訴訟問題も解説」(ミット)等がある. |
いわゆるドン・キホーテ問題とは
Q最近のドン・キホーテ騒動で,私の地区の薬局が大騒ぎをしているが…
Aそれは,危機感からの声だと思う.今,政府が強力に推進している「薬販売の規制緩和」で,既存の薬剤師が一般用医薬品販売の分野で不要になるかも知れないからだ.
Qどうして不要になるのか.
A例えば,規制緩和論者は「自分に合った薬は,自分が一番よく知っている」といい,だから,「一般用医薬品はコンビニでも売れるようにすべき」とか,「薬剤師が不在になる深夜や早朝の薬局・薬店でも売れるようにすべき」と主張している.騒動の元になったドン・キホーテという会社は,ディスカウント市場で成功した後,薬市場に参入してチェーン展開を始めた会社で,昨年の夏頃から,六本木のセンターに薬剤師を配置し,首都圏にある配下の薬局・薬店で薬剤師が不在になる深夜・早朝,TV電話で客に対応して薬を売り始めた.それに行政が待ったをかけたが,会社は応じない.正に前代未聞の事態だ.
ドン・キホーテ騒動は何が問題か
Q遠隔診療と似ているが,どうして騒動になったのか.遠隔診療はITの進歩で映像もシャープになり,離島・へき地の患者には福音だし,病診連携や医学教育にもプラスだ.
A遠隔診療は,患者の利益や医療の向上に貢献する.ところが,「薬販売の規制緩和」の出発点は経済の活性化だ.安全性重視の薬事法の精神からは,薬販売のあり方は薬剤師との対面・対話販売でなければならない.その考え方からすると,「ドン・キホーテ方式は疑問」という結論になる.
Qなるほど.「薬の規制緩和」は「医療の規制緩和」と同根・同類といえそうだ.医療も,株式会社による病院開設の容認とか,混合診療の解禁などと騒々しい.だから,薬の話も医師にとっては他人事ではない.
A厚生労働省は,急遽,七人からなる「深夜・早朝における医薬品の供給確保のあり方等に関する有識者会議」なるものを設け,公開で検討を始めた.私もメンバーの一人だった.薬事法も,進化する社会の実態に合わない部分が生じてきているので,一見して疑問な事態も無下に「違法」と決めつけるわけにはいかない.その法と現実のギャップをうまく調和させ,実社会のなかに「軟着陸」させなければならない.
Q具体的には,どうするのか.
Aまず,規制緩和論者が主張する「利便性」,つまり「薬の入手しやすさ」の内容が,果たして,最優先されるべき消費者の利益であるかどうかを検証することだ.
Q最優先ではないと思う.発生率こそ低いが,市販の風邪薬や鎮痛剤で,SJS(スティーブンス・ジョンソン症候群)やTEN(ライエル症候群)などの重い薬害が出る.
A同感だ.薬の「利便性」は「安全性」が確保された上のものでなければならない.それこそが本当の意味の「利便性」だ.有識者会議でも,そのことを確認し合った.
ドン・キホーテ騒動の一応の結末
Qそれで,結末はどうなったのか.
A「コンビニ」の方は,昨年末,厚生労働省の作業部会が,一般小売店でも販売できる医薬品として,消化剤やうがい薬など,約三百五十品目を「安全上特に問題のないもの」として選定した.そして,医薬品から医薬部外品に移行させて一般小売店でも売れるようにした.この流れは今後も続くので,「進行形」のなかでの一応の結末ということになる.
Q「深夜・早朝」の方はどうなったか.
Aそちらも今年三月末,薬事法施行規則を改正し,安全性に配慮した条件を付けて,国はOKを出した.つまり,昨年の突然の大騒動から,わずか半年で,長年続いた薬局のあり方に一気に大きな風穴が開いたことになる.
Q国はどんな条件を付けたのか.
A今回の施行規則改正では,事前にパブリック・コメントを求めたが,一番関心が高かったのは,各店舗と異なる場所にあるセンターの薬剤師が対応できる地区の広さだった.正に「利便性」と「安全性」のせめぎ合いの問題だ.結局のところ,全国をカバーするのではなく,範囲を同一都道府県ないし隣接する都道府県に限ることとし,今回は辛うじて「軟着陸」させた.他にも,センターの薬剤師を,毎週一回は配下の店舗で薬事の業務に従事させる条件などがある.
Q既存の薬局の方は,どうなったのか.
Aこの騒動を契機に,輪番制などを普及させ,安全性を確保しつつ,深夜・早朝の消費者の利便性に応えることになるだろう.「安全性」が確保されれば,後は自由競争だ.
規制緩和の怒濤の流れ―これでいいのか
Q自由競争とはいっても,実質は薬局の既存勢力と新興のチェーン勢力の衝突だろう.恐らく医療の世界も,規制緩和によって新旧の間の勝負になっていくと思う.
A勝敗の鍵を握るのは,患者,消費者だ.問題は本当に安全性や質が確保されるかだ.
Q両者,「安全性」確保のスタート・ラインについたわけだが,既存の薬局でさえ,薬害を十分防止できていないことが心配だ.規制は,「緩和」だけで本当に良いのだろうか.
A規制緩和は消費者や企業の「自己責任」の成熟を前提とする.アメリカがいい例だ.しかし,現在の日本では,「時期尚早」の感がする.六本木ヒルズの回転ドアによる小児死亡事故で,国が早速に規制強化に乗り出したことがそれを象徴している.つまり,局面に応じた規制の緩和と強化の二極分化だ.
医師は,規制緩和の弊を許さず,かつ規制強化の試練に耐え,患者や消費者の生命健康を守るのが責務だということを認識してほしい.
|

