 |
第1044号(平成17年3月5日) |
NO.17
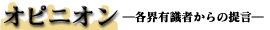
新しい持続可能なビジョンが必要
金子 勝(慶應義塾大学教授)

冷戦時代の終焉とともに,戦後の高度成長期の時代に作り出された「終身雇用」や「平等神話」もなくなってしまったと指摘する金子勝氏.氏に,このような時代の転換期のなかでの,医師会のあるべき姿を語ってもらった.
(なお,感想などは広報課までお寄せください)
 |
金子 勝(かねこ まさる)
慶應義塾大学経済学部教授.昭和27年生まれ.昭和50年東京大学経済学部卒業後,昭和55年東京大学大学院経済学研究科博士課程修了.その後,東京大学社会科学研究所助手,法政大学経済学部教授を経て,現在にいたる.専門は制度経済学,財政学,地方財政論. |
個人の人生だろうが社会全体であろうが,大きな転機を迎えると,その渦中にある人間は方向を見失ってしまう.時として,何が起きているかさえ分からなくなり,ずるずると失敗を繰り返して泥沼にはまってしまうことがある.バブル崩壊以降の日本もそうだと思う.
私は,よく,「辛口なことをいいますね」といわれる.しかし,この人は,「どうしちゃったんだろうか」と思わず見返してしまう.不良債権処理問題,ITバブル,ITバブル後の米国経済,そして,イラク戦争など,私は起きることをことごとく当ててきたからだ.もちろん,私は手品を使ったのではない.重要な出来事に直面する時,私は必ず日本の新聞やテレビを鵜呑みにせず,外国メディアの情報をチェックしている.記者クラブに依存して政府の「大本営発表」をたれ流している日本のメディアを信じないで,世界を見ながらしゃべっているだけなのだが,その食い違いがあまりにひどいので,「みんな目を覚ませ」という私の発言が「辛口」に見えてしまうらしい.
終わったのは「戦後」の仕組み
思い起こしてみよう.一九九〇年代初めに冷戦時代が終わって,これからは「市場万能主義」の時代になると,だれもが錯覚した.「例外なき規制緩和」が呪文のように繰り返され,それはやがて,「構造改革」と名前を変え,批判者に「抵抗勢力」というレッテルを貼ることで「正義」を獲得しようとしてきた.
だが,冷静に振り返れば,終わったのは「冷戦」だけではなく,「戦後」という枠組みであった.対外的には,国連安全保障理事会は,戦勝国による戦後処理体制という残滓を抱えていたが,イラク戦争を契機にして機能しなくなった.ブッシュが米大統領に再選され,米国の単独行動主義と,それに対抗して,「多極構造」を掲げる欧・中・ロという形で,ますます亀裂し始めている.宗教原理主義が浸透する米国は,むしろ世界では例外的存在であることが明らかになりつつある.
このように,国際状況の急速な変化にもかかわらず,日本の外交は冷戦時代そのままに,「ただ米国についてゆくしかない」というだけで,最初から,いろいろある外交的選択肢を放棄している.一種の思考停止状態だ.
例えば,多くの国が次々と撤退するなかで,自衛隊派遣を一年間延長してしまった.イラクがますます混乱してゆく状況で,一体どうする気なのだろうか.世界中(特にアジア諸国)で,日本は大義のないイラク戦争を支持している国だと見なされているうえに,首相は戦犯を合祀している靖国神社への参拝を続けている.ドイツのシュレーダー首相がナチス幹部の墓参りをしているようなものだ.
外交とは,正当性で競い合うものである.国際的に通用しないことをすれば,足下を見られ,叩かれてしまうのは当然だろう.それでもメディアは感情的な反中国キャンペーンに明け暮れ,国内では,相変わらず寝ぼけた憲法改正論議に夢中になっている.今や「国益」を第一義的に考え行動する保守派リアリストさえもが解体してしまったのだ.
市場原理主義が無責任を生む
一方,グローバリゼーションがもたらすバブルとバブル崩壊は,日本社会の無責任体制が抱える欠陥を露呈させてしまった.こうした閉塞感を打破するのが,規制緩和や民営化であるという冷戦時代の議論が繰り返されてきた.アメリカをモデルとして「構造改革」が声高に叫ばれたが,それは日本社会の無責任体制を助長させるだけに終わった.銀行も特殊法人も政府財政も社会保障制度も企業経営者も,みなズルズルの先送りを続けている.
「市場に任せろ」というスローガンは,責任追及を免れるための口実として使われてきた.しかも,この「構造改革」は,個人・企業・地域などで二極化(ひどい格差拡大)をもたらしている.
戦後,高度成長が作り出した「終身雇用」や「平等神話」は,もはや存在しない.ここでも,「戦後」は終わってしまった.
これから起こること
これから起こることを想像してみよう.二〇〇七〜八年に大きな転換点がやってくる.人口が減少し始め,団塊世代が退職し,過去発行した国債の償還期限が押し寄せてくる.しかも,団塊ジュニアと呼ばれる世代のフリーターは四百十七万人(二〇〇一年時点)に達している.まもなく団塊世代のサラリーマン約五百万人と同じ規模になるだろう.これまで働いて貯金をし,税金を納めていた団塊世代が一転して年金のもらい手になり,貯金をし,税金を納めるべき団塊ジュニア世代の多数派が不安定就業層なのだ.特にフリーターたちが,そのまま十年,二十年と経って社会の中核を占めるようになった将来を想像してみればいい.日本の社会が持つとは思えない.だが,年金制度も健康保険制度も介護保険制度もパッチワークのような「改革」を繰り返しているだけだ.人々は,ますます将来不安に陥っている.
医師会は,これまで自己利益を主張するだけの「利益団体」と見なされてきた.確かに,人口が増え,経済成長がある場合は,それでもよかったのであろう.しかし,これからは,そうはいかない.持続可能な制度改革のビジョンを自ら提起する能力が問われてくる.その際,狭い自己利害を超えて,何よりも高齢社会の到来に伴う人々の不安を解消することが優先されなければならない.時代の転換期には,だれもが生まれ変わらなければ生き残ってはいけない.また,尊敬を受けることもない.医師会も例外ではないと,私は思う.
|

