 |
第1054号(平成17年8月5日) |
NO.22
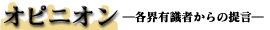
わが国の社会保障制度のあるべき姿
藤田伍一(一橋大学大学院教授)

社会保障制度改革の議論が活発化するなかで,藤田伍一一橋大学大学院教授に,わが国の社会保障制度の将来のあり方に関して,年金と医療に絞ってその問題点を整理してもらった.
(なお,感想などは広報課までお寄せください)
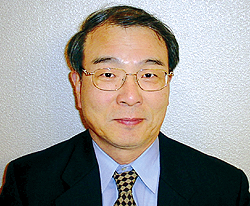 |
藤田伍一(ふじたごいち)
一橋大学大学院社会学研究科教授.社会政策,社会保障専攻.昭和17年生まれ.昭和48年一橋大学大学院博士課程単位取得.同大学社会学部助手,専任講師,助教授,教授を経て,現在に至る.この間にカリフォルニア大学客員研究員.藤田伍一・塩野谷祐一編「アメリカの社会保障」(東大出版会)等がある. |
はじめに
わが国における社会保障制度の改革は,焦眉の急となっている.しかも,二重の意味で改革を余儀なくされている.
一つは,これまでの成長本位の社会・経済構造がうまく機能しなくなったことである.すなわち,社会保障の前提となる社会・経済的枠組みが,市場のグローバル化や不況の長期化によって転換を余儀なくされつつあることである.
もう一つは,社会保障制度の内部的軋轢が限界に達したことである.わが国の社会保障は「世代間扶養」のシステムを採用しているが,急速な人口高齢化や長期不況によって,これがうまく機能しなくなってきたのである.例えば,年金においては「賦課方式」の欠点が露呈しており,医療においても「拠出金制度」による世代間扶養方式が行き詰まってきている.
ここでは,年金と医療に焦点を絞って問題点を整理し,わが国の社会保障制度の将来について考えてみたい.
年金の改革
わが国の公的年金は,昭和四十八年から「世代間扶養」の仕組みを導入したが,高齢化と低成長によって財政的な行き詰まりを示している.例えば,厚生年金では五年ごとの「財政再計算」時に拠出期間の延長や受給開始年齢の引き上げを行い,給付のカットなどを繰り返し行ってきたが,財政は依然として厳しい状況が続いている.
加えて,国民年金では,加入義務者のうち三分の一が未加入・滞納の状態にあり,いわゆる「空洞化」現象を引き起こしている.厚生年金でも滞納や脱退が相次いでいるが,年金の「空洞化」は,長期的不況による支払い能力の減退も一因であろうが,基本的には「世代間扶養」方式に対する反発があるためと考えられる.
すなわち,拠出者は自分の老後のためではなく,他人である老齢者のために拠出していることから,保険料納付意識が大きく低下している.「世代間扶養」のシステムに不満と不信をもつ若年者を中心に,未加入・滞納者が続出しているのである.したがって,年金改革は,拠出金の引き上げや年金額のスリム化ではなくて,拠出者に「自分の年金」であることを保障すること,その措置として,「拠出」に対する反対給付としての「年金権」を付与することに尽きるであろう.
医療の改革
医療保険については多くの構造的課題を抱えているが,それらの問題は結果的に医療費の増加という形で現れやすい.医療保険には医療費増加を促す構造的な要因が存在しているのである.
第一に,医療資源の三分の一以上が高齢者医療に投入されていることである.しかも人口の高齢化によって高齢者は年々増加し,ますます高齢者医療にウエートが置かれることになる.
第二に,医療技術の高度化によって医療生産性は増加するが,同時に開発コストやロイヤルティーも莫大なものとなっている.
第三に,診療報酬や薬価の決定である.本来,診療は「定性的」なものであるが,これを「定量化」して「診療価格」を決定している.その決定内容で医療費は大きく変動するのである.
現在,患者負担等を拡大することで,医療費の増大に一応ブレーキは掛かっているが,以上の三要因を内包することから,医療費は拡大路線に復帰しやすいことを銘記しておかなければならない.
わが国の医療保険が目指す「医療保障」の理念は,「診療機会の均等化」と「最適医療の確保」である.そのためには,診療の機能分化を促進し,時間的・空間的な「無医地区」を解消していかなければならない.特に第一次診療機能を強化し,かかりつけ医を普及させたり,健診システムの拡充等によって「予防機能」を重層化する必要がある.また,専門家である医師の養成・研修のあり方にも,いくつかの検討課題がある.
今,抱えている医療の重要課題としては,国民に等しく質の高い医療を提供していくための将来の処方箋を明らかにすることである.その場合,「混合診療の解禁」ではなく,いずれ医療保険を適用するとする「特定療養費制度の拡充」が柱となっていくであろう.
社会保障をめぐる条件
さらに,社会保障を改革するに当たっては,二つの社会・経済的条件をクリアしなければならない.
一つは,本格的な高齢時代を迎えて,社会コストが大幅に増大すること,もう一つは,わが国の経済活動水準はトレンドとして「ゼロ成長」となることである.
だが,わが国の経済活動は十分な高度に達しており,J・K・ガルブレイスが指摘するように,わが国でも「成長」より「分配」を優先すべき時代となる.社会保障をテコにして経済運営を図れば,水平飛行(ゼロ成長)型の省資源的・循環的な社会・経済構造を構築していくことは十分可能と考えられる.
厚生労働省によれば,現在,八十兆円台の社会保障給付費は,平成三十七年には二百七兆円(平成十二年度予算ベース)に膨らむと試算されている.しかも,この過程で,年金と比べて医療関係費が急増していくと考えられている.
したがって,リスクが安定している年金については年金数理による給付に変更し,リスクの不安定な医療・介護については国の社会保障資源を集中的に投入する等,メリハリのある分かりやすい政策を展開する必要があるように思われる.
|

