 |
第1056号(平成17年9月5日) |
NO.23
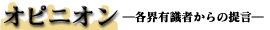
安心の医療へ
木村尚三郎(静岡文化芸術大学学長・東大名誉教授)

わが国の高齢化が着実に進行しているなかで,これからの高齢社会に必要とされる医療とはどのようなものなのか,木村尚三郎東大名誉教授に,1つの提案をしてもらった.
(なお,感想などは広報課までお寄せください)
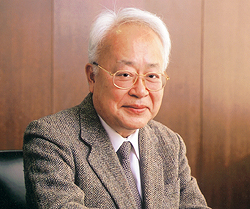 |
木村尚三郎(きむらしょうさぶろう)
静岡文化芸術大学学長,東大名誉教授.東大文学部西洋史学科卒.東大教養学部助教授・教授を経て,現在に至る.専攻は,ヨーロッパ史,現代文明論.主な著書に「歴史の発見」(中央公論社),「成熟の時代」(日本経済新聞社)などがある. |
「先生,足の裏を押すと痛いんですけど」
「じゃ,押さないでおきなさい」
思わず,アハハと笑ってしまう.ある高名な落語家の傑作である.しかしここには,単なる笑い話以上の,これからの高齢社会を生きる大切な知恵が含まれていると思う.
お年寄りは,心配症である.「死」が,年とともに現実感を帯びて近づいてくる.いやでも,このことを意識せざるを得ない.したがって,これまで経験したことのない異常が身体のどこかに現れれば,死に至る病ではないかとおびえる.病を探し回る日々が,やがて,本当の病を招いてしまう.
「病は気から」というのは,本当だと思う.大都市の市長としてバリバリ活躍されていた方が,次の選挙でまさかの落選となり,直後に亡くなられた.まだ記憶に新しい,痛ましい出来事である.選挙民が市長を無能と判断したからではなく,多選を避けたいとの一事から,新しい風を求めたに過ぎないと思われる.しかし本人にしてみれば,まさに予想外の出来事であり,文字通りのショック死であった.
「風邪を引きましたので」との口実でズル休みをすると,本当に風邪を引いてしまうともいわれる.まさに「嘘から出たまこと」で,心の嘘を身体がまことにしてくれるのである.私も今年七十五歳となり,後期高齢者の仲間入りをしたが,一応無事に生きていられるのは,幸か不幸か仕事に追われ通しで,身体のさまざまな変調を気にする暇がないからだと思っている.
名医のカン働き
冒頭に述べた足の裏を押す,病気を探し回る心のゆとりがない.クリニックがくれる六種類の薬を,いささか不遜(ふそん)な態度ながら,自分のためというよりお医者さんのためと思って,ポイポイ口に放り込んでいる.血圧,血糖値を下げる薬,心臓の薬,血液をサラサラにする薬など,多彩である.人間ドックには一度も入ったことがない.検査をすれば必ずポリープの一つや二つ,あるいはそれ以上が見つかるだろう.それだけで,気が滅入る.気が滅入れば,病を引き起こす.
戦時中の中学生時代,東京にいた.学童疎開組の,直前世代である.焼夷弾がグワーッと,いいようのない落下音とともに,束になって降ってくる.家屋を燃やす弾であるが,直撃をくらえばもちろん死ぬ.グラマン戦闘機から発する,野太く鈍い音の,機銃掃射も浴びた.いずれも,逃げようがない.ひたすらじっとして,死を待つのみである.そのときから,人間どうあがいても,死ぬときは死ぬという人生観ができあがった.
高齢化率の高い,いざというときお医者さんもいないへき地では,お年寄りが押しなべて元気である.若い者がいないのだから,何でも自分でするより外はなく,お年寄りがさらにお年寄りの面倒を見る.病気になったら大変だから,真剣に自分の身体の健康維持に努める.多少の身体の不調は,自力で直す.
高齢社会の進展とともに老人医療費は膨らむ一方であり,ただでさえ景気低迷の国民全体の「暮らしといのち」を圧迫していく.何とかしてこの老人医療費を抑え込まねばならず,また多忙をきわめる医師の,手間隙をも省かねばならない.病院は,お年寄りで溢れ返っている.
このようなとき,「先生,足の裏を押すと痛いんですけど」と患者さんにいわれ,「じゃ,押さないでおきなさい」といえるお医者さんは,名医だと思う.ふつうは,機器による検査から始まって,病気の先回りをして対処しようとする.名医には,このまま放置しておいても,どっちみち大事には至らず,いずれ本人も気づかぬうちに治ってしまうだろうといった,カン働きがある.
このようなカン働きは,アメリカの経営者の間でも,重視され出しているという.アブダクションといい,推論とか暗黙知を意味している.
つまり,数値化しうる明白な結論を導き出そうとするのではなく,多分,こういうことだろうという,暗黙的な仮説を立てることである.間違った考え,見通しを引き出す結果となることも,ないではない.
しかし,人間の身体とか経済のように,相手が教科書通りにはいかない生き物の場合,大局的なカン働き,ないし,アブダクションは不可欠であると思う.
高齢社会に必要なもの
カン働きで,「足の裏を押さないでおきなさい」とお医者さんにいってもらえれば,「どこか悪いのではないか」と日々不安のうちに暮らすお年寄りには,「安心」が与えられる.「安心」が得られれば,元気になる.元気になれば,近くのお寺参り,神社詣でからはじまって,「元気なうちに」と一念発起,四国八十八カ所巡りにも自分の足で挑戦する.手足が活発に動き,山々の緑との対話や,触れ合った人々との交歓は,当人の気力,体力を増し,それによって,いよいよ病気知らずの元気になる.
「人事を尽くして天命を待つ」とばかり,現代のお医者さんは検査に次ぐ検査,処置に次ぐ処置,治療に次ぐ治療によって,患者さんに対して真摯に対応しようとする.しかし患者さんは,故障自動車とは違う.不安で一杯の「心」を持った存在である.
カン働きによって,患者さんやお年寄りに「安心」を与え,病気の回復を早める.ないしは,病気を出さないようにする.これも,これからの医療の大切な役割であると思う.
それによって,何よりも,まず患者さんやお年寄りに幸せ,元気が与えられる.そして,医療費が削減され,医師の負担も,軽減される.
経験とカンによってお年寄りに「安心」を与え,受け身になりがちのお年寄りに,能動的な,自ら生きる力をふるい立たせる.自力で生き,自力で治す心と知恵を授ける.そのような「安心の医療」が,これからの高齢社会には何よりもほしい.
|

