 |
第1089号(平成19年1月20日) |
新春対談
唐澤 人会長 vs 岸本忠三第27回日本医学会総会会頭 人会長 vs 岸本忠三第27回日本医学会総会会頭
〈知識〉と〈知恵〉で,“生存”の意味を問い直そう

今年四月,第二十七回日本医学会総会が,大阪では二十四年ぶりに開催される.そこで,今回は,総会の会頭であり,インターロイキン-6を発見するなど,免疫学の世界的権威としても知られる岸本忠三氏と唐澤 人会長が,日本医学会総会や医療,日医の今後などについて大いに語り合った. 人会長が,日本医学会総会や医療,日医の今後などについて大いに語り合った.
 唐澤 今年は,いよいよ日本医学会総会を大阪で開催されるわけですが,すばらしい総会になるよう,期待しております.先生は,ご幼少のころから大阪でいらっしゃいますか. 唐澤 今年は,いよいよ日本医学会総会を大阪で開催されるわけですが,すばらしい総会になるよう,期待しております.先生は,ご幼少のころから大阪でいらっしゃいますか.
岸本 大阪の富田林市です.
唐澤 お正月の思い出は,どんなものですか.
岸本 田舎ですから,暮れになると餅つきや大掃除,母たちは大みそかの遅くまでお節料理を作っておりました.大きな家で寒いので,みんなでこたつに入ってみかんを食べながら紅白歌合戦を見るのが恒例でした.
最近は,料理屋などが作ったお節が売られ,ホテルで過ごす人も増えていますね.家族が一緒にこたつに入ってだんらんすることが非常に少なくなったように思います.
その延長線上で医療を見ますと,われわれが子どものころは,赤ん坊は家で生まれ,祖父母は家で亡くなりました.つまり身近な生死を見てみんな育っているわけですが,このごろはめったにない.子どものころから生命を近くに感ずることがなくなってきたと思うのです.また,僕が育ったのは,田舎の村でしたが,代々診てもらっているお医者さん─“かかりつけ医”がいました.それが少なくなりましたね.
唐澤 確かに今は,人生の最大行事と言える出産も看取りも,ほとんど病院などですね.昔は,いろいろなものが家庭を中心にしてあったように思うのですが…….
岸本 お正月に限らず,親子や家族の間の話し合いが消え,家族の連携が失われ,社会が変わって,それが教育や医療にも影響を及ぼしてきていると思います.
唐澤 先生は大阪大学のご出身ですが,ご家族にお医者さんが…….
岸本 いえ,父は校長でした.今だったら大変だなと思いますけれども…….(笑)
僕は,野口英世の伝記などを読んで医師になりたいと思いましたし,親が「医者になれ」と言ったのも,当時は医師が最も尊敬される職業だったからです.『日本経済新聞』の「私の履歴書」(平成十二年九月四日朝刊)にも書きましたが,息子を何とか医師にしたいというのが父の夢でした.しかし,僕は医師より,野口英世や湯川秀樹博士のような研究者になりたいという思いがあって,紆余曲折の末,医学部へ行ったのです.
先生のところは,代々お医者さんですか.
唐澤 いえ,母方の伯父が医師だっただけです.父は僧侶で,厳しい修行のことしか話しませんでしたから,僧侶も嫌だなと思ったのです.結局,母や伯父の影響が大きかったかなと思っています.
先生は医師になられてから,臨床の方には進まれなかった…….
岸本 僕は,研究者になろうと思って医学部へ行ったのですが,五年生の時に,生化学の山村雄一先生が九州大学から来られました.その講義を聞いて,「ああ,この人の話はよく分かるな,おもしろいな」と思って山村先生の所へ入り込んだ.そこが第三内科だったので,最初内科からスタートしたのですが,途中から研究者になり,また内科の教授に戻って,最後は管理職と,何をしているのか分からなくなりましたけれども…….(笑)研究も臨床も,いろいろなことを経験させてもらいました.
「生命と医療の原点―いのち・ひと・夢―」が総会のメインテーマ
唐澤 先生は臨床分野にもご造詣が深くて,先日も,「最近は遺伝子の解明が進み,新しい方向として,テーラーメイド医療までもが現実となっているが,その進歩は基礎的な研究に支えられている」というお話を伺いました.今後も医療は進歩すると思われますが,今度の医学会総会は,医療をもう一度見直し,原点に帰ろうという,大変斬新なテーマを掲げておられますね.普段からお感じになっていることがあったのでしょうか.
岸本 「生命と医療の原点―いのち・ひと・夢―」というのがメインテーマです.
唐澤 私は,あの副題が大変気に入っているのです.
岸本 基礎医学,臨床医学,そして未来の医学を表しています.医学会総会は普通の学会とは違うわけです.そこで,初日は,第一線で医療に携わっておられる先生方に,最先端の研究,医学・医療の進歩と,それが臨床にどのように応用されてきつつあるかを理解してもらうための基礎的なことを考えました.
二日目は,それらに基盤を置いて,テーラーメイド医療,生活習慣病,画像診断などの進歩,脳科学の進歩による認知症治療薬,あるいは基礎的研究の進歩によるがん医療などについて議論してもらう.同時に,研究者の方には,自分のやっている研究がどう役立ってきているかを周辺まで幅広く知ってもらうことで,さらに深く研究を進めていくうえでプラスにしていただきたい.
そういう意味では,異分野の人が集まって討論することに,今回の総会の意義があると思います.あまりにも最先端の難しいシンポジウムばかりが並んでいたら,どこへ行っていいのか分からないですよね.そこで,ある程度集中して絞る─言わば“small but excellent”という学会です.
唐澤 医学会総会は四年に一度ですので,その四年の間にも相当変化がありますね.
岸本 僕はいつも言うのですが,もう少し長い目で見ますと,医学は論文の上に論文が積み重なって発展していくわけで,百年前の医学は古いものになる.ところが,人間の“知恵”というのはそれほど進むものではない.ですから,二百五十年前のモーツァルトが今でも通用し,それを越えるものは今もない.
つまり,“知識”と“知恵”とは,その進歩の度合いがまったく違うわけです.
今,医療の面でも,いろいろな問題が起きています.たとえば,おばあさんが孫を産むとか,死んだ男性の精子を用いて子どもが生まれてくるとか.科学技術は急速に進むのに,人間の知恵はそうは進んでいかない.そのために,きしみが生じているわけで,それらも,もう一度考え直し,知恵をつけようというプログラムを,ある程度イメージしているつもりなのですが.
唐澤 昨年暮れに,ベルツ賞の表彰式に参列しました.一九〇四年,ベルツ先生が日本を去るに当たり,「医学教育を通じて,日本人は実に優秀だと感じた.日本の医学は間違いなくすばらしいものになるが,一つだけ気になることがある」と,「あまりに集中して医学に注力し過ぎるから,発展させる“精神”の部分を見直し,涵養しておかなくてはいけませんよ」と言い残されたそうです.当時,ベルツ先生は日本人のそういう部分を見抜かれていたのかなと思いましてね.
「いのち,ひと,夢」というテーマ,私は,そこに,“心”と“愛”という二つを入れて欲しいなと思ったのですが,その“心”をもう一度問い直されたような気がします.何のために科学や医学が進歩していくのか,原点に戻って問い直そうというのですね.
岸本 ええ,さらに,医療の恩恵を受ける側である一般の人にも,医学・医療はここまで進歩している,これほど役立っている,こういう点が問題だということを理解してもらいたいと思います.
一般公開の企画展示では,テーマ館である大阪城ホールと近隣地区において,「いのち」の誕生から,最先端の手術室や画像診断,薬,大阪府医師会が行っている日本と世界の医療の比較など,医学のみならず医療問題に至るまで,会場を回れば全部分かるような「回遊式」の展示形式にし,特に力を入れました.
開催が,四月の桜が満開になるシーズンで,西の丸庭園から大阪城ホールを通りJRの駅までは大変な人出になりますが,一見の価値は十分ありますので,ぜひ見てもらえればと思います.
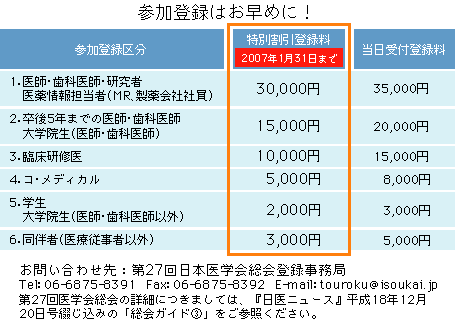
平仮名の「いのち」に込めた思い
唐澤 「いのち」は基礎医学,「ひと」は臨床医学,「夢」は未来医療ということで,非常に分かりやすい副題ですね.
岸本 単なる科学の問題だけではなく,なるべく知識と知恵を一緒にして「いのち」を考えようとの思いから,漢字の「命」ではなく,平仮名にしてあるのです.
唐澤 基礎医学でも,ナノレベルでの解明とか,遺伝子レベルの解明など,最先端の研究では,あらゆる分野が総合的に協力し合わないと新しい発展につながりませんね.
岸本 医学と工学との連携が盛んになって,例えば,眼科の眼底三次元画像解析など,画像診断も分子イメージングが進んでいますね.
唐澤 角膜移植でも,幹細胞を利用して異物反応のない角膜が再生できるそうで,再生医療などの分野は臨床医学と直結していますから,一つのつながりの形で論じられますね.
岸本 世間の見方も変わってくるでしょうね.
唐澤 未来の医療について,どのようにお考えですか.例えば,悪性腫瘍とか,臓器移植,最近は,アンチエイジングなどという話題もありますが…….
岸本 寿命については,胎生期の長さによってプログラムが大体決まっています.“十月十日”で生まれる生物種である人間の寿命は,九十年から百年です.それをずっと元気に過ごして,パッと消えるというのが一番幸せな生き方ですよね.
例えば,認知症になる,ならないといった脳の仕組みや記憶の仕組みも,次第に解明されて認知症にならないで済むようになり,さらに身体的な不自由さは,補助具や,ロボット,サイボーグなどをうまく使えば,相当なくなると思います.
そうなれば,高齢になっても階段を登り,外を歩くことは達成可能だと思うのですが,やはり,“十月十日”で生まれる生物種としては,不老長寿という昔からの願いはかなわない.DNAを変えて違った生物種に変わっていったら分かりませんが…….(笑)
唐澤 最近,終末期医療とか看取り医療が大きな話題になっていますが,生まれれば死ぬわけですから,それをどのように迎えるかが重要だと思いますね.例えば,長生きであれば,がんも一生に二回くらいは出るという話を聞きますが,それもさまざまな手段でうまく乗り越えて…….
岸本 がん治療は相当進むでしょう.すでに,分子標的治療薬─がん細胞の血管新生を阻害するとか,がんに対して特異的に作用する抗体医薬が次々と開発されてきています.ただし,医療費は非常に高くなりますが…….
唐澤 例の非小細胞肺がんの治療薬(ゲフィチニブ)の話などもありましたね.
岸本 折り合いの問題ですが,みんな幸せに天寿を全うできれば一番いいですよね.
唐澤 家族に囲まれながら,というところでしょうか.
ところで,医学会総会は,若い先生方に,ぜひご参加いただきたいですね.“卒前教育”“新医師臨床研修”“いわゆる後期研修”などのキーワードが焦点になっていますが.
岸本 医学会総会も,若い医師や医学生に足を運んでもらうきっかけになるように,大阪ドームで,臨床研修病院と学生とのマッチングを行ってもらうことを考えています.
さらに,四月八日の特別シンポジウム「今日の医学教育,医療制度の問題点とその改革─医学,医療制度の理想像へ向けた提言(仮題)─」では,研修医の代表にもシンポジストとして入ってもらい,研修医が置かれている現状と問題点,さらに今後を考えてもらおうと思っています.参加してもらえれば,自分がどういう道へ進もうかと考える際の参考になると思うのです.
大阪開催としては前々回になる第十六回総会は,僕が卒業する前年の昭和三十八年で,当時の阪大第五代総長の今村荒男先生が会頭だったのですが,そのころはすべて手作りです.われわれも手伝いに駆り出され参加しましたが,「自分もいつかはこういうことをやろう」「こういう所で発表できるようになろう」という思いはありました.ですから,医学会総会に参加することは非常に有意義ではないかと思います.
唐澤 私どもが医師になったころは,試験管洗いなどもやりましたからね.(笑)
私は,昨年四月から日医を預かるようになりましたが,最近印象深く思うのは長く会長を務められた武見太郎先生で,「生存科学」ということをよくおっしゃっています.
それは,先ほどの先生のお話のように,「自然が決めた年齢まで元気で生きる.そして体が弱ってくる.しかし心は豊かで,知恵も豊かである.そういう人生を送りたい」ということで,その根底にあるのが「生存の理法」だと書いていらっしゃるのです.その「生存の理法」の“生存”とは何かが分からなかったのですが,実は,大阪開催としては前回,第二十一回総会(昭和五十八年)の記録を見ましたら,武見先生を座長に,この「生存の理法」というテーマの開会講演を,故大江精三日本大学文学部教授がされているのです.この時のメインテーマは,先生はご存じと思いますが,「医─科学と人間」なのですね.今回の総会と根底的には非常に近い主題で開催されていたので,意義深い感じがします.私は,今回も何か新しいもの─恐らく,後世に残るメッセージがたくさん出てくるのではないかと,本当に期待しているのです.
岸本 昨年十月に会長が出演されたNHKの番組「日本の,これから〜医療 安心できますか〜」では,視聴者から生アンケートを取っていましたね.今回の特別シンポジウムでは,直前に,多くの人からアンケートを取り,その結果を基に,医学会,厚生労働省,医師会などが意見を交わし,今後のあるべき医学教育,医師の育て方,医療,社会福祉等の問題を話し合っていただく予定です.そこでの三時間で結論が出るわけではありませんが,今後も続けて考えていただく出発点になればよいと思います.
医療は“人”,そして“投資”
岸本 忠三(きしもと ただみつ)
第27回日本医学会総会会頭,大阪大学前総長,同大学院生命機能研究科教授,日本医学会副会長.昭和39年大阪大学医学部卒業,昭和44年同大学院医学研究科修了.日本学士院会員,平成10年文化勲章受章. |
 |
唐澤 少子高齢化の時代になり,日本の将来像が見えにくいのですが,生活を守るための社会保障制度,なかでも最も身近な医療については,国民皆保険制度が壊されないようにしたい.ただ,心配なのが医療財源です.“モノ・ヒト・カネ”と言われますが,医療を支えるさまざまな専門分野の人が活動するには,ある程度そろっていないと支えられませんね.
岸本 効率化と言っても,削れる限度がありますよね.
医療は,大量生産で機械で作るものではなく,人の手で行い,人がかかわるものですから…….
唐澤 “人”対“人”ですね.
岸本 医療は人がかかわるので,非常にお金がかかるわけです.今,社会保障費を減らしていいのかという議論がありますが,それを受ける側である国民がどう考えるかが,一番大きな問題です.その議論が大きなうねりになることが必要だと思いますが…….
唐澤 もちろん,科学の進歩が補完してくれますから,治療・手術・検査など,効率的で安全な医療になっていくと思いますが,やはり顔を合わせて語り,慰め,支えるという医療の根本的な部分は,“人”が手を加えなければならない.その辺りを国民の皆さんにも考えていただきたいですね.確かに,少ない現役世代で多くの高齢者を支えることになりますから,効率化の問題も大事かとは思いますが.
岸本 医療や科学が進歩して,みんなが,七十,八十歳になっても元気でいられるようになれば,その人たちが働けるようになる.必要なところにお金をかければ,それがこちらへ返ってきます.医療は,決して“消費”ではなく,“投資”なのだという考え方ですよね.そういう問題も,ぜひ,特別シンポジウムで議論し,その流れを,日本医学会と日医とでつないで,発展させていければいいと思うのですけれども.
日医が取り組むべきこと─組織強化と情報発信
 唐澤 日医としましても,少子高齢社会,医療保険制度など喫緊の課題に加え,新型インフルエンザやテロ,大災害といったさまざまな局面で,国民の健康に影響する大きな問題については,積極的に取り組んでいこうと思っています. 唐澤 日医としましても,少子高齢社会,医療保険制度など喫緊の課題に加え,新型インフルエンザやテロ,大災害といったさまざまな局面で,国民の健康に影響する大きな問題については,積極的に取り組んでいこうと思っています.
また,医師はおよそ二十七万人で,日医会員は十六万人余りですから,できるだけ多くの先生方に入会していただきたいと思います.先生から日医に対するご意見が,何かありますでしょうか.
岸本 僕は,平成十七年に,「中医協の在り方に関する有識者会議」に委員として出ていましたが,中医協でも,同じ診療側でありながら,開業医と病院勤務医は立場がまったく別のような感じを受けました.
日医は,日本の医師全体の代表であるべきで,開業医も勤務医も,医師全員が参加してこそ,国あるいは国民に向かって,良い医療を行うための提言ができるのではないでしょうか.一つにならないと,外へ向かっても大きなインパクトにならないと思います.
唐澤 それぞれの立場が明確になるような医療提供体制ですので…….もちろん開業医も,専門医や勤務医も,大きな接点があるはずなのですから,先生の言われるとおり,日医が提言していくべきなのでしょうね.
岸本 共通の目標をみんなで確認していただけたらいいですね.
唐澤 医療を受けるのは国民ですからね.医師のために医療があるわけではない.
岸本 そういう点を国民に向かって発信していくことが大事だと思います.
唐澤 それと,若い先生方が,「医師会とは何か,入会するとメリットがあるのか」とおっしゃる…….
岸本 若い先生方はメリットということを言いますね.しかし,日医が国民に向かって発信し,国民が「そうだな」と思うという,全体のうねりをつくっていくことが大事です.そうでないと,「社会保障費は削れば削るほどいい」といったことになりかねません.結局,国民に被害が及ぶのだということを,医師全体がまとまった一つの組織として日医が知らせなければならないのです.組織率と情報の発信が重要だと考えます.
唐澤 情報を提供するとともに,ご意見を真摯に拝聴するという姿勢も大事だと考えています.それから,日医は学術専門団体ですから,医学・医術は中心的課題として大切にしなくてはいけないと思っています.
岸本 開業医と勤務医が混然一体で,決して利害が対立するものではないのと同じように,日医と日本医学会も混然一体となって協力し合っていかなければいけませんね.
唐澤 そういう意味では,日医も日本医学会も,非常に大きな可能性を秘めていると言えるかも知れませんね.本日は,有意義なお話を,ありがとうございました.
岸本 ありがとうございました.
|

