 |
第1250号(平成25年10月5日) |
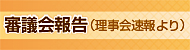

今号より,日医の活動を会員の先生方に広く知ってもらうため,日医常勤役員が出席している主な外部審議会の概要を,掲載していくこととなった.
今回は,九月三〜十二日までに開催された外部審議会の模様を紹介する.
官民連携による自殺対策の推進を目指して
─内閣府 第1回自殺対策官民連携協働会議─(報告・三上常任理事)
内閣府第一回自殺対策官民連携協働会議が九月三日,都内で開催された.
本会議は,自殺総合対策大綱(平成二十四年八月二十八日閣議決定)に基づき,国,地方公共団体,関係団体,民間団体等が連携・協働し,国を挙げて自殺対策を推進することを目的としている.
当日は,「自殺総合対策大綱における施策の実施状況」として,(一)自殺の実態を明らかにする,(二)国民一人ひとりの気づきと見守りを促す,(三)早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する,(四)心の健康づくりを進める,(五)適切な精神科医療を受けられるようにする,(六)社会的な取組で自殺を防ぐ,(七)自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ,(八)遺された人への支援を充実する,(九)民間団体との連携を強化する─取組といった各省庁の取り組みの実施状況が提示された.
その他,「警察庁の自殺統計に基づく自殺者数の推移等」と「平成二十五年度自殺予防週間」について内閣府よりの説明があった後,意見交換を行った.
報告制度案,日医・四病協の合同提言内容が大幅に盛り込まれる
─第8回病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会─(報告・三上常任理事)
第八回病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会が九月四日,都内で開催された.
議事は,(一)社会保障制度改革国民会議報告書及び「法制上の措置」の骨子について(報告),(二)病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方(案),(三)その他─であった.
当日,参考資料として,日医・四病院団体協議会合同提言「医療提供体制のあり方」を提出していたが,(二)で示された案には,合同提言の内容が大幅に取り入れられ,「医療機関が報告する医療機能の名称及び内容」もかなり変更された.また,医療機能の名称のうち,「長期療養機能」について,病期を表すものではないとして,「慢性期」とするよう提案したところ,他の委員からも賛同する意見が相次ぎ,「慢性期機能」に変更することが了承された.
入院時の食事療養等について議論
─第7回小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会─(報告・石川常任理事)
第七回小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会が九月九日,厚生労働省で開催された.
議事は,(一)小児慢性特定疾患対策の検討状況,(二)公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築に係る検討─であった.
(一)では,これまでの議論を踏まえた「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(中間報告)(概要)」が示された他,(二)では,「慢性疾患児地域支援事業(仮称)」などに関する平成二十六年度予算概算要求や「他制度との比較」「小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担限度額」等についての説明があった.
現在,「自己負担なし」である「入院時の食事療養」を今後どうするかという議論の中では,生活者の立場から,「子育て支援というものを十分にやるのであれば『自己負担なし』でやるべきである」と主張した.
高額療養費の見直しの方向性示される
─第67回社会保障審議会医療保険部会─(報告・鈴木常任理事)
第六十七回社会保障審議会医療保険部会が九月九日,都内で開催された.
議題は,(一)医療保険部会の今後の検討スケジュール,(二)高額療養費の見直し─についてであった.
(二)では,厚労省事務局より見直しの方向性が示され,七十歳未満については,上位所得者と一般所得者を細分化し,七十歳以上についても,一般所得者と現役並み所得者を細分化する見直し案のイメージが提示された.基本的には,上位所得者の限度額を引き上げ,一般所得者の中でも低所得者の方は引き下げる方向である.
「日本の自己負担割合三割というのは世界的に見ても非常に高いが,それでも公的給付が高く保たれているのは,高額療養費制度で自己負担額が抑えられているためである」とした上で,「高額療養費の見直しにおいては,所得の高い方により負担して頂き,低所得者の負担を抑えることは当然である.七十〜七十四歳の一部負担金の見直しを議論する場合においても,低所得者への配慮が必要であり,当然,高額療養費制度とセットで考える必要がある」と発言した.
平成25年度調査票案等を了承
─社会保障審議会介護給付費分科会(第96回)─(報告・高杉常任理事)
社会保障審議会介護給付費分科会(第九十六回)が九月十一日,都内で開催された.
当日は,「平成二十四年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成二十四年度調査)の結果(最終報告)」の説明を受けた後,「平成二十四年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成二十五年度調査)の調査票案等」について審議を行った.
平成二十五年度調査では,既に実施を了承した十一種類の調査で用いる調査票案の内容と,二種類の調査「集合住宅における小規模多機能型居宅介護の提供状況に関する調査研究事業」「地域包括ケアシステムにおける有床診療所に関する調査研究事業」を追加実施することについて審議を行い,どちらも了承した.
調査は,本年十月より開始され,調査結果に対する評価が行われた後,平成二十六年三月以降に分科会に提出され,次期介護報酬改定の資料となる予定.
12のワクチンについて,従来どおりの接種で合意
─平成25年度第3回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会,平成25年度第4回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)─(報告・道永常任理事)
平成二十五年度第三回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会,平成二十五年度第四回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議が九月十二日,都内で開催された.
議題は,(一)ジフテリア,破傷風,百日せき,麻しん,風しん,BCG,おたふくかぜ,水痘,A型肝炎,B型肝炎,ロタウイルス,肺炎球菌のワクチンの安全性等─についてであった.
各ワクチンの副反応報告数(平成二十五年四月一日〜六月三十日報告分)はこれまでと傾向に変化がなく,従来どおり接種することが合意された.
規制改革会議に対する揺るぎない対応を要請
─第32回社会保障審議会医療部会─(報告・中川・今村副会長)
第三十二回社会保障審議会医療部会が九月十三日,都内で開催された.
議事は,(一)社会保障制度改革推進法第四条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子(報告),(二)病床機能報告制度及び地域医療ビジョン,(三)在宅医療・介護連携の推進─についてであった.
議論の中で,中川俊男副会長は,規制改革会議が十二日に,看護師の業務範囲の拡大等を検討対象に選んだとの報道に触れ,厚労省事務局がどう捉えているのかを質した上で,「専門家が入っての議論とは思えない.厚労省としてゆるぎない姿勢で臨んで欲しい」と要望した.また,医療機関が報告する医療機能の名称及び内容として提示された四区分に関連して,厚労省事務局に対し,次期診療報酬改定の基本的な考え方において機能分化を急ぎ過ぎると整合性が保てなくなるのではないかと指摘した.
今村聡副会長は,(三)で,在宅医療連携拠点に関する事業の,今後の展開方針について質問した他,さまざまな在宅関連事業が実施されているが,住民は安心して医療・介護を受けられる体制が必要なのであり,出来るだけ事業をまとめ分かりやすくすること,高齢者だけでなく小児の在宅医療も一つの枠組みの中で実施出来るものを考えることを求めた.
|

