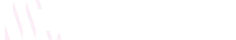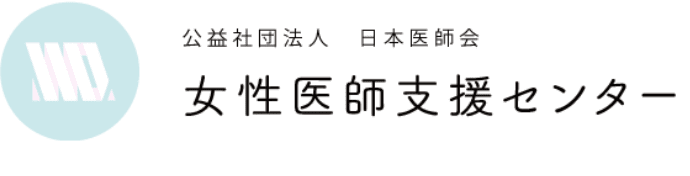- トップページ
- 働きやすい職場を探す
- 職場への復帰
職場への復帰
公開日:2021.09.14 / 最終更新日:2025.11.01- 自分に合った
- 持続可能な復帰の仕方を
- 考えましょう。

① 復帰後の働き方を勤務先とよく話し合いましょう
復帰後の働き方については、当直の有無なども含めて、どのような勤務形態にするかを勤務先としっかり話し合い、持続可能な復帰の仕方を考えることが大切です。これまでの章で紹介した制度なども、活用できるとよいでしょう。
復帰の仕方は人それぞれです。例えば、出産後早めに復帰し、スキルを保ったまま第一線で働く人もいれば、育児休業を長めにとってから復帰して、最初は短時間勤務制度等を利用しながら少しずつ仕事に取り組み、徐々に子どもが手を離れてきたらまた第一線で働くという人もいます。自分のキャリアプランとすり合わせながら、考えてみてください。
 Column
Column
ここまで見てきたように、育児をしながら働くうえで当直を免除してもらうこと自体は、公に認められている権利といえます。とはいえ当直免除について、忙しい同僚に対し後ろめたい思いを持つ医師も少なくありません。その背景には、医師の残業や当直への対価が十分に払われていないという問題がありますが、働き方改革が徐々に進み、この問題に対しても様々な形で解決が図られようとしています。
当直をできるだけ受けないようにしたいと考える人もいますが、少しでも受けた方が病院や同僚が助かるのは言うまでもありませんし、何より当直は医師として責任ある業務を経験できる貴重な場でもあります。その後のキャリアアップを考えると、できる範囲で取り組んでいくことが望ましいでしょう。一定期間の当直は免除とし、余裕が出てきたら土曜日の外来や休祭日の日直、休祭日の前日の当直などから取り組んでいくといったように、徐々に段階を踏んで復帰するという方法もあります。
② やむを得ず長いブランクが生じたときに利用できる制度
育児をしながら仕事を続けることは大変ですが、知識や技術の遅れを取らないために、少しずつでも働き続けることが理想です。ただし、周囲のリソース不足や子どもの病気など、やむを得ない事情でブランクができてしまうこともあるでしょうが、様々な支援を利用して少しずつステップを踏むことで、再び第一線に戻ることが可能です。
例えば日本医師会には“日本医師会ドクターバンク”があり、女性医師の就業先の紹介や、復職(再研修)の支援を無料で行っています。また、各都道府県の医師会にもドクターバンクや女性医師のための相談窓口があります。ぜひ活用しましょう。
【体験談】 子どもの疾患で4年間の離職後、安心して働ける職場に出会えました(内科、30代)
学生時代に結婚した私は、いずれ子どもができても働き続けたいと考えていました。ですが、研修4年目に妊娠し、子どもに心疾患があるとわかりました。子ども中心の生活をせざるを得なくなり、産後は4年ほど仕事から完全に離れ、その間に二人目の子どもも生まれました。
上の子が少し落ち着いて復職を考えた時に、一人で外来診療を行うのが不安だったので、そうでないことを第一条件に職場を探しました。
現在は週2回の外来と、もう一つ別の診療所で週1回の外来を行っています。どちらも午前だけなので、子どものお迎えにも無理なく行けています。就業時間も含め、様々な支援を得られる環境で働くことができて、医師としてのやりがいを感じています。
【体験談】 様々なご縁のおかげで、産後10年かけて常勤医に(皮膚科、40代)
私は地元の大学を卒業後、他県の大学に入局しました。夫は大学の同級生で、母校で働いていたので、しばらく週末婚を続けていました。大学院を修了した年に第1子を出産し、専門医資格も学位も取れたので、いったん仕事を全て辞め、地元に戻って夫と共に生活することにしました。
その後、第2子の妊娠・出産でブランクができてしまい、地元に伝手もなく、仕事を再開できずにいました。そこでドクターバンク(旧女性医師バンク)を利用し、紹介していただいたクリニックで週3時間から勤めることにしました。ある時、クリニックの先生に大学と復帰支援事業の共同勉強会を紹介していただいたことが契機となり、大学の復帰支援枠に所属することになりました。週4時間から勤めて子どもの成長とともに勤務時間を増やし、6年後には常勤医師になりました。
苦労もありましたが、様々な方に助けられ、ご縁がつながって今があることをありがたく思っています。
Selection
Stories
-

50歳を過ぎてからの再研修。
内科、50代
私は子育て中、臨床以外の仕事や、医療者教育といった分野で非常勤として働くことはありました。子育てが一段落し、再び医師としてフルで働ければと思いましたが、臨床の現場からは20年以上離れており、知識も手技も古くなっていたため、常勤でしっかり働くには再研修が必要だと思いました。
-

いつか再び最前線で働きたいと思いながら。
産婦人科、30代
私は大学院の時に結婚、出産しました。早期の仕事復帰を考えていましたが、子どもに重度の持病があり、研究を継続するのは困難でした。途中で投げ出す形になるのは申し訳ないと思いましたが、「仕事はこの先いくらでもできるが、小さい命を支えるのは今しかない」と、教授や医局長にも後押ししていただき、子育...
Selection
- トップページ
- 働きやすい職場を探す
- 職場への復帰