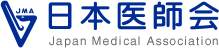2024年2月21日
第7回 生命(いのち)を見つめるフォト&エッセー 受賞作品
一般の部【厚生労働大臣賞】
「命は続く」
松友 寛(59歳)愛媛県
平成27年1月。父が定期的に通っている病院から電話が入った。父の体に
「悪性の
「1年」が余命を指していると理解するまでに、数秒の間があった。急な展開に頭がついていけなかった。胆管がんというこの腫瘍は発見が難しく、大抵の場合、見つかった時点で厳しい状態になっているのだという。人の良さそうな医師の口調に申し訳なさが
完治を目指さない父の闘病が始まった。夏を越すまでは割合に元気だったが、医師の診立ては正しく、秋の深まりとともに父は急速に衰えていった。年を越した時点で、通院での治療は限界を迎えていた。2月の末に再入院、そして早くも3月の頭には、緩和ケア病棟を備えた別の病院に転院することになった。
「痛みが出てきて
と告げると、父は情けなさそうな顔で
「ここは病気を治して退院する病院とは違うんじゃなあ。」
転院して数日が経った頃、父がぽつりとつぶやいた。緩和ケア病棟の一室。クリーム色の壁を柔らかい照明が照らしていた。この病棟では、入院患者が肉体的、精神的に少しでも心地よく過ごせるよう、看護師たちが24時間体制で面倒を見てくれる。それまでいた病院とは全く違う空気に触れ、父の表情や言動は見違えるほど明るくなっていた。そんなタイミングだけに、父の言葉をどう捉えたらいいのか分からず、僕はうろたえた。
「わしはこの病院で死ぬんよ。死んで、わしの家に帰るんじゃ。」
と続けた父の口調は、しかし、意外なほど晴れやかだった。自らの死について語りながら、自棄になったような様子は
しばらくして、病院から渡された『看取りのしおり』を読んだ。そこに『死はすべての生物が必ず果たさなければならない大切な仕事』といった一文があった。死を悲劇的な結末としか見ていなかった僕の目から、
入院して3週間。父は1日の大半を眠って過ごすようになっていた。時折目を覚ましたが、もう満足には話せない。何かに
そんなある夜、父が体の痛みを強く訴えた。看護師はモルヒネの使用を勧めながら、
「今の状態ですと、眠ったまま起きなくなる可能性もあります。」
一緒にいた弟と顔を見合わせた。事実上のお別れになるかもしれない。しかし、父にこれ以上の我慢を強いる意味はないと思った。
「お父さん、僕や。聞こえるか。」
父が薄目を開けた。深夜の病室は静かで、どこからか機械の上げるかすかな音だけが響いていた。弟は席を外している。薬剤を投与する前に、1人ずつ父との時間を持つことにしたのだ。命を閉じるという、最後の大仕事に臨む父。そんな父に言うべきことは何だろうと自問した。思い浮かんだのは、他でもない、燃え尽きようとしている父の命についてだった。父個人の命は絶えても、それで全てが終わりになるわけではない。
「よう頑張ったなあ、お父さん。」
と僕は話しかけた。
「お父さんの血は僕の中に流れとるし、僕の子どもらにも流れとる。あいつらが大人になって、結婚して子どもができたら、その子らにも流れるんや。」
「僕らが元気で生きていくってことは、お父さんからもらった命がずっと続いていくってことやろ。やけん、なんも心配いらんで。」
小さく父が頷いた。僕の方に顔を傾け、懸命に口を動かす。乾いた唇が震えた。
「あんわれ。」
あんわれ? あんわれ......そうか、「がんばれ。」か。わかったお父さん、がんばるよ。お父さんから受け取った命やもんな。
ソメイヨシノの
あの日から7年。僕らは今も父の命とともに日々を生きている。
第7回 受賞作品
一般の部: 【 厚生労働大臣賞 】
【 日本医師会賞 】
【 読売新聞社賞 】
【 審査員特別賞 】
【 審査員特別賞 】
【 入選 】
【 入選 】
中高生の部:【 文部科学大臣賞 】
【 優秀賞 】
【 優秀賞 】
【 優秀賞 】
小学生の部:【 文部科学大臣賞 】
【 優秀賞 】
【 優秀賞 】
【 優秀賞 】