医師への軌跡
医師の大先輩である大学教員の先生に、医学生がインタビューしてきました。
自分の好きなことや
臨床実習で得た気付きを
大切にしてほしい
岡部 正隆
東京慈恵会医科大学 解剖学講座 教授
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 副理事長
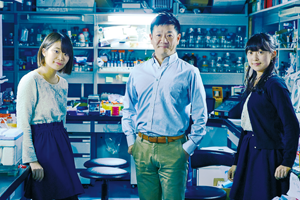
好きな分野を追いかけて
山田(以下、山):先生は医学部卒業後、研究一筋でこられたそうですね。
岡部(以下、岡):僕は子どもの頃から生き物が大好きだったんです。医学部で基礎医学に触れた時も「これはヒトの生物学だ!」と思って楽しくて仕方がなく、学部生のうちから解剖学教室に入り浸って実験していました。そんなある日、発生学の授業を受けて「臓器などの成り立ちがわかれば解剖学のすべてがわかるのでは」と思い至ったんです。大学院に進学してから9年間は、ショウジョウバエを使って、遺伝子から形態形成のメカニズムを解明する研究に没頭していました。
加藤(以下、加):そこから、どうして教育に携わるようになったのでしょうか?
岡:ある時「せっかく医師免許を持っているのに、このままハエばかりやっていていいのか、せめて脊椎動物に戻ろう」と思って(笑)。それでイギリスに留学し、魚やニワトリ、マウスの発生を研究しました。帰国後の働き口を探している時にちょうど声をかけていただき、母校に戻ってきたんです。医師免許を持った基礎医学の大学教員は少なくなっていますし、教員として基礎医学の分野で貢献するのが、自分なりの医師免許の活かし方だろう、と。
「健康」は誰が決める?
加:先生はご自身が色覚異常をお持ちで、カラーユニバーサルデザイン*の普及にも携わっていらっしゃいますよね。患者の立場で活動されて、感じたことなどはありますか?
岡:そもそも僕は、自分を患者だとは思っていません。色弱は疾病ではなく、血液型のような、遺伝的多様性の一つだと考えています。たしかに今の社会では、色弱の人が生活や仕事に不便を感じる場面はあると思う。でもそれは、少し工夫すればなくせる不便さなんです。
色弱は、先天性の場合は治療法がないので、多くの医師は、色覚検査をして「色覚異常」と診断することしかしていないのが現状です。でも本当は、医師は行政にも多大な影響力があるのだから、色弱の人が困らない社会の仕組みづくりを担うこともできるはずです。
色弱に限らず、他人と違う部分があっても、日常生活に支障がなければ、それを病気と呼ぶ必要はないと思います。本人が困っていないのに病名をつけることは、時に差別や偏見を助長します。だから医師は、その人の身体状態だけでなく、精神的・社会的な側面まで慎重に診なければならない。そして、検査で病気の人を見つけることだけではなく、「病気」と呼ばれうる人でも不便なく暮らせるような世の中をつくることにも注力してほしいと思います。「病んでいる」かどうかを決めるのは、医師ではなく、その人自身なんです。
一つひとつの気付きを大切に
山:私はそろそろ進路を考える時期ですが、何が自分の強みなのかわからず、迷っています。
岡:君たちは今、ポリクリで臨床の現場に出ているよね。日々色々な患者さんや症例を見ていると、ハッと何かに気付く瞬間が必ずあると思う。そうして気付いたことそれ自体が君たちの強みであり、個性なんです。
今は先の見えない時代で、将来に不安を抱くのもわかる。でもそんな時だからこそ、好きなことを伸ばして、自分をブランド化していけばいいんじゃないかな。これは、他人の評価を気にしろという意味ではないよ。身近なところでいいから、自分が少しでも興味を持てたことについて突っ込んで考えるようにしていれば、評価は後から付いてきます。立派な気付きじゃなくたっていい。日々の一つひとつの刺激を大切に、自分が面白いと思える道を主体的に歩んでいってほしいと思います。
*カラーユニバーサルデザイン…人間の色覚の多様性に配慮し、より多くの人に利用しやすい配色を行った製品や施設・建築物、環境、サービス、情報を提供するという考え方。
岡部 正隆
東京慈恵会医科大学 解剖学講座 教授
1993年、東京慈恵会医科大学卒業。1996年に医学博士を取得。1997年より、国立遺伝学研究所で助手を務める。イギリスに2年間留学し、2007年より現職。
山田 麻綾
東京慈恵会医科大学 4年
私は以前から、自分の強みを見つけなければ、と悩んでいたのですが、慈恵の先輩である岡部先生の「好きなことを伸ばしていけばいい」という言葉に励まされました。
加藤 千智
東京慈恵会医科大学 3年
「病気かどうかは、その人自身が困っているかどうかで決まる」というお話を聞いて、学理上の「疾患」をどう治そうかという発想に傾きがちだった自分に気付きました。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岡部 正隆先生
- Information:Winter, 2017
- 特集:新たな専門医の仕組み(前編)
- 特集:専門医になるまでの医師のキャリアのロードマップ
- 特集:どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?
- 特集:今までの専門医制度と何が変わるのですか?
- 特集:まだまだ知りたい 専門医、どうなるの?
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」② 口腔ケアの充実で合併症を減らす
- 同世代のリアリティー:番外編 1型糖尿病 前編
- 地域医療ルポ:神奈川県横浜市中区|ポーラのクリニック 山中 修先生
- チーム医療のパートナー:事務職員/アシスタントプロデューサー
- チーム医療のパートナー:事務職員
- 10年目のカルテ:公衆衛生医師 高橋 千香医師
- 10年目のカルテ:医系技官 櫻本 恭司医師
- 医学教育の展望:医学生と教員が対話し、医学教育の未来を考える
- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動
- 大学紹介:北海道大学
- 大学紹介:慶應義塾大学
- 大学紹介:岡山大学
- 大学紹介:佐賀大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:中尾 茉実×佐伯 尚美

