大学紹介
北海道大学
【教育】充実した全学教育と医学教育
北海道大学大学院 医学研究科 副研究科長 吉岡 充弘

札幌市の中心部にありながら、広大で自然豊かなキャンパスに恵まれ、充実した6年間を過ごすことで、フロンティア精神・国際性の涵養・全人教育・実学の重視という大学が掲げる四つの基本理念を理解し、生涯にわたって自己成長し続けることのできる教育が用意されている。
北海道大学は1918年に北海道帝国大学として創設され、その翌年医学部が設置された。間もなく100周年を迎える歴史ある医学部は、総合大学としての特色を存分に活かし、医学に関係する科目以外にも、学部の域を超えた北海道大学の全教員による全学教育科目や、国際的に活躍するために必要な幅広い外国語科目など、多種多様な教養科目を用意している。
1年次の医学教養コースでは他学部の学生と共にクラスを編成し、幅広い教養科目(全学教育科目)を履修できる。2年次の基礎医学コースでは、人体の正常な構造と機能、正常から病気に至るプロセスを理解し、3年次の臨床医学コースでは疾病について多面的に学び、診断・治療の基本を身につける。4年次2学期から6年次までは臨床実習コースで、全診療科を回った後、1診療科で長期の診療参加型臨床実習を行う。実習可能な病院数が多く、また、基礎・臨床いずれでも海外での短期留学が行える機会が用意されている。医学研究を志向する学生には、早期に研究の機会にふれ、医学・医療の急速な進歩と社会情勢の変化に対応できる研究者を養成することを目的としたプログラム(MD-PhDプログラム)も用意されている。
また、最近本学が重視しているのは、医学教育の国際化である。四季折々の自然が楽しめる地の利と、教員が個別に指導を行えるきめ細やかな指導体制を生かして、世界各国の大学と協定を締結し、年間40人近い数の留学生を受け入れている。多様な留学生と共に学び、国内にいながら国際色豊かな医学教育環境を体感できることも、大きな特色である。
【研究】北海道大学大学院での研究
北海道大学大学院 医学研究科 副研究科長 渥美 達也

北海道大学大学院医学研究科(医学研究院)では、基礎医学、社会医学、臨床医学のいずれの領域においても非常に幅広く研究が行われています。特に、放射線医学分野の最先端研究開発支援プログラムを推進した「分子追跡陽子線治療装置」の開発、解剖発生学分野では脳機能発現の舞台となる興奮性シナプス伝達系の分子解剖学的研究など、世界を牽引するトップレベルの研究は枚挙に暇がありません。また、革新的イノベーション創出プログラムに採択された北海道大学の「『食と健康の達人』拠点」と関連する研究の一環として、公衆衛生学のチームが北海道内の市町村を舞台に健康政策の基礎資料となる「食習慣と健康状態の疫学調査」を行うなど、地元文化と密着する研究も広く展開しています。
私自身が責任者を務める免疫・代謝内科学分野は、膠原病・臨床免疫学、内分泌・代謝内科学、腎臓内科学の3領域をカバーしており、もっとも人数の多い教室のひとつです。診療を行いながら、臨床に密接に関わる研究や将来臨床に役立つ基礎研究を広く展開しています。医学生の皆さんの多くは、将来は臨床医に、と考えて勉学に励んでいることでしょう。研究者を目指す人は言うまでもありませんが、臨床医を目指す場合も大学院で研究を行う意義は大きいと思います。優れた指導医になるためにはEBM(Evidence Based Medicine:根拠に基づく医療)を理解し実践できる医師にならなければなりません。論文を読み込み、どういう背景で研究が行われ、その結果がどのようにまとめられているかを理解するには、自らが実際に研究を経験することが重要です。自分自身が研究に携わらなければ本当の意味での専門医にはなれないと確信しています。そのためにも、一定の期間、大学院に在籍し研究に従事することは非常に重要であると思います。
【学生生活】歴史あるキャンパスと自由な文化の中で学ぶ
北海道大学 医学部 5年 田中 翔
同 5年 鳴海 茜
鳴海:北海道大学のキャンパスはとても綺麗で、近所の子どもたちが遊びに来たりもします。実習の合間に散歩すると、いい気分転換になります。札幌は街並みが素敵で、食べ物もおいしくて、本当に良いところだと思います。
田中:夏にはキャンパス内でジンギスカンパーティー、通称ジンパが毎日のように開かれています。大学生協でもジンパセットを安く売っているんですよ。秋にはキャンパス内の銀杏並木をライトアップする金葉祭があって、冬はスキーに行けて、四季それぞれの楽しみがあります。医学展など市民の皆さんがいらっしゃるイベントもありますし、勉強以外の部分もとても充実しています。
鳴海:私たちは、毎年1回『フラテ』という学内誌を発行する、フラテ編集部という部活に所属しています。フラテ編集部は、大正14年から続く歴史ある学生主体の団体です。新任教授や退任教授にインタビューしたり、全国各地のOBの先生方との座談会を毎年開いています。去年の座談会は静岡で行いました。学生主体で行っているフラテ編集部の活動は、社会勉強にもなりますし、大先輩の先生から期の近い先生まで、全国各地にいらっしゃる色々な先生とお話しできるのは、自分の将来を考えるうえでもいい刺激になっています。
田中:医局の説明会に行ったときにも感じるのですが、北大ってすごく自由な雰囲気があるんです。選択肢の一つとして情報をくれるけど、決して強制はされない。広い視野を与えてくれる先輩方がいて、色々な選択肢の中から自分の行きたい道を選ぶことができる。そういう自由な雰囲気も、北大の魅力だなと思っています。
※医学生の学年は取材当時のものです。

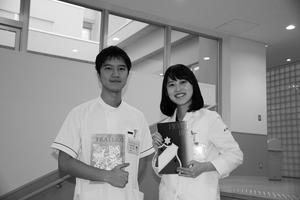
〒060-8638 北海道札幌市北区北15条西7丁目
011-716-2111



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岡部 正隆先生
- Information:Winter, 2017
- 特集:新たな専門医の仕組み(前編)
- 特集:専門医になるまでの医師のキャリアのロードマップ
- 特集:どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?
- 特集:今までの専門医制度と何が変わるのですか?
- 特集:まだまだ知りたい 専門医、どうなるの?
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」② 口腔ケアの充実で合併症を減らす
- 同世代のリアリティー:番外編 1型糖尿病 前編
- 地域医療ルポ:神奈川県横浜市中区|ポーラのクリニック 山中 修先生
- チーム医療のパートナー:事務職員/アシスタントプロデューサー
- チーム医療のパートナー:事務職員
- 10年目のカルテ:公衆衛生医師 高橋 千香医師
- 10年目のカルテ:医系技官 櫻本 恭司医師
- 医学教育の展望:医学生と教員が対話し、医学教育の未来を考える
- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動
- 大学紹介:北海道大学
- 大学紹介:慶應義塾大学
- 大学紹介:岡山大学
- 大学紹介:佐賀大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:中尾 茉実×佐伯 尚美

