大学紹介
慶應義塾大学
【教育】次世代を先導する「一身独立」のPhysician Scientistの育成
慶應義塾大学 医学部 医学教育統轄センター長 平形 道人

2017年に創設100周年を迎える慶應義塾大学医学部は、塾祖福沢諭吉に報恩の念を抱く世界的細菌学者北里柴三郎を初代医学部長として誕生し、多くの医学界のリーダーを輩出し、その中心的な役割を果たしてきました。福沢の「贈医(患者のために全身全霊を尽くす医師のあり方)」の精神、北里の理念「基礎・臨床一体型医学・医療の実践」を継承し、教育目標として「豊かな人間性と深い知性を有し、確固たる倫理観に基づく総合的判断力を持ち、生涯にわたって研鑽を続け、医学・医療を通して人類の福祉に貢献する人材の育成」を定めています。その達成のために、以下の独自教育プログラムを推進しています。
1)Medical Professionalism:医師の責務・医療倫理の理解、医師としての行動規範の修得、ヒューマニズムの実践、コミュニケーション能力の向上、生涯学習の姿勢の確立など、良き臨床医、優れた医学研究者となるために最も大切な医療プロフェッショナリズムを入学から6年間一貫して学びます。2)「自主学習」(全学生必修の研究プログラム):1989年に、わが国で初めて設置された研究実習で、学生が研究、臨床の第一線で活躍する教員の研究室に加わり、自分で選んだテーマの研究に挑戦し、創造的な問題解決能力を涵養します。また、医学研究のリーダーの育成を図り、「研究医養成プログラム(MD-PhDコース)」も設置しています。3)医療系三学部合同教育プログラム:医学部、看護医療学部、薬学部の学生が交流し、「グループアプローチによる患者中心の医療実践」をテーマとして共同作業を行い、チーム医療に貢献する視野の広い医療人を目指しています。4)地域基盤型臨床実習: 地域医療を担う教育関連病院に長期滞在し、大学病院とは異なる地域医療(プライマリ・ケア、健康・予防医療など)を学び、わが国の今後の医療を支える能力を身につけます。5)国際交流プログラム:1984年に始まった「短期海外留学プログラム(欧米を中心とする20以上の交流医学部・病院での1か月以上の臨床実習。2015年度実績 34名)」、「ラオス・プライマリヘルスケア保健医療チーム活動プロジェクト」などの教育プログラム、「国際医学研究会(南アメリカ)」、「日韓医学生学術交流会」、「日中医学生交流協会」、「アフリカ医療研究会」などの学生団体活動により、国際医療人としての資質を修得しています。
本学は21 世紀の医療・医学研究を担うリーダーを引き続き育成するために、慶應義塾の「半学半教」の精神に基づき、「教員/指導医・学生」、「専門分野・研究領域」「職種」の境界を超え、お互いに学び、教え合う教育システムの更なる充実に取り組んでいます。
【研究】実証的に真理解明する精神
慶應義塾大学 医学部 機能形態学講座 教授 久保田 義顕

慶應義塾大学は約160年前、福沢諭吉によって設立されました。その当時、福沢諭吉が門下生に対しその志を託した、いわゆる『建学の精神』が今でも脈々と受け継がれております。『独立自尊』『半学半教』などは、塾外の方でも耳にしたことがあるかもしれません。それらと並んで重んじられるものに『実学の精神』があります。多くの方が「実学」と聞いて、おそらく「実際に役に立つ学問」という印象をもたれるかと思います。近年、医学・生物学を含めた自然科学研究において、研究成果の実用化、産業化の必要性が声高に叫ばれ、国家的な方針として、実用化に近い研究に対して重点的に公的資金が配分されるという傾向が日に日に強まっております。実のところ、福沢諭吉の言うところの『実学の精神』はある意味、その真逆の精神を意味しております。この理念においては、科学(サイヤンス)とは、実証的に真理を解明する科学的な姿勢、つまり実用性や利潤性を度外視し、物事の真実を徹底的に追及する姿勢を指します。これは昨今の応用研究に偏りがちな風潮、世論に対して、160年前にそれを予知し、警鐘を鳴らしていたのかもしれません。本年度の慶應医学賞受賞者である、京都大学本庶佑名誉教授 のスピーチにおける、「医療、医学におけるイノベーションは、偶然の発見に幾多の幸運が重なって達成される」「人間の脳で予知可能なものに大きなブレークスルーは無い」などの名言は、図らずも福沢諭吉の『実学の精神』とマージするものです。ともあれ、本学基礎・臨床医学分野においては、再生・発生・免疫・がん・神経・代謝・老化・疫学など多様な部門が、個々の領域における世界トップレベルの研究者たちとしのぎを削り、同時に、同じく建学の精神である『社中一丸』の理念のもと、『基礎・臨床一体型医学・医療の実現』に向け、一丸となって、日々研究活動に勤しんでおります。
【学生生活】時間をうまく使って個性を伸ばす
慶應義塾大学 医学部 5年 松井 友哉
同 5年 松田 理沙
松田:これまでの授業の中で特に面白かったなと記憶に残っているのが、教室で整形外科の手術をライブ中継で見た授業です。4年生でまだ病院実習が始まっていなかったので、初めて見た手術として印象に残っています。
松井:新しい技術を活用した、最先端の授業が多いのが慶應の特徴だと思います。2年生になると、全員にiPadが配付されます。例えば組織の授業では、そのiPadを使って標本画像を共有したりします。顕微鏡では一つの標本をグループで一緒に見ることはできないので、とても便利です。解剖の授業では、3D眼鏡を使って、先生が行った解剖を画面越しに見たりしています。解剖では三次元的な構造把握が大事と言われるのですが、より感覚で掴みやすいなと思いました。
松田:慶應の雰囲気を一言で表すなら、「自由な大学」です。カリキュラムに比較的余裕があるので、各自やりたいことをやって個性を伸ばす、という感じです。部活やアルバイトを頑張りながら、要領よく勉強も両立している人が多い印象です。
松井:僕はヨット部の活動に時間を充てています。ヨットは戦略要素が強く、すごく頭を使う競技で楽しいですね。部活の縦のつながりも学年内の横のつながりも強いので、試験対策・国試対策も協力して取り組んでいます。
松田:私は馬術部に入っています。馬術は人間の技術だけじゃなくて、馬の能力や性格の要素も影響するのが面白いんです。大学の横に厩舎があるので、毎朝通って馬の世話をしています。
※医学生の学年は取材当時のものです。

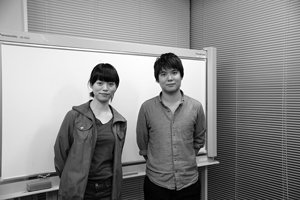
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35
03-3353-1211



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岡部 正隆先生
- Information:Winter, 2017
- 特集:新たな専門医の仕組み(前編)
- 特集:専門医になるまでの医師のキャリアのロードマップ
- 特集:どうして専門医の仕組みを見直すことになったのですか?
- 特集:今までの専門医制度と何が変わるのですか?
- 特集:まだまだ知りたい 専門医、どうなるの?
- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」② 口腔ケアの充実で合併症を減らす
- 同世代のリアリティー:番外編 1型糖尿病 前編
- 地域医療ルポ:神奈川県横浜市中区|ポーラのクリニック 山中 修先生
- チーム医療のパートナー:事務職員/アシスタントプロデューサー
- チーム医療のパートナー:事務職員
- 10年目のカルテ:公衆衛生医師 高橋 千香医師
- 10年目のカルテ:医系技官 櫻本 恭司医師
- 医学教育の展望:医学生と教員が対話し、医学教育の未来を考える
- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動
- 大学紹介:北海道大学
- 大学紹介:慶應義塾大学
- 大学紹介:岡山大学
- 大学紹介:佐賀大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:中尾 茉実×佐伯 尚美

