女性のみの職場でバランスをとる
~東京労災病院 耳鼻咽喉科の働き方~-(前編)
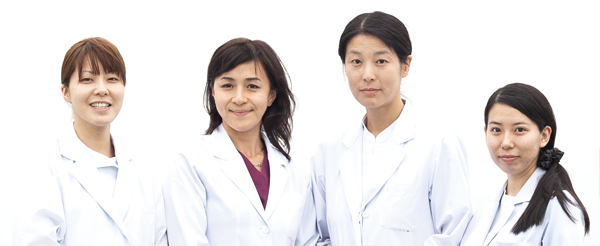
時短勤務の先生と働くことで時間の重要性に気づく
津田(以下、津):急性期の総合病院で女性が中心的な役割を担いながら、かつワークライフバランスのとれた働き方をしているというのは素晴らしいことだと思います。女性だけの職場ということで、男性がいる職場との違いは意識されているのでしょうか。
友田(以下、友):男女の違いをすごく意識しているというわけではないのですが、私自身こちらに着任してはじめて時短勤務の先生と一緒に働くようになったことで、仕事の仕方は考えるようになりました。フルタイムで働いていれば当然、当直もありますし、夜間や緊急の呼び出しにも応じるわけですが、お子さんが小さいと、時間が来たら帰らなければならないし、朝早く来るのも難しいですよね。手術が長引いてしまったら、最後まで診ることもできない。そういう中で、どうしたら仕事を楽しいと思ってもらえるか、責任を持ってもらえるかということを考えました。
酒井(以下、酒):友田部長が着任したのは、以前ここにいた先生が産休明けで復帰し、時短勤務で働いていたときでした。私自身も時短の先生と一緒に働いてみることで、時間の重要性に気づきましたね。それまでは何となく仕事していましたが、「何時までに終わらせよう」と意識するようになりました。今現在は誰も時短を取ってはいませんが、不測の事態さえなければ、19時を目処に帰るようにしています。
津:それぞれ結婚したりお子さんがいる中で、一緒に働くとなると大事なことは何ですか?
酒:コミュニケーションはやはり大事だと思いますね。互いに気を遣い合える関係でないと、うまくいかないと思います。
津:誰かが急に担当できなくなったときに、暗黙のうちに誰かがやってくれるというような関係ですね。そうした気遣いは女性だからできるのでしょうか。
友:同性同士だからこそ気がつく部分はあるのかもしれません。ここはたまたま男性がいないから、女性同士が必要な気遣いをし合うことができているという感じでしょうか。例えば子どもが熱を出してしまったとき、お母さんを責めても仕方がないのに、男性だと「突然休まれちゃ困る」と言う方が少なくないと感じます。そういう場合は文句を言うよりも、残りの人でどうやりくりしていくかを考えることの方が大事だと私は思います。こちらに来てからは、若い先生たちが自主的に手伝ってくれるので本当に助かっています。
女性のみの職場でバランスをとる
~東京労災病院 耳鼻咽喉科の働き方~-(後編)
院内の医師全員で患者さんを診る
 津:女性ばかりで困ることはありますか?
津:女性ばかりで困ることはありますか?
友:今は特に感じませんが、例えば同時期に産休の先生が多くなってしまうと、院内だけで対処するのは難しいかもしれません。様々な科をローテーションする看護師と違って、医師は担当する診療科が違えば、隣の科の人数がいくら足りないと言っても手伝うことはできませんからね。ここは医局とのつながりがそれほど強くないこともあり、急に人数が少なくなった時には近隣の病院など地域で手伝ってもらえるような体制があればありがたいなと思います。
津:病院の枠を超えた連携が必要ですね。
友:はい。また院内でも、「医師全員が皆で患者さんを診ているんだ」というような考え方がもう少し広がればと思っています。例えば救急医療なら、ある程度まで診たら次の先生にバトンタッチするような風土が既にありますが、それ以外の診療科ではまだ主治医制を大事にしているところがあります。患者さんからも、途中で医師が変わると不安になるという声を聞きますので、科のメンバーが全員でしっかり診ていること、誰が担当になっても同じ医療を提供できることを伝え、安心感や理解を得ることも必要だと感じます。
数時間の外来だけでも手伝ってもらうと助かる
津:酒井先生はご結婚されたばかりだそうですが、お子さんを産もうと思ったとき、不安に思うことはありますか?
酒:仕事内容に責任が持てるかが気になりますね。家庭があることで、今まで持てていた責任が持てなくなるのでは…と。
友:妊娠・出産の時期や、産後復帰してしばらくは、仕事はある程度選んでもいいのではと思います。責任感が強い人ほど「迷惑をかけるから…」と辞めてしまいがちですが、そういう人材が眠っていると、もったいないと思うんです。外来だけでも短時間でも、手伝ってもらえたらとても助かります。
津:では、時短からキャリアの道に戻るタイミングについてはどうお考えですか?
友:ある程度自分の専門性が見えてきてから出産すれば、復帰後、わりとすぐにキャッチアップできると思います。ただ、若いうちに産む場合は、その後のキャリアについて少しでも考えておいたほうがいいと思います。勉強や仕事に割ける時間が限られるなかで、短時間でも仕事ができる分野や、どのようにキャリアアップできるのかについて、私たちからも若い先生たちに伝えていけたらと思います。
広い視野をもって情報を集めてほしい

津:若いうちに、理解がある上司や先輩に出会えない場合、キャリアが不安定になってしまう側面もあるのでしょうか。
友:今、女性医師が医局に属さず、一人で妊娠・出産やキャリアのプランを立てようと思うと、すごく難しいと思うんです。昔の医局のように大きな視野でまとめてくれる方がいれば、産休後に大学で研修をし直してから、また臨床に出たりもできると思うのですが、今は「他の病院に行くにも人脈がない」という人も少なくありません。ですが、近年は制度もいろいろできているし、相談できるところも増えているので、自分に合うものを必ず見つけられると思います。広い視野をもって情報を集めてほしいですね。
津:最後に、キャリアを考える上で一番大事に思っていることを教えて下さい。
友:いろいろなキャリアがありますが、それでもやはり一番は、「患者さんに誠実に」ということだと私は思っています。自分のワークライフバランスも大事ですが、やっぱり他の仕事と違って、命と関わる仕事をしているという認識は大前提にあるべきだと考えます。もちろん、プライベートも充実していないと、良い医療も提供できないと思いますが、医師になろうと思った頃の志をいつまでも持っていてほしいですし、自分がそういう職業を選んだということを誇りに思ってほしいと思います。
津:どうもありがとうございました。女性の立場や考えをよく知る機会として、ここに若い男性の医師がいらしたら、とても勉強になるでしょうね。
友・酒:ぜひ来てほしいですね。お待ちしています。
東京労災病院 耳鼻咽喉科
聞き手:津田 喬子先生
日本医師会男女共同参画委員会委員 日本女医会会長



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:一戸 由美子先生
- Information:July, 2013
- 特集:意外と知らない 医師会のリアル
- 特集:医師会の三層構造
- 特集:郡市区医師会の現場を見てみよう!
- 特集:番外編・都道府県医師会って?
- 特集:日本医師会副会長の一日
- 特集:医師会の今後について 役員と学生が真剣に話してみた
- 同世代のリアリティー:女性のキャリア・ライフイベント 編
- NEED TO KNOW:患者に学ぶ(1型糖尿病)
- チーム医療のパートナー:臨床薬剤師
- 地域医療ルポ:北海道名寄市|名寄市風連国民健康保険診療所 松田 好人先生
- 先輩医師インタビュー 安藤 高朗(医師×病院経営者)
- 10年目のカルテ:産婦人科 池宮城 梢医師
- 10年目のカルテ:産婦人科 宮本 純孝医師
- 医師の働き方を考える:女性のみの職場でバランスをとる
- 医学教育の展望:臨床実習に診療所での体験的学習を導入
- 大学紹介:獨協医科大学
- 大学紹介:杏林大学
- 大学紹介:名古屋市立大学
- 大学紹介:愛媛大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3

