
「学び」は「どこ」で生じる?
人は「状況の中」で学び合っている(前編)
「徒弟制」的な学び
前ページでは、「勉強」と「学ぶ」の違いについて考えました。医師として正しい知識を身につけて成長していくために、「勉強」がとても大切であることは言うまでもありません。一方で、勉強しただけでは、いきなり医師として完璧に働くことはできません。現場に出て上級医らのやり方をまねたりしながら、何年もかけて実践知を蓄えていくことで、医師として一人前になっていきます。
こうした、見よう見まねで実践的な知識・技術を身につけ、ステップアップしていくあり方は「徒弟制」と呼ばれます。徒弟制と聞くと、何となく閉鎖的・封建的で悪いもの、というイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、「学ぶ」の語源が「まねぶ」であることを思い出せば、こうした徒弟制のような学びのあり方の方が、人間本来の学びに近いように感じられます。
実際、教育学や心理学、認知科学などの分野では、徒弟制的な学びのあり方に一定の評価が与えられています。アメリカの認知科学者であるジョン・S・ブラウンやアラン・コリンズは、徒弟制の中で学びが生じる過程を研究し、「認知的徒弟制*1」として理論化しています。
「学び」は「どこ」で生じる?
徒弟制、あるいは認知的徒弟制的なシステムは、現代でも様々な場面で活用されています。しかし、いくら徒弟制的なシステムが評価されているといわれても、「もっと効率のいい教え方があるのではないか」などと疑問を覚える人もいるかもしれません。徒弟制的なシステムはなぜ有用だとされるのか。それを深く知るためには、「学びとはそもそもどういうことか」を問い直す必要があります。
「人が学ぶ」とは、どのような現象なのでしょうか。「個人の頭の中に、知識が定着すること」「できなかったことができるようになること」などの答えが思い浮かぶでしょうか。これらの答えには、「学びは人の頭の中で起こるものだ」という前提が置かれています。しかし実は、近年の教育学の世界では、学びは個人の頭の中に閉じたものではなく、個人の頭の中と外界との「間」に開かれている、と捉えられているのです。これは一体どういう意味なのか、「学び」に関する研究の歴史を振り返りながら読み解いていきましょう。
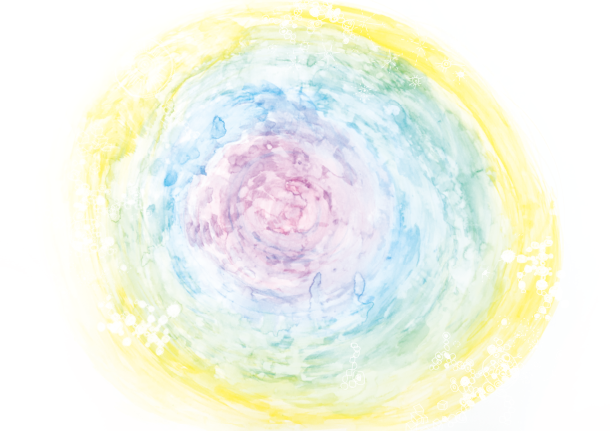

「学び」は「どこ」で生じる?
人は「状況の中」で学び合っている(後編)
20世紀における学習観の変遷
~「できる」から「わかる」へ~
学びや学習に関する研究は、まず心理学の分野で発展してきました。20世紀前半の心理学では、「行動主義」という考え方が支配的でした。人間の心理を分析する際に、客観的に観察可能な「行動」のみを対象としようというものです。
さて、この行動主義にもとづくと、人間の学習も、他者により観察可能な行動の変化(「できない」から「できる」へ)によって把握されることになります。
アメリカの心理学者バラス・スキナーは、行動主義にもとづいて動物の学習の様子を実験により観察し*2、その結果から「プログラム学習*3」を提案しました。この学習法は、例えばドリルを用いた反復演習など、様々な場面で採用されています。
しかし、「できるか否か」だけに着目すると、「解法を丸暗記しているが、なぜ解けるのかわからず応用もできない」という人も、「十分学んでいる」とみなされてしまいます。学習は、行動主義だけで解明しきれるものではありませんでした。
20世紀半ばになると、行動主義に代わり認知主義が台頭します。人間が外界からの情報をどのように知覚し処理しているか、という「認知」そのものに関心が向けられるようになり、学習論のテーマは「できる」から「わかる」へと大きく変化しました。
ジャン・ピアジェは、認知心理学の代表的な研究者の一人です。彼は、「人は自分がもともと持っている認知の枠組み(=シェマ)を使って外界の対象と相互作用しながら、概念や知識を自ら学び取っていく」と考えました。プログラム学習などでは、人は問題を与えられて解き、自分の外側にすでにある知識を頭の中に「取り込む」存在とされます。それに対してピアジェは、知識は外界にそのままあるのではなく、個人の頭の中と外界との相互作用によってはじめて構成されるという立場に立ったのです。
「他者」と「学び合う」
ピアジェは、個人と外界の相互作用に着目したものの、「個人がどう発達していくか」という観点から脱することはありませんでした。しかし、誰しも社会の中で、周囲の他者と関わりながら生きています。たった一人で環境や対象に働きかける、という状況はほとんどありえないでしょう。ソ連の心理学者レフ・ヴィゴツキーは、子どもには「自力でできる領域」と、「他者(大人や、自分より発達の進んだ子ども)と一緒にやればできる領域」とがあるとし、子どもの発達における他者の働きかけの重要性を示して、後の研究者に大きな影響を与えました。
こうした流れを受け、1980年代には「状況的学習」という概念が提唱されはじめます。人の学習は「状況に埋め込まれている(situated)」と表現され、知識は人の頭の中で構成されるのではなく、周囲の状況(身の回りの他者や、使う道具、文脈)との関わりと切り離すことができないとされます。
ジーン・レイヴとエティエンヌ・ウェンガーによる「正統的周辺参加」論は、状況論の代表的な研究の一つです。彼らは徒弟制を研究し、学習を「人が実践共同体に参加して、成員としてアイデンティティを形成する過程」そのものだと定義しました。
例えば寿司職人は、まず見習いとして皿洗いや掃除、出前などの仕事を任されます。この仕事は、寿司を握るという仕事から見れば「周辺的」ですが、店を回していくために不可欠な「正統的な」仕事です。そこから、次第に高度な仕事を教わり、店の仕事の進め方や言葉遣いを身につけながら、一人前の職人に成長していきます。状況論的な考えにもとづけば、この過程は「見習いが寿司を握る知識や技術を身につけた」という以上の意味を持ちます。見習いが先輩や親方と関わること、各人の店の中での立場や役割が少しずつ変化していくこと、一人前になって「店の文化」を継承した職人が、店を維持し、あるいは変革していくこと。こうした状況の変化すべてが、すなわち「学び」だと捉えられるのです。
医師にとっての「学び」とは
医学生の皆さんが臨床実習に行くと、患者さんの問診や血圧測定、検温などを任されることがあるかもしれません。単なる見学ではなく、周辺的だけれど正統的な役割を持つことで、皆さんはその診療科が行う医療という実践に少し「参加」することができます。研修医になれば、その役割はやや拡大し、採血や日常的な処置を実施したり、入院患者さんを継続的に診察し、変化があれば上級医に相談しながら対応するといった、より本格的な仕事を任されるようになります。このように求められる役割を果たすなかで、「様々な患者の変化とその対処方法」や「治療に対する様々な反応」などの経験が蓄積され、先輩や上級医の行動や指示の意味が理解でき、次第に仕事の全体像が把握できるようになるでしょう。
このような実践的な場では、患者さんの状態、先輩医師の動き、看護師の業務の流れなど、変化し続ける状況を見ながら、そこに自分のアプローチを合わせていく必要があります。その方法は、誰かが教えてくれるものではなく、周囲を観察したり、質問や対話をするなかから見出していくほかありません。
このように考えると、医師もまた、一人で学べるものではなく、患者さんやその家族、先輩や同僚の医師、多職種との相互作用の中で学びを深めていく存在であることがわかります。もちろん、ときにはうまくいかないこともあるでしょう。しかしそれでもめげずに改善とチャレンジを続けていくことで、徐々に共同体の中で認められ、重要な役割を任せられるようになり、一人前の医師としての自覚や自信を獲得していくのです。
*1 認知的徒弟制…「モデリング(親方が模範を示す)」「コーチング(親方が弟子に教える)」「スキャフォールディング(弟子が自立できるよう支援する)」「フェーディング(親方が手をひくことで弟子を独り立ちさせる)」という四つの段階により学びが生じるとする。
*2スキナーによる実験…代表的な実験に、「スキナー箱」という、レバーを押すと餌が出る仕掛けを施した箱を用いたものがある。箱にラットなどを入れ、「偶然レバーを押す(反応)と餌が手に入る(強化刺激)」という経験を繰り返すことで、ラットが「レバーを押す」という反応を学習する、というもの。
*3プログラム学習…この学習法は、次のような要素に特徴づけられる。「スモールステップ」:一定の学習目標を設定し、そこに至るまでの過程を系列化して、無理なく習得できるよう小刻みに分割する。「即時確認」:学習者に設問を解かせ、正解か不正解かを即座にフィードバックする。「自己ペース」:個々の学習者に合ったペースで進める、など。
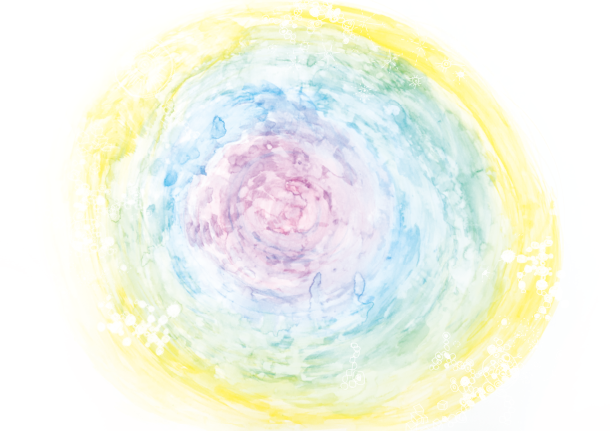
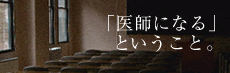


- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:高山 義浩先生
- Information:Winter, 2020
- 特集:他者に学ぶ、他者と学ぶ ~医師と医学生の学びを問い直す~
- 特集:「学び」は「どこ」で生じる?~人は「状況の中」で学び合っている~
- 特集:医学教育の中で「他者」と「学び合う」ための仕掛け
- 特集:Interview1 春田 淳志先生 筑波大学医学群 医学教育企画評価室(PCME) 医学医療系 地域医療教育学/ 総合診療グループ 准教授
- 特集:Interview2 大嶽 浩司先生 昭和大学医学部 麻酔科学講座 主任教授
- 特集:医師と医学生の学び~より良い医師を目指して~
- 同世代のリアリティー:カメラマン 編
- チーム医療のパートナー:療育に関わる専門職【後編】
- 地域医療ルポ:神奈川県横須賀市|三輪医院 千場 純先生
- レジデントロード:内分泌・代謝・糖尿病内科 今村 修三先生
- レジデントロード:小児外科 宮嵜 航先生
- レジデントロード:総合診療科 田中 孟先生
- 医師の働き方を考える:がんと闘病しながら、研究も私生活もアクティブに
- 日本医師会の取り組み:健康スポーツ分野における様々な取り組み
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:宮崎大学「地域包括ケア実習」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- 日本医師会後援映画「山中静夫氏の尊厳死」
- FACE to FACE:山下 さくら × 河野 大地

