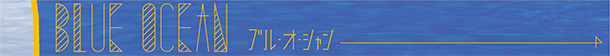
Blue Ocean
本連載は、医師不足地域で働く若手医師に、地域医療の最前線で働くことの魅力についてお尋ねするコーナーです。今回は茨城県の筑波学園病院に勤務する花澤碧先生にお話を伺いました。

多職種と同じ目線で協力し合い
自分が必要とされる地域で働く
地域密着型の医師を目指す
――花澤先生が医師を目指した理由を教えてください。
花澤(以下、花):親が医師なので医師という職業が身近だったこともあり、小学校の卒業文集には「医師になりたい」と書いていました。当時はドラマの「Dr.コトー診療所」の影響から、離島で働く医師に憧れがありました。私は水戸市の出身で、高校までずっと県内だったので、大学も地元である筑波大学を選び、地域枠で入学しました。
――小さな頃から、医師不足地域の医療についてのイメージは持たれていたのですね。
花:はい。大学の地域医療実習では、親の大学時代の同期の先生がいる礼文島に行き、離島の医療を目の当たりにしました。今は離島にこだわる気持ちはありませんが、医師の不足地域で働くことに魅力を感じています。
――臨床研修先に日立総合病院を選んだ理由を教えてください。
花:日立総合病院は救急車を99%受け入れる病院で、重症患者でもファーストタッチは必ず研修医が行います。最初の2年間で救急医療をしっかり経験しておきたいと思ったのが選択した一番の理由でした。また、医局の雰囲気の良さも魅力でした。医師が決して驕らず、他職種の方と同じ目線で対等に診療に当たっていたのです。科や職種の垣根を越えた協力体制も整っていて、「皆でこの地域を支えよう」という気概に溢れていました。
臨床研修を通じて、軽症から重症、子どもからお年寄りまで、様々な疾患と人に出会い、多様な社会背景や家庭環境に触れることができました。この時の経験は、今の内科での救急対応にも非常に役立っています。
――呼吸器内科に進んだ理由を教えてください。
花:呼吸器内科は広く全身を診られることなどから、自分の中の地域密着型の医師像に近いと思ったからです。筑波大学の医局に入局し、3年目は国立病院機構水戸医療センターで、呼吸器内科を半年、あとの半年は内科をローテーションしました。4年目は再び日立総合病院へ赴任し、5年目の現在はつくば市の筑波学園病院に勤務しています。今年の10月からは初めて大学病院で勤務する予定です。
――印象に残っている患者さんはいますか?
花:4年目の日立総合病院で、進行肺がんの診断から看取りまで自分が主体となり、じっくりと関わったことが印象に残っています。ご本人やご家族の人生観や自宅での生活、社会的な背景も、診療のうえでは疾患そのものの治療と同じくらい大事な要素だということを実感し、非常に勉強になりました。
今の病院ではがんの患者さんよりご高齢の方の誤嚥性肺炎などを診ることが多いのですが、やはりしっかり患者さんの目を見て話し、初対面の時からその人自身の価値観を引き出せるようにと心がけています。
他職種の力を借りて
――他職種との関わりで注意していることはありますか?
花:私はまだ5年目なので、わからないことは他職種の方に何でも訊くようにしています。なかでも看護師さんは、患者さんやご家族の様子を一番間近で見ています。終末期の方を診る際などには特に、看護師さんからの情報は不可欠なので、密な連絡を心がけています。
――今後の展望をお聴かせください。
花:10月からの大学病院勤務の際には、最新の治療や高度医療に目を向けますが、その後は県内の医師不足地域で臨床に携わるイメージを持っています。自分が求められる場所ならどこへでも行くつもりです。
――茨城県や医師不足地域で働くことの魅力は何でしょうか?
花:医師が少ない地域のほうが、医師と他職種の協力体制が強く、チーム医療が実践できているように感じています。皆が「この病院が地域の砦」という責任感や使命感を持っている姿に尊敬の念を抱きます。
仕事以外では、都心が近いこと、自然のスポットが多いことが茨城県の魅力だと思います。日立周辺はラフティングやバーベキュー、登山などアウトドアのレジャースポットが充実しており、臨床研修の同期などと遊ぶ場所には困らないと思います。

――最後に医学生にメッセージをお願いします。
花:医師はあらゆる人を相手にする仕事なので、学生のうちに様々な人と関わっておくと、医師になってからのコミュニケーションに役立つと思います。私自身は医学部の中で付き合いを完結させてしまっていたので、もっと友人知人の幅を広げておけば良かったと思っています。
研修先を選ぶ際は、病院の雰囲気を自分の肌で感じ取ることを大切にしてほしいです。特に多職種の連携体制が鍵ですね。研修医は何もできない存在なので、上級医だけでなく多職種の力をたくさん借りて、多くのことを学んでほしいと思います。


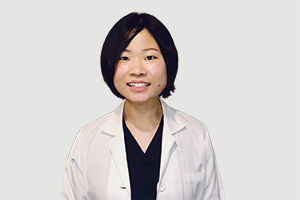
花澤 碧先生
2018年 筑波大学卒業
筑波学園病院 呼吸器内科
※取材:2022年8月
※取材対象者の所属は取材時のものです。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:三木 淳先生
- Information:Autumn, 2022
- 日本医師会の取り組み:新会長インタビュー
- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアI 10年目以降の中堅医師の生き方
- 特集:医師のキャリアのターニングポイント
- 特集:XX年目のカルテ 脳神経内科:中嶋 秀樹医師
- 特集:XX年目のカルテ 放射線治療科:永井 愛子医師
- 特集:XX年目のカルテ 小児心臓血管外科:原田 雄章医師
- 特集:XX年目のカルテ 公衆衛生医師:高橋 千香医師
- チーム医療のパートナー:連携口腔ケアサポートチーム
- Blue Ocean:茨城県|花澤 碧先生(筑波学園病院)
- 日本医学会 120年のあゆみ
- 医師の働き方を考える:長崎大学理事 伊東 昌子先生
- 日本医師会の取り組み:医師の多様な働き方を支えるハンドブック
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:愛媛大学「保健所実習」
- 同世代のリアリティー:ブライダル業界 編
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医学生の交流ひろば:米国内科学会Student Committee
- 医学生の交流ひろば:Team Medics
- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A
- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~再受験生・編入生のこれまでとこれから~
- FACE to FACE:福永 ゆりか×大神 絵理華

