医師への軌跡
全ての医師・医学生がキャリアを自己決定できるように
賀來 敦
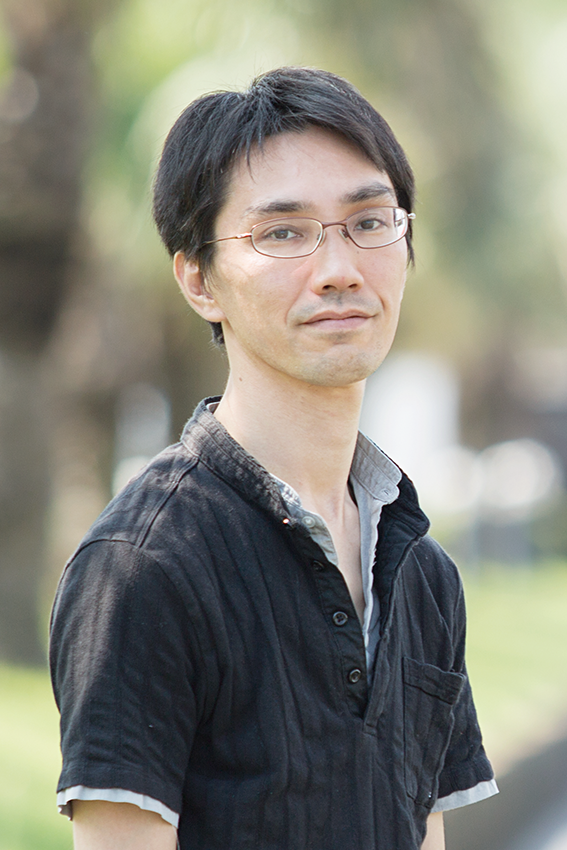
医師のキャリア形成を支援
――賀來先生は全国各地で、医師・医学生のキャリアに関する講演やワークショップを行っていらっしゃいます。先生が医師のキャリア形成に興味をもったのはいつ頃だったのですか?
賀來(以下、賀): 新医師臨床研修制度が始まった頃です。制度の変更によって、医学生は自分で行きたい研修病院を探し、マッチングを受けることができるようになりました。医学生は、説明会や病院見学で情報収集をし、自分が一番良いと思う研修病院に応募するという、一般企業の就職活動に似たプロセスを経るようになったのです。私はその頃医学生でしたが、過去にMRとして働いた経験があったので、そのプロセスにすんなり入っていけました。しかし、周囲を見ていると、どうもノウハウを持っていないようでした。そこで試しに「病院見学への行き方」「研修分野の選び方」といったテーマで昼休みにミニレクチャーをしてみると、50~60人が集まったのです。これは結構ニーズがあるぞ、と感じたのが最初のきっかけですね。
自分の価値観を大切にする
――活動を通じて、先生が目指していることを教えてください。
賀:全ての医師・医学生が、自身の価値観や興味・関心に基づいて将来を選択できるようにするためのサポートをしたい、と思っています。そのためにはまず、自身が本当に大切に思っていることは何なのかを明らかにし、研修病院や勤務先でどんな働き方ができるか情報収集をして、目指す医師像に近づく道を選んでいくという一連の流れを、医師・医学生にもできるようになってもらいたいのです。現在は、キャリア・デベロップメント・アドバイザーの資格も取得し、ノウハウを教えるというよりは、キャリアカウンセラー的に関わっています。
「選択できる」ということ
――近年では男女問わず、自分や家庭の時間を大切にしながら働きたいという価値観をもった医学生や研修医も増えてきているように感じます。
賀:そうですね。私自身も医師として働くなかで、実は「自身が本当はどんな風に仕事をしたいのか」はわかっているのに、職場の「暗黙のルール」によって望まない働き方を選択してしまうことも多いのではないか、と思うようになりました。そういう風に、本当は家庭での時間を大切にしたいと思っているのに、勤務先での評価を気にして長時間勤務を続けてしまうというような人も少なくないのが現実ではないかと思います。
医師の世界全体として、技量を上げるのが最優先、長時間勤務も当たり前…という価値観が、長い間「暗黙のルール」となっていたように感じます。それも一つの価値観ですから、「長時間勤務は絶対にいけない」と考えているわけではありません。問題はそれが明文化されていないことだと思うんです。
――説明会等でワーク・ライフ・バランスに関する制度について説明を受けても、実際に利用できる雰囲気かどうかは入職してみないとわからないという声も聞かれますね。
賀:今後、医師・研修医が自身の価値観に合った病院を選択できるようにするためには、各病院の客観的なデータの公表が必要だと思います。例えば、後期研修中に妊娠・出産した人数と、その後研修を終わらせた人数、離脱した人数などをデータ化し、これを公表している病院が評価されるような仕組みができれば、状況は変わってくるのではないでしょうか。
研究で制度運用を改善したい
――先生も家庭を大事にするという、ご自身の価値観を尊重した働き方をしているんですね。
賀:はい。もともと「男性も料理や洗濯をする方がモテる」という家庭で育ったこともあって(笑)、生活を仕事だけでいっぱいにしてしまうのはバランスが悪く、満足できないと感じていました。ですから、妻とフラットな関係で家事・育児を分担できる勤務先を選びました。
――今後は、医師のキャリア形成支援の分野でどのようなアプローチをしていきたいと考えていますか?
賀:様々な場でレクチャーやワークショップを続けると同時に、研究を通じて制度やその運用にもアプローチしていきたいと考えています。例えば現在は、地域枠入試制度が地域医療体制の維持に有用であるかどうか、学生へのインタビューを通して調査する研究を行っています。地域枠入試は、その制度運用にはまだ一貫性がなく、地域枠を利用している学生や研修医にとって曖昧な制約になっている場合も少なくありません。例えば、専門医志向になりつつあるのに、地域枠で入学し、地域医療に終身従事することを望まれているのではないかというプレッシャーから、へき地勤務に身を投じてしまう…といったように、ルールが曖昧であるがゆえにキャリアに苦悩したり、不必要なプレッシャーを受けたりすることがないようにしたい。研究を行うことで、地域枠入試制度とその運用がより良くなる手助けとなればと考えています。
社会医療法人清風会
岡山家庭医療センター
2000年岡山大学院薬学研究科薬学専攻修了。2008年旭川医科大学卒業。千葉県での後期研修中に、夫人が妊娠。夫婦ともに医師として働き続けられる環境を探し、岡山家庭医療センターに移籍。同時期に、厚生労働省の指定するキャリア・コンサルタント資格であるキャリア・デベロップメント・アドバイザーの資格取得。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:賀來 敦先生
- Information:Winter, 2016
- 特集:医の倫理 患者とともに悩み、考える
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う
- 同世代のリアリティー:MRと医師の関係 編
- チーム医療のパートナー:臨床研究コーディネーター
- チーム医療のパートナー:認定遺伝カウンセラー
- NEED TO KNOW:知っていますか? 矯正医官
- 地域医療ルポ:東京都町田市|西嶋医院 西嶋 公子先生
- 10年目のカルテ:血液内科 細羽 桜医師
- 10年目のカルテ:腫瘍内科 金政 佑典医師
- 日本医師会の取り組み:医療保険・介護保険
- 医師の働き方を考える:「この仕事が好き」と思えることが大事
- 医学教育の展望:専門医の効率的な資格取得を支援する
- Cytokine:集まれ、医学生!
- 大学紹介:防衛医科大学校
- 大学紹介:東邦大学
- 大学紹介:大阪医科大学
- 大学紹介:徳島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:峯 昌啓×阪田 武

