「この仕事が好き」と思えることが大事
~脳神経外科医 加藤 庸子先生~(前編)
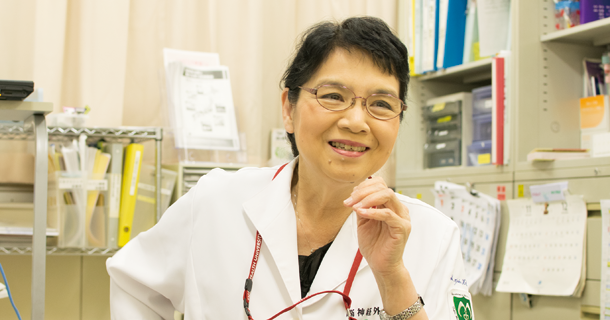
即決で脳外科を選び、没頭
村岡(以下、村):まず、先生が脳外科を選ばれたのは、どういう経緯だったのでしょうか?
加藤(以下、加):教授に声をかけていただいたのがきっかけでした。私は学生の頃、休みがあるたびにいろんな医局に出入りしていました。婦人科や泌尿器科の医局にも顔を出していたんですが、脳外科の教授が、私に「君いいね、入らないか?」と言ってくださったんです。父が外科医だったということもあって、興味はありましたし、その場で入局を決めました。
村:当時の医局は、女性は少なかったのではありませんか?
加:少なかったですね。私が先生に見込まれたのは、健康そうに見えたのも大きいのではないかと思っています。医師のなかでも外科系は、やはり体力が必要ですからね。
入局してからは、他の研修医と手術の担当を奪いあうようにしながら、貪欲に技術を磨きました。とにかく仕事が楽しかったし、腕を上げたかったんです。
村:先生は現在まで独身でいらっしゃいますが、結婚は考えなかったのですか?
加:昔は、28歳になったら結婚したいと思っていました。けれど、人生なかなか思う通りにはいかないですね。そのぐらいの年頃って、学位や専門医資格を取ったり、留学をしたりする時期でもあるし、徐々に患者さんも定着してきて、仕事がますます楽しくなって、いつしか機を失った、という感じでした。
村:まずは臨床研修、その後に専門医…という流れができて、男女問わず、結婚する時期が難しくなってきましたよね。
加:ええ、そう思います。特に女性医師は、ちょうど自分が医師として伸びる時期と、結婚して子どもを産むタイミングが重なりがちです。そこをどう解決するかは、難しい問題だと思います。とはいえやっぱり私は、若い先生方には是非結婚してほしいなと思っていますよ。
ざっくばらんに語り合える会
村:先生は1991年に日本脳神経外科女医会を発足させていますね。やはり、脳外科で女性医師が仕事をしていくうえで、女性同士での話し合いが必要だったのでしょうか。
加:いえ、そんな大げさなものじゃないんですよ。アメリカで脳外科の女医会が結成されて、日本から代表として一人訪問しなければならなくなったんです。そこで一番年長だった私が、当時20名ほどだった女性専門医の先生方の意見を集約してアメリカに届けました。結局そのとき意見を出してくださった先生方が、今の女医会の土台となったんです。現在は脳外科の女性専門医も500名ほどに増え、そのうち6割はこの会に入っています。
村:具体的にどのような活動をしていらっしゃるんですか?
加:みんなで集まって、ざっくばらんに経験談をシェアする会を、年に2回ほど行っています。片肘をついてでも、寝転がってでもいいから、気軽に本音を話せるような場を目指しています。
村:いいですね。自分だけが悩んでいるのではないとわかったら、勇気が出ますからね。
加:現在は、勤務している坂文種報德會病院でも「医学生・若手研修医 先輩とのTalk会」と題して、先輩医師と研修医、医学生の交流の機会を設けています。講演会だと、だいぶ上の人の話を聴く場合が多くなってしまうじゃないですか。そうではなくて、自分よりもちょっと上の年代の先輩と、気軽にやりとりできるような環境を作っています。
「この仕事が好き」と思えることが大事
~脳神経外科医 加藤 庸子先生~(前編)
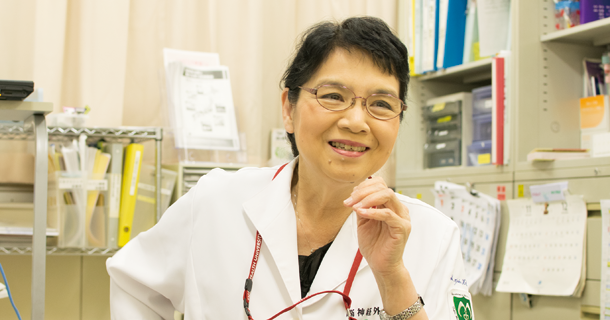
即決で脳外科を選び、没頭
村岡(以下、村):まず、先生が脳外科を選ばれたのは、どういう経緯だったのでしょうか?
加藤(以下、加):教授に声をかけていただいたのがきっかけでした。私は学生の頃、休みがあるたびにいろんな医局に出入りしていました。婦人科や泌尿器科の医局にも顔を出していたんですが、脳外科の教授が、私に「君いいね、入らないか?」と言ってくださったんです。父が外科医だったということもあって、興味はありましたし、その場で入局を決めました。
村:当時の医局は、女性は少なかったのではありませんか?
加:少なかったですね。私が先生に見込まれたのは、健康そうに見えたのも大きいのではないかと思っています。医師のなかでも外科系は、やはり体力が必要ですからね。
入局してからは、他の研修医と手術の担当を奪いあうようにしながら、貪欲に技術を磨きました。とにかく仕事が楽しかったし、腕を上げたかったんです。
村:先生は現在まで独身でいらっしゃいますが、結婚は考えなかったのですか?
加:昔は、28歳になったら結婚したいと思っていました。けれど、人生なかなか思う通りにはいかないですね。そのぐらいの年頃って、学位や専門医資格を取ったり、留学をしたりする時期でもあるし、徐々に患者さんも定着してきて、仕事がますます楽しくなって、いつしか機を失った、という感じでした。
村:まずは臨床研修、その後に専門医…という流れができて、男女問わず、結婚する時期が難しくなってきましたよね。
加:ええ、そう思います。特に女性医師は、ちょうど自分が医師として伸びる時期と、結婚して子どもを産むタイミングが重なりがちです。そこをどう解決するかは、難しい問題だと思います。とはいえやっぱり私は、若い先生方には是非結婚してほしいなと思っていますよ。
ざっくばらんに語り合える会
村:先生は1991年に日本脳神経外科女医会を発足させていますね。やはり、脳外科で女性医師が仕事をしていくうえで、女性同士での話し合いが必要だったのでしょうか。
加:いえ、そんな大げさなものじゃないんですよ。アメリカで脳外科の女医会が結成されて、日本から代表として一人訪問しなければならなくなったんです。そこで一番年長だった私が、当時20名ほどだった女性専門医の先生方の意見を集約してアメリカに届けました。結局そのとき意見を出してくださった先生方が、今の女医会の土台となったんです。現在は脳外科の女性専門医も500名ほどに増え、そのうち6割はこの会に入っています。
村:具体的にどのような活動をしていらっしゃるんですか?
加:みんなで集まって、ざっくばらんに経験談をシェアする会を、年に2回ほど行っています。片肘をついてでも、寝転がってでもいいから、気軽に本音を話せるような場を目指しています。
村:いいですね。自分だけが悩んでいるのではないとわかったら、勇気が出ますからね。
加:現在は、勤務している坂文種報德會病院でも「医学生・若手研修医 先輩とのTalk会」と題して、先輩医師と研修医、医学生
「この仕事が好き」と思えることが大事
~脳神経外科医 加藤 庸子先生~(後編)
ぶつかったら環境を変えて
村:教授として大学にいらっしゃると、外科系を志す女子学生から相談を受けることもありますか? 自分も外科でやっていけるのだろうか、とか。
加:そうですね、よく聞かれます。そういう時の私の答えは、とにかく自分が好きなことをやりなさいということ。その診療科が好きじゃないと、一生ものにはなりませんからね。そしてもうひとつ、もし難しい環境にぶち当たることがあったら、思い切って環境を変えてみること。海外留学でも国内留学でもいいんですけど、少し違う社会を見てみることを勧めています。
村:先生ご自身も、何度か留学していらっしゃいますね。
加:ええ。卒後4年目に中国に、33歳でオーストラリアに留学したのですが、そのときの経験は人生に影響を与えていると思います。それからもいろんな国の医療を視察したり、積極的に留学生を受け入れたりしています。海外の医療のあり方や、留学生の様子を見ていると、日本も柔軟に他国の良い部分を受け入れる姿勢を持たないとな、と思わされますね。
女性でも働きやすい外科系に
村:海外の働き方やライフスタイルの良いところを取り入れたら、外科系でも女性が働きやすくなるでしょうか。
加:例えば日本では、一人の主治医が最初から最後まで手術を担当するけれど、ヨーロッパでは、主治医が複数いて、術中に心臓マッサージをしていても、17時になったら別の先生がやってきて交代するのが当たり前という国もあります。日本ではそういうことを認めない空気もあるけれど、そういうおおらかさがある社会になっていけば、もっと働きやすくなるのではないかと思います。他にも、曜日交代で外来を担当するようにすることもできると思うし、子どもの面倒を見てくれるボランティアさんを町内で募ることもできるのではないかと。今後、そういった柔軟な支援策を取り入れていくのが重要なのではないかと私は考えているんです。
村:最後に、これから医師を目指す医学生、特に女子医学生に一言あればお願いします。
加:よく、学生さんたちは随分先のことを心配している印象を受けますけど、あまり先のことを考えても仕方ないんじゃないかなと私は思います。私自身もそうでしたが、歳をとるにつれて周りの環境も、自分の気持ちも変わっていくものです。数年の間にも、思ってもみないことが起こるかもしれないし、思いがけないチャンスが巡ってくるかもしれない。そういうチャンスが来たら迷わず挑戦してほしいですね。きっちり将来を設計しても、その通りにいかないのが人生ですよ。だから、その時自分が置かれた環境で、好きだと思える仕事を一所懸命やるしかないんじゃないかと私は思います。もし誰かがその姿を見ていてくれれば、自ずと道が開けてくるはずですよ。

語り手
加藤 庸子先生
藤田保健衛生大学 坂文種報德會病院
脳血管ストロークセンター センター長
藤田保健衛生大学 医学部 脳神経外科 教授
聞き手
村岡 真理先生
村岡整形外科クリニック 副院長
日本医師会 女性医師支援委員会 委員
青森県医師会 男女共同参画委員会 委員



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:賀來 敦先生
- Information:Winter, 2016
- 特集:医の倫理 患者とともに悩み、考える
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う
- 同世代のリアリティー:MRと医師の関係 編
- チーム医療のパートナー:臨床研究コーディネーター
- チーム医療のパートナー:認定遺伝カウンセラー
- NEED TO KNOW:知っていますか? 矯正医官
- 地域医療ルポ:東京都町田市|西嶋医院 西嶋 公子先生
- 10年目のカルテ:血液内科 細羽 桜医師
- 10年目のカルテ:腫瘍内科 金政 佑典医師
- 日本医師会の取り組み:医療保険・介護保険
- 医師の働き方を考える:「この仕事が好き」と思えることが大事
- 医学教育の展望:専門医の効率的な資格取得を支援する
- Cytokine:集まれ、医学生!
- 大学紹介:防衛医科大学校
- 大学紹介:東邦大学
- 大学紹介:大阪医科大学
- 大学紹介:徳島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:峯 昌啓×阪田 武

