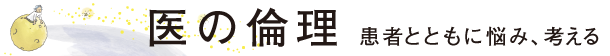
医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う(前編)
様々な葛藤にさらされる現代の医師は、患者とともに、どのように倫理的な問題に向き合っていけば良いのでしょうか。
ケースバイケースで判断する
医学も医療も発展を続けており、少し前にはできなかったこともどんどん技術的に可能になっていきます。妊娠の初期段階で遺伝性疾患の有無を知ることができる検査、植物状態や脳死状態を作り出す生命維持装置――、このような高度な医療技術を使える現代の医師、そして患者は、様々な難しい意思決定を迫られます。
倫理的な規範には解釈の幅があり、ケースバイケースで判断せざるを得ず、決まった答えが出ないことも多いものです。そんななかで最善の選択を行うために、医師と患者はどのように考えていけばよいのでしょうか。この特集の最後に、治療に関する意思決定と、医師と患者の関係のあり方について考えてみましょう。
「先生に全てお任せします」から患者自身が自己決定する時代へ
医師・患者関係については、長きにわたって、ヒポクラテスの主張に代表されるような「医師は医療に関する専門家であるのに対し、患者は素人である」「医師は慈善行為として医療を行い、患者を我が子のように思って接するべきだ」といった考え方が一般的でした。具体的には『ヒポクラテス全集』に、「(患者には)これから起こる事態や現在ある状況は何一つ明かしてはならない」「素人には、いついかなるときも何事につけ、決して決定権を与えてはならない」などの記述があります*1。20世紀半ばまでは、これらが医師のあるべき姿として尊重されてきました。
しかしこのような考え方は、次第にパターナリズム*2的であるとして批判を受けることになります。第二次大戦後、欧米を中心に市民の医学・医療への関心が高まり、患者と医師が対等な関係を築くこと、そして患者の人権の擁護や自由意志に基づく同意が重視されるようになりました。そして、米国の病院協会が編纂した「患者の権利章典」(1973)では「インフォームド・コンセント」や「情報公開」が謳われ、米国医師会の倫理綱領(1980、1993、2001)には患者の権利についての項目が明示されるなどの変化が起きました。
この考え方は日本にも輸入されます。1990年に日本医師会の生命倫理懇談会が提出した「『医師に求められる社会的責任』についての報告」では、インフォームド・コンセントを「説明と同意」と表現し、日本でも導入すべきであると提言しています。1998年には医療法が改正され、医師は「医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と定められました。それまで「先生に全てお任せします」が当たり前だったものが、「情報提供に基づき、患者が自ら受ける医療を決める」方向に舵が切られたのです。

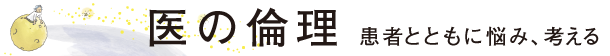
医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う(後編)
医師・患者関係の多様性
この医師・患者関係のあり方について、代表的なモデルの一つ(エマニュエルらのモデル*3)に沿って考えてみます。このモデルでは、医師・患者関係を、パターナリズムモデル・情報提供モデル・解釈モデル・審議モデルの4つに分類しています。
パターナリズムモデルは、医師の判断に基づく意思決定が、患者の最大の利益につながるという前提に立っています。治療に関する判断は医師に任せられ、ときに医師が患者の価値観を無視することも起こりえます。しかしそれが常に不適切なわけではなく、救急医療など一刻を争う場面では医師に決定が委ねられることもあるでしょう。
対照的に情報提供モデルでは、治療に関する選択を患者に任せます。患者は「医療というサービス」の消費者として捉えられ、医師の役割は、治療に関する医学的事実を患者に提供することとされます。
先の2つのモデルが医師・患者いずれかに判断を委ねているのとは対照的に、解釈モデルと審議モデルは、医師と患者の対話を重視しています。解釈モデルでは、医師は自らの意見は表明せず、患者の考えを整理することに徹するのに対し、審議モデルでは、医師は自身の意見も主張し、ときに説得的に患者に関わります。
患者とともに悩み、考える
どのモデルが正しい、という答えはもちろんありません。しかし実際の臨床では、医師だけで決める、患者だけで決める、といった場面は少なく、それぞれが考えや思いを持って対話するなかで、少しずつ方針が決められているはずです。
倫理的な葛藤に関して、法律も、様々な規範も、医学的なエビデンスも、先人の知恵も、間違いではない「範囲」を示すだけであり、明確な答えを示してくれるものではありません。患者も医師も、その葛藤を前に、「正解かどうかわからない選択肢」を選び、引き受けていくしかないのです。それはとても重く、大変なことでしょう。
だからこそ患者は医師に、知識や医学的な情報を提供することだけでなく、それを踏まえて、「ともに悩み考え続ける」ことを期待しているのではないでしょうか。

*1…大槻真一郎訳(1985)『ヒポクラテス全集』エンタプライズ
*2…パターナリズム:ギリシャ・ローマ語における『父親』の意に由来する言葉であり、『親が子を守るような保護主義』を指している。善意に基づくものであっても、庇護される側の自己決定権が侵害されるとして批判的な意味で使われることが多い。
*3…赤林朗(編)(2008)『入門・医療倫理』勁草書房



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:賀來 敦先生
- Information:Winter, 2016
- 特集:医の倫理 患者とともに悩み、考える
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う
- 同世代のリアリティー:MRと医師の関係 編
- チーム医療のパートナー:臨床研究コーディネーター
- チーム医療のパートナー:認定遺伝カウンセラー
- NEED TO KNOW:知っていますか? 矯正医官
- 地域医療ルポ:東京都町田市|西嶋医院 西嶋 公子先生
- 10年目のカルテ:血液内科 細羽 桜医師
- 10年目のカルテ:腫瘍内科 金政 佑典医師
- 日本医師会の取り組み:医療保険・介護保険
- 医師の働き方を考える:「この仕事が好き」と思えることが大事
- 医学教育の展望:専門医の効率的な資格取得を支援する
- Cytokine:集まれ、医学生!
- 大学紹介:防衛医科大学校
- 大学紹介:東邦大学
- 大学紹介:大阪医科大学
- 大学紹介:徳島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:峯 昌啓×阪田 武

