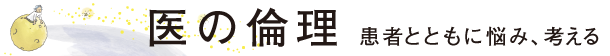
終末期医療にまつわる倫理的な問題(前編)
延命治療や安楽死・尊厳死に関わる議論や論点を見てみましょう。
ヒポクラテスの誓いと安楽死の禁止
「死の近づいた患者にまつわる二つのケースを見てきました。医学・医療の進歩によって、数十年前には助からなかったような患者も、生命を存続させることが可能になってきています。しかしそのことが、終末期医療を取り巻く状況をより複雑にしているのも事実です。
古代ギリシャの「ヒポクラテスの誓い」まで遡ると、医師は患者にはいかなる危害も加えないこと、求められても致死薬の投与はしないことが定められています。患者が少しでも生きながらえる可能性があれば、延命治療に尽くすのは当然のことであり、患者の死に手を貸すなどというのはもってのほか、というのがその思想でした*1。
幕末に緒方洪庵らが訳した『フーへランドの医戒』でも、「およそ人の生命をちぢめるようなことは、医師たるものは誓ってこれをなすべきでない」と述べられています。一方で、「不治の病を得て、苦悩するものが、自分から死を願う」ことがあっても、その患者を「一刻も早く、苦悩からのがれさせ」ようとすることは、「たいへん道理があるようではあるが(略)『偽言』」であり、「罰せられるべき」という記述も残されています*2。
ただし、16~17世紀のイギリスの思想家ベーコンは、不治の病で苦しんでいる人の生命を縮めるのも医師の仕事であるとして、これをeuthanasia(安楽死)と呼びました。しかし、これは殺人行為であり、医師としては賛成するわけにはいきません。
しかし、市民のなかには安楽死を希望する人も多く、20世紀になると、アメリカやイギリスで安楽死を法律で認めさせようとする社会運動が起こりました。1937年には、アメリカにおいて「アメリカ安楽死協会」が設立されます。両国では何度か法案も提出されましたが、いずれも成立には至りませんでした。
安楽死から尊厳死へ
医療技術の発達・普及に伴って、この問題は新たな局面を迎えます。1960年代になると、人工呼吸器の普及によって、回復の見込みがないにもかかわらず延命治療を続けられている患者が目立つようになったのです。「このような患者に対する延命治療は無駄であり、また患者の人間としての尊厳を毀損するもので中止すべきである」という考え(尊厳死)が出てきました。これは、人工呼吸器の取り外しだけでなく、ケース4のTさんのような遷延性意識障害の患者の栄養停止にも及んでいきます。
この頃のアメリカでは、患者の自己決定権を尊重する動きが起こっていたこともあり、本人の意思に基づき延命治療の中止を認めるべきであるという考えが生まれます。しかし、尊厳死が問題になるような状況においては、患者はすでに意識を失っていると考えられるため、正常な判断能力がある時点であらかじめ自分の意思を文書として残しておこう、という流れも出てきました。このような文書は「リビング・ウィル」「アドバンス・ウィル」などと呼ばれています。
1974年には「アメリカ安楽死協会」は「死ぬ権利協会」と改名し、リビング・ウィルに関する署名活動を活発化させました。1976年には、ニュージャージー州で昏睡状態となって人工呼吸器につながれていた若い女性患者に対して、裁判所が人工呼吸器の取り外しを容認する判決を出し、注目が集まりました(カレン・クィンラン事件)。その後アメリカの各州は、このような患者の延命中止を容認する法律、自然死法を成立させます。

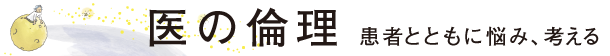
終末期医療にまつわる倫理的な問題(後編)
末期患者をめぐる日本での議論
回復の見込みのない患者に対する延命処置を続けることは止めてもよい、むしろ患者の生活の質(QOL)を重んじたケア(ターミナルケア)をすべきであるという考えが、日本でも次第に強くなっていきました*1。1992年、日本医師会・生命倫理懇談会は「『末期医療に臨む医師の在り方』についての報告書」で、回復する見込みのない重症の末期患者に対しての治療の差し控えや中止を容認する見解を示し、厚生省(当時)もこれを追認するようになりました。2007年には厚生労働省が「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を発表し、終末期医療及びケアのあり方とその方針の決定手続きについて掲載しています。このガイドラインでは、基本的には患者本人の意思の尊重を最優先に掲げていますが、患者の意思が不明な場合、また患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて、医療チームは家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする、と示しています。
尊厳死・安楽死についてどう考えるか
日本には、尊厳死や安楽死を認める法律はありません。2012年、超党派の議員連盟が「尊厳死法案*3」を公表しましたが、すでにわが国では不治の患者の延命治療の中止については国民的合意があり、前述の厚生労働省のガイドラインに従えば問題はないということもあって、法制化には至っていません。
積極的安楽死については現在、世界の数か国が法律でこれを認めています。日本における過去の判例をみてみると、1962年の名古屋高等裁判所の判決は、現行の法律のもとでも、一定の条件を満たせば安楽死は容認できると示し、注目されました。1995年の横浜地方裁判所の判決でも、特定の要件を満たせば積極的安楽死は容認できるとされています。
とはいえ医師にとって、患者を死に至らしめるという行為は容認しえないことで、日本医師会も、積極的安楽死には反対の態度をとっています。目の前に死を希求する不治の患者やその家族がいたとき、医師としてどのような判断を下すべきなのかは、過去の判例はもちろん、目の前の患者・家族の意思や様々なガイドラインを参照しながら、常に考え続けなければなりません。
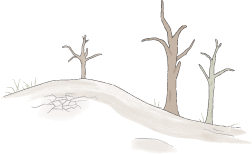
*1…森岡恭彦(2010)『医の倫理と法 その基礎知識 改訂第2版』南江堂
*2…杉本つとむ(1992)『江戸蘭方医からのメッセージ』ぺりかん社
*3…「尊厳死法制化を考える議員連盟」による「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」

監修:森岡 恭彦先生
日本赤十字社医療センター 名誉院長
東京大学 名誉教授/自治医科大学 名誉教授/
元日本医師会副会長



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:賀來 敦先生
- Information:Winter, 2016
- 特集:医の倫理 患者とともに悩み、考える
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:生殖医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題 casestudy
- 特集:終末期医療にまつわる倫理的な問題
- 特集:医師と患者がともに倫理的葛藤に向き合う
- 同世代のリアリティー:MRと医師の関係 編
- チーム医療のパートナー:臨床研究コーディネーター
- チーム医療のパートナー:認定遺伝カウンセラー
- NEED TO KNOW:知っていますか? 矯正医官
- 地域医療ルポ:東京都町田市|西嶋医院 西嶋 公子先生
- 10年目のカルテ:血液内科 細羽 桜医師
- 10年目のカルテ:腫瘍内科 金政 佑典医師
- 日本医師会の取り組み:医療保険・介護保険
- 医師の働き方を考える:「この仕事が好き」と思えることが大事
- 医学教育の展望:専門医の効率的な資格取得を支援する
- Cytokine:集まれ、医学生!
- 大学紹介:防衛医科大学校
- 大学紹介:東邦大学
- 大学紹介:大阪医科大学
- 大学紹介:徳島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- FACE to FACE:峯 昌啓×阪田 武

