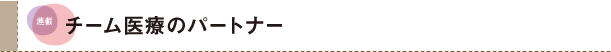
障害者就労移行支援(前編)
就労移行支援とは
――就労移行支援とはどういった仕事ですか?
猪井(以下、猪):就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。
労働基準法に基づいて勤務先企業と雇用契約書を交わして働く一般的な就労形態を一般就労、そのような働き方が難しい場合などに福祉サービスを受けながら働く働き方を福祉的就労といいます。私たちは、障害があり一般就労を希望している方を対象に、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行っています。
具体的な支援の過程は、まず職種や就職先に求める条件など、利用者さんの希望を伺います。次に就職活動の準備として、生活リズムを整えながら就職の知識やスキルアップのための講座に参加していただき、さらに実際の企業で様々な職種や職場を体験してもらいます。そして就職活動の際は、応募や面接のサポートも行います。就職後は、定期的に職場訪問してご本人や職場の担当者から状況を伺うなど、就労定着支援を行います。
米須(以下、米):一般就労の中にも一般雇用と障害者雇用があります。一般雇用では、障害があることを開示して働く場合もあれば、障害者手帳の所持や通院歴を非開示で就職する場合もあります。障害者雇用は、一般企業の中で障害者雇用で働く場合と、特例子会社という障害のある方の雇用の促進と安定を図るために設立された会社で働く場合があります。
私たちは利用者さん個人の障害特性を念頭に置いて、何が向いているかをご本人と共に考え、特性に合う業務や環境のある企業を探します。一方、利用者さんが障害特性に自己対処できる方法がないかも一緒に考えていきます。就労移行は我々と利用者さんとの共同作業ともいえます。
――利用者さんがサービスを利用されるきっかけや利用条件などについて教えてください。
猪:一番多いのは、働くことに難しさを感じて自分で検索して弊社にたどり着いたというケースです。ここに来てから専門的な見解を確認するため、初めて医療機関にかかる方もいます。
退院した方をソーシャルワーカーや地域の保健師さんから紹介してもらう場合もあります。
米:弊社の利用には、原則、主治医の意見書が必要です。主治医意見書には、一般就労でどれくらいの時間働けるのか、どういった配慮が必要か、などが記載されています。また通院に同行して現状の障害特性や症状など、医師の意見を直接聴くこともあります。
体調の安定を優先させて福祉的就労につないだり、場合によっては医療機関のデイケアや自立訓練といった福祉サービスへつないだりというケースもあります。就労移行支援の利用にならなかったとしても、必ず適切な社会資源の情報提供を行うようにしています。
――利用者さんへの直接の支援のほかには、どのような業務がありますか?
米:利用者さんの受け入れ先である企業との話し合いや、就職先や実習先の新規開拓などがあります。
企業からの問い合わせにも対応します。障害者雇用の方法についての問い合わせへの助言や、障害者を受け入れるにあたっての環境調整の必要性の説明などを行っています。
――スタッフにはどのような方が多いのでしょうか?
猪:福祉系の資格をもつサービス管理責任者のほか、職業指導員、生活支援員、就労支援員によって構成されています。一般就労を目指す場なので、福祉だけではなく一般企業に関する知識も求められます。そのため、社員には多種多様な業界の経験者がいます。


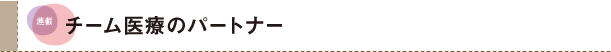
障害者就労移行支援(後編)
企業の合理的配慮
――就労定着支援や企業への働き掛けについて教えてください。
猪:就労定着支援においては、企業へ合理的配慮の要請を行います。合理的配慮とは、障害のある人が他の人とお互いに平等・公正に支え合い、共に活躍するための調整を行うことです。具体的には、どうやって本人のスキルを高めていけばいいか、今ある強みがより活かされるように環境調整でご協力いただけないかなどを確認します。例えば、聴覚過敏で周りが気になってしまう人の席を移動する、指示をマークにして誰にでもわかりやすくするなどが挙げられます。合理的配慮の提供は企業の努力義務ですが、企業側もどこまで対応したら良いのか迷うところなので、我々が介入して調整役を果たすこともあります。
企業側も、実際に雇い入れていくなかで、障害者と自分たちに大きな隔たりはなく、地続きの存在なのだと理解されていくようです。
米:就労定着支援は最長でも3年です。私たちがいなくなる前提の支援をしていくため、企業と利用者さん本人が直接オープンに話をして、必要な配慮を話し合いで決められるような状態を作っていくことが大事です。私たちを介さなくてもきちんとコミュニケーションが取れる状態をいかに早く作っていくかという「引いていく支援」を目指しています。
安心できる場として
――業務のうえで大切にしていることや、やりがいは何ですか?
米:弊社では「障害は本人ではなく社会の側にある」と考えています。利用者さんの多くは自分の特性と環境との不適合に悩んだり傷ついたりした経験があるため、まずは自己肯定感の下がってしまった方々のケアの場でありたいと考えています。訓練においては、座学プログラムや模擬業務を通して自己理解を深め、また支援員やほかの利用者さんとの会話を通して、コミュニケーションを学ぶ機会も提供させていただいています。具体的な就労ノウハウの提供だけでなく、安心感や帰属意識が持てるようなコミュニティでありたいと思っています。
猪:弊社としては、社会に出て行くにあたっての自信につながるよう、利用者さんに「できた」「楽しい」と思ってもらうことを大事にしています。一方で、本当の意味での夢や目標を一緒に見付けるためには、利用者さんとはポジティブなものだけでなく、様々な葛藤といったネガティブな感情も共有していきたいとも思っています。
今の時代、同じ会社でずっと働き続ける以外の選択肢もあります。一つの企業での勤務が軌道に乗り本人の自信もついたら、より選択肢が広がるようスキルアップをするなど、本人の希望を踏まえたうえで、今後、何ができるかを共に考えていけることも、この仕事の醍醐味ですね。
――最後に、これから医師になる医学生へメッセージをお願いします。
米:服薬など医学的なアプローチと、こちらの社会的なアプローチとのバランスが取れるように、支援機関との連携を歓迎してもらえると嬉しいです。医療の力を借りないと解決できない課題もあるため、そのようなときにはぜひ力を借りたいです。
現在、障害者雇用は非常に多様化しています。最新情報を共有し、共に利用者さんに適切な支援ができたらと願っています。
 米須 英明さん
米須 英明さん
LITALICOワークス
水道橋センター センター長
 猪井 志織さん
猪井 志織さん
LITALICOワークス
五反田センター
※取材:2021年11月
※取材対象者の所属は取材時のものです。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:根本 慎太郎先生
- Information:Winter, 2022
- 特集:予防接種を知る
- 特集:予防接種にまつわる歴史
- 特集:予防接種を支える仕組み
- 特集:日本の予防接種のこれから
- 同世代のリアリティー:獣医学生 編
- チーム医療のパートナー:障害者就労移行支援
- Blue Ocean:青森県|相馬 宇伸先生(弘前大学医学部附属病院)
- Blue Ocean:青森県|小玉 寛健先生(弘前大学医学部附属病院)
- 医師の働き方を考える:人々の命を救うため 現地のニーズに合わせた医療を提供する
- 日本医師会の取り組み:産業保健に関する日本医師会の取り組み
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医学生大募集!ドクタラーゼの取材に参加してみませんか?
- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE私とドクタラーゼ
- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE座談会
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:札幌医科大学「地域医療合同セミナー1」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- FACE to FACE:宮地 貴士 × 菅野 勇太

