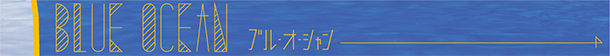
本連載は、医師不足地域で働く若手医師に、地域医療の最前線で働くことの魅力についてお尋ねするコーナーです。今回は青森県の弘前大学医学部附属病院の相馬宇伸先生と小玉寛健先生にお話を伺いました。

泌尿器科ならではの多様さで地域の患者さんを丁寧に診ていく
目標となる恩師との出会い
――弘前大学を卒業後に県外で臨床研修を受け、再び大学に戻られているのですね。
小玉(以下、小):はい。私は秋田県出身で、一般入試で弘前大学に入りました。隣県であることや、センター試験と二次試験の比率を考えると、自分の状況に一番合っている進学先でした。
臨床研修先には、宮城県内の病院を選びました。せっかくなら一度県外から青森を見つめ直してみようと考えました。
そして、後期研修のタイミングで弘前大に戻ってきました。科をまたいで同期や先輩、後輩がいるため気軽に相談でき、働きやすいことが、出身大学の大きな魅力だと感じています。
――泌尿器科を選ばれた理由は何でしょうか?
小:学生の頃は、泌尿器科は男性器を診る科というイメージしかありませんでした。それが覆されたのが、臨床実習で泌尿器科を回った時でした。ロボット手術や腎移植、内視鏡的治療や透析など、幅広い経験ができる診療科だということを実感し、非常に魅力を感じました。泌尿器科の先生方がフレンドリーであったことも覚えています。
臨床研修では、主に泌尿器科と外科を回りました。外科の先生方も素敵な先生が多かったのですが、なかでも泌尿器科の指導医だった女性の先生が、様々な手術はもちろん、病棟や外来、透析など、何でもテキパキと行っており、その姿がとても印象的でした。泌尿器科は「診断から治療まで」とよく言われますが、それを体現したような先生に出会えたことが、泌尿器科に進む決め手となりました。
研修中も弘前大学泌尿器科の先生と連絡を取っていたこともあり、母校に戻って泌尿器科へ入局しました。

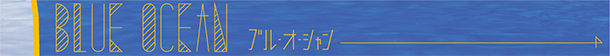
青森ならではの医療事情
―――これまで赴任した病院での経験などをお聴かせください。
小:後期研修1年目はまず大学病院に勤務しました。その後、鷹揚郷腎研究所弘前病院、青森市民病院、つがる総合病院、むつ総合病院と各地の中核病院を回り、手術や外来などの泌尿器科医としてのスキルを学びました。2020年10月から大学病院に戻り、現在はがん治療や移植医療に従事しています。各地で異なる診療を経験した今、最初の頃よりは大学病院でも役に立てていると感じます。
――市中病院では主にどのような症例を経験するのですか?
小:市中病院では、子どもから高齢者まで幅広い患者層を診療します。救急外来では尿路感染症の患者さんが多く、特に抗生剤の使用方法に関してはじっくり勉強する機会になりました。手術はがん手術が中心となりますが、りんご農家の方から「収穫の時期は避けてほしい」などと言われることも少なくありません。また、収穫が落ち着いた頃に遅れて検診結果を持ってくる方や、雪の多い冬場は通院が億劫になる方もいらっしゃいます。医師としてはもどかしく感じますが、患者さんの仕事や生活の状況を考えたうえで診療していくことが大切だと思っています。
市中病院は団結力があり、病院全体で「地域の患者さんを診ていこう」といった風土があります。泌尿器科は専門性が高いため、若いうちから他科の先生方の役に立てる点も魅力です。
――これまでで印象に残る患者さんはいらっしゃいますか?
小:泌尿器科は、外来などで症状の訴えを受け、診断・治療していく科なので、経過の長い患者さんもおられます。そういった患者さんからは外来に来た時に「先生、調子はどう?」と逆に気に掛けていただくこともあります。節度を保ちつつも、できるだけ親身に関わるように心掛けています。
――今後の展望をお聴かせください。
小:最近は移植に興味があり、今後は腎移植を専門にしていきたいと思っています。そのことを教授に話したら、「頑張ってください!」と後押ししてくださいました。また、当院消化器外科の出身で、現在は県外の病院の移植外科で部長としてご活躍の先生が大学に指導にいらっしゃった際に、その先生のところで勉強ができるよう、教授が話を通してくださいました。教授をはじめ先生方との出会いに感謝し、移植医療に貢献したいと思っています。
――青森県および医師不足の地域で働く利点はありますか?
小:青森県は広いため、異動の際の引っ越しは大変です。しかし、その地域ごとに異なる自然・文化・名産に触れ、味わうことができるのは、青森で働く面白さといえるでしょう。
医師が少ないこともあり、忙しい時期もありますが、その分自分の年次ではなかなかできない経験が積めるという点は、強みだと感じています。
――最後に、医学生にメッセージをお願いします。
小:私が泌尿器科を選んだのは臨床実習がきっかけでした。臨床実習を回っていると、ときには退屈に感じることもあるかもしれません。けれど、そこで扉を閉ざしてしまうと、面白さを発見する機会も断たれてしまいます。その診療科に進むかどうかに関わらず、できるだけ色々な先生方の話を聞いてみるなど、出会いを大切にしてほしいなと思います。


 小玉 寛健先生
小玉 寛健先生
2015年 弘前大学医学部卒業
弘前大学医学部附属病院 泌尿器科
※取材:2021年12月
※取材対象者の所属は取材時のものです。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:根本 慎太郎先生
- Information:Winter, 2022
- 特集:予防接種を知る
- 特集:予防接種にまつわる歴史
- 特集:予防接種を支える仕組み
- 特集:日本の予防接種のこれから
- 同世代のリアリティー:獣医学生 編
- チーム医療のパートナー:障害者就労移行支援
- Blue Ocean:青森県|相馬 宇伸先生(弘前大学医学部附属病院)
- Blue Ocean:青森県|小玉 寛健先生(弘前大学医学部附属病院)
- 医師の働き方を考える:人々の命を救うため 現地のニーズに合わせた医療を提供する
- 日本医師会の取り組み:産業保健に関する日本医師会の取り組み
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医学生大募集!ドクタラーゼの取材に参加してみませんか?
- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE私とドクタラーゼ
- 創刊10周年企画 これからのDOCTOR-ASE座談会
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:札幌医科大学「地域医療合同セミナー1」
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- FACE to FACE:宮地 貴士 × 菅野 勇太

