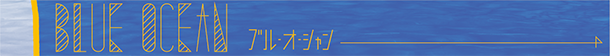
Blue Ocean
本連載は、医師不足地域で働く若手医師に、地域医療の最前線で働くことの魅力についてお尋ねするコーナーです。今回は秋田県の男鹿みなと市民病院に勤務する松本奈津美先生と、羽後町立羽後病院に勤務する阿部寛道先生にお話を伺いました。

人々と共に生き
長い継続性の中で診る医療に憧れて
Dr.コトーのような医療を
――松本先生が医師を目指した理由をお聞かせください。
松本(以下、松):子どもの頃にテレビドラマの「Dr.コトー診療所」を観て、離島医療や継続的な地域医療に憧れを抱いたことがきっかけです。
――臨床研修先はどちらに行かれたのですか?
松:大館市立総合病院です。まんべんなく症例を経験できそうな規模で雰囲気も良く、また離島研修や、都内の総合診療科の先生のもとで1か月研修できる制度などに惹かれました。
――専門研修での経験についてお聞かせください。
松:出身校である秋田大学の「アカデミック総合診療医育成プログラム」を選択し、卒後3年目は大学病院で内科と救急を回りました。綿密なカンファレンスやプレゼンをし、論文を読む経験を積むことができて、非常に意義深い1年だったと感じます。4年目は横手市の市立大森病院に赴任し、5年目の現在は男鹿みなと市民病院に勤務しています。週に1回、研修日として秋田大学に戻り、医局の先生方とカンファレンスをし、フィードバックを頂いています。
――印象に残っている患者さんはいますか?
松:初めて診たうつ病の患者さんです。小さなお子さんのいるシングルマザーでした。精神科は遠方にしかなく、家庭の事情でそこへの通院が困難だったため、私が診ることになりました。様々な人に相談しながら診るうち、少しずつ快方に向かい、最終的には職場復帰を果たされました。患者さんはとても強い方で、最終的には本人の力で回復されたと思います。私にできたのは「頑張りすぎないで」と声をかけて寄り添うことくらいでした。とはいえ、今後うつ病の患者さんにできることは広がったと思いますし、長い経過の中で徐々に回復していく姿を見られたのは嬉しい経験でした。
医師不足の地域ではどんな患者さんも診ることになると頭ではわかっていたものの、実際に様々な症例に出会うと戸惑うことばかりです。診ている最中は気を揉んでしまい、まるで余裕がありません。ただ、後から振り返れば良い経験だったと思うことも多く、精一杯やれば、患者さんにもそれが伝わることがわかり、自分なりに醍醐味を感じています。


総合診療科の特徴と魅力
――総合診療科のどのようなところに惹かれますか?
松:どのような患者さんも断らず、家族関係や社会的な要因も加味して全人的・継続的に診る点です。地域医療の現場ではどの科の先生も心がけていることだとは思いますが、総合診療科はその姿勢を本当に重視していると感じます。医局では上級医の先生に「患者さんの家族関係は?」「この情報をとってみたら?」といった助言を頂くことが多くあります。助言に従って試行錯誤を積み重ねた結果、患者さんとの関係が変わった例もあり、毎回目から鱗が落ちるような思いがします。
――将来の展望についてお聞かせください。
松:明確なキャリアプランはないのですが、診療所の経験は積んでみたいですね。外来だけで疾患をマネジメントする点に興味があります。そしていずれは一つの場所で診療したいと思っています。その土地の人々と共に生き、長い継続性の中で診る医療に憧れがあります。
また、今後は在宅医療にも注力したいです。私に見える範囲では、施設や在宅で看取る仕組みが不十分に感じるからです。入院先で看取るとなると、特に今のコロナ禍では面会制限があり、家族と満足に会えないまま最期を迎える患者さんも少なくありません。人々ができるだけ長く自宅で過ごせる仕組みの重要性を日々感じています。
オンオフの切り替えは明確に
――休日はどのように過ごしていますか?
松:赴任する先々で「お気に入りの店で食事をし、サウナや温泉に行く」などのルーティンを決め、定期的に楽しんでいます。今は近くに水族館があるので年間パスを買いました。休日を儀式化し、強制的に遊ぶことでオンとオフを切り替えています。
――最後に医学生へのメッセージをお願いします。
松:医師の仕事は体力勝負のところがあるため、学生時代から体力づくりをした方が良いと思います。また、精一杯遊び尽くしてほしいです。遊びの中で、自分の好みや効果的なリフレッシュ方法を知ることで、仕事で忙しい日々でも「これさえあれば自分は大丈夫」と思えるものを見出せると思います。
また、私は学生時代に高知の「Tシャツアート展」の滞在型ボランティアに参加し、当時の仲間と今も交流しています。こうした医療系以外の友人は貴重なので、学生時代に様々な人と出会うことをお勧めします。


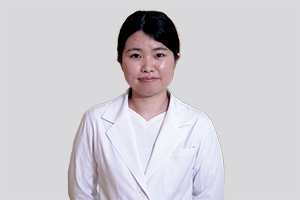
松本 奈津美先生
2018年 秋田大学卒業
男鹿みなと市民病院 内科
※取材:2022年10月
※取材対象者の所属は取材時のものです。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:軍神 正隆先生
- Information:Winter, 2023
- 特集:シリーズ 臨床研修後のキャリアⅡ そして医師人生は続く
- 特集:XX年目のカルテ 開業医:坂野 真理医師
- 特集:XX年目のカルテ 病院院長:三石 知左子医師
- 特集:XX年目のカルテ 大学教授:大塚 篤司医師
- 特集:XX年目のカルテ 大学教授:藤巻 高光医師
- 特集:これから長い医師人生を歩み始める皆さんへ
- チーム医療のパートナー:看護師長(病棟責任者)
- Blue Ocean:秋田県|松本 奈津美先生(男鹿みなと市民病院)
- Blue Ocean:秋田県|阿部 寛道先生(羽後町立羽後病院)
- 医師の働き方を考える:産婦人科医 柴田 綾子先生
- 日本医師会の取り組み:医学部卒後5年目まで会費減免期間を延長します
- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:大阪医科薬科大学「学生研究」
- 同世代のリアリティー:スポーツ科学研究者 編
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援
- 医学生の交流ひろば:MedYou Labo
- 医学生の交流ひろば:Dendrite
- 医学生の交流ひろば:鹿児島大学プライマリ・ケアサークル KAAN
- 医学生の交流ひろば:全国医学部ミニキャン&ご馳走の旅
- 医学生の交流ひろば:札幌医科大学 PQJ 2023 運営委員会
- 医学生の交流ひろば:医学生・医師が答えるみんなの疑問 Q&A
- 医学生の交流ひろば:医学生座談会~CBTを終えて~
- FACE to FACE:井上 敬貴×伊東 さら×ダン タン フイ

