大学紹介
島根大学
【教育】医の炎を燃やして地域から世界へ
島根大学 医学部長 大谷 浩
 島根大学医学部は、少子高齢化最先進県である島根県に立脚しており、日本のみならず世界における最先端の社会・医療ニーズに応えることが使命であるととらえて、教育・研究・臨床を一体として推し進めています。全ての入学生が心に「医の炎」を灯して生涯自己研鑚する医療人になれることを目標に掲げており、教員が教育熱心で学生との距離がとても近いことを、多くの学生が評価してくれています。
島根大学医学部は、少子高齢化最先進県である島根県に立脚しており、日本のみならず世界における最先端の社会・医療ニーズに応えることが使命であるととらえて、教育・研究・臨床を一体として推し進めています。全ての入学生が心に「医の炎」を灯して生涯自己研鑚する医療人になれることを目標に掲げており、教員が教育熱心で学生との距離がとても近いことを、多くの学生が評価してくれています。
地域医療実習では、県内約50の非常に協力的な病院・診療所との間に緊密なネットワークを築いています。県内各地域で活躍される先生たちの指導のもと、学生は患者さん、そして患者さんがお住まいの地域と密に関わり、多職種連携の現場で医療の原点を学ぶことができます。地域医療実習では、自由単位として1年次から様々なプログラムに参加でき、5年次にはいわゆる地域枠入学生のみならず全学生が2週間の実習を行い、また6年次にはより長期の実習も選択できます。
現在、日本の医学・医療が世界水準から取り残されつつあります。本学は、その大きな一因が、世界にアクセスできる英語力の欠如にあるとの強い危機意識から、医学英語教育を6年一貫で強化しています。地域から世界の最先端にアクセスして学び続け、また地域の患者さんから得た新知見を世界に広く発信できるようになるため、英語は必須の手段です。1~6年次まで、島根大学医学部英語学習支援室eクリニック(フェイスブックをご覧ください)にて展開する医学英語学習プログラムや多彩な海外研修を自由に組み合わせて履修し、自由単位を取得できます。また、研究マインドの醸成へ向けた自由単位「医学研究の基礎」などの取り組みは、国立大学医学部長会議のWEB(下記URL)への投稿をご覧ください。
URL: http://www.chnmsj.jp/kenkyuui_torikumi28.html
【研究】地域に根ざしたユニークな医学研究
島根大学 疾病予知予防プロジェクトセンター長 並河 徹
 島根大学では、学際的な研究組織としてプロジェクトセンターをいくつか立ち上げて地域貢献と先進的研究の両立を目指しています。疾病予知予防プロジェクトセンター(CoHRE:コアと呼びます)はその中の一つで、加齢性疾患、特に認知機能低下・運動機能低下・動脈硬化など、高齢者のQOL、健康寿命に関わる病態の予知予防に取り組む研究者のチームです。医学研究者のほか、社会科学の研究者が参加しており、遺伝的素因から生活習慣、地域コミュニティーの社会学的特性に至るまで、幅広い要因について健康調査に基づいたデータをもとに研究を進めています。すでにのべ6000件を越える調査データ、血液、DNAサンプルの収集を行っており、学際的研究でも社会科学研究者との共同研究で、地域コミュニティーでの信頼関係が住民の血圧に影響を与えることを明らかにするなどユニークな成果を挙げています。最近では、地理情報システム(GIS)を駆使して健康に関する地域特性の解析を進めており、自治体との共同研究、健康づくりに関わる共同事業なども展開しています。昨年度からは、地域中核病院や自治体とともに、Academic Knowledge Network (AKN)という仕組みを立ち上げました。これは、地域医療の現場で働いている医師・看護師・保健師・自治体政策担当者などが、日常業務の中から見つけた疑問やアイデアをもとに研究を実施するものです。研究の成果を実際の医療現場で役立てていただくと同時に、リサーチマインドを持つ地域医療のリーダーとして活躍していただくことを目標としており、大学の研究者は現場に出向いてその研究をサポートします。現在、実際に数人の方がこの仕組みで研究を開始しており、成果も出始めているところです。これからも、既存の大学の枠にとらわれず、地域に密着したユニークな研究を進めていきたいと考えています。
島根大学では、学際的な研究組織としてプロジェクトセンターをいくつか立ち上げて地域貢献と先進的研究の両立を目指しています。疾病予知予防プロジェクトセンター(CoHRE:コアと呼びます)はその中の一つで、加齢性疾患、特に認知機能低下・運動機能低下・動脈硬化など、高齢者のQOL、健康寿命に関わる病態の予知予防に取り組む研究者のチームです。医学研究者のほか、社会科学の研究者が参加しており、遺伝的素因から生活習慣、地域コミュニティーの社会学的特性に至るまで、幅広い要因について健康調査に基づいたデータをもとに研究を進めています。すでにのべ6000件を越える調査データ、血液、DNAサンプルの収集を行っており、学際的研究でも社会科学研究者との共同研究で、地域コミュニティーでの信頼関係が住民の血圧に影響を与えることを明らかにするなどユニークな成果を挙げています。最近では、地理情報システム(GIS)を駆使して健康に関する地域特性の解析を進めており、自治体との共同研究、健康づくりに関わる共同事業なども展開しています。昨年度からは、地域中核病院や自治体とともに、Academic Knowledge Network (AKN)という仕組みを立ち上げました。これは、地域医療の現場で働いている医師・看護師・保健師・自治体政策担当者などが、日常業務の中から見つけた疑問やアイデアをもとに研究を実施するものです。研究の成果を実際の医療現場で役立てていただくと同時に、リサーチマインドを持つ地域医療のリーダーとして活躍していただくことを目標としており、大学の研究者は現場に出向いてその研究をサポートします。現在、実際に数人の方がこの仕組みで研究を開始しており、成果も出始めているところです。これからも、既存の大学の枠にとらわれず、地域に密着したユニークな研究を進めていきたいと考えています。
【学生生活】主体的に学ぶ学生の背中を押してくれる環境
島根大学 医学部 4年 板倉 大輔
島根県で医学を学ぶ良さは、県全体がまさに地域医療の最前線であることにあると思います。大学には地域医療支援学講座などが中心となって地域医療を学ぶ体制が整っていますし、OB・OGには地域医療の第一線で活躍されている先生も多く、先生方の勉強会に学生として参加させてもらうことも多いです。
島根大での学びの目玉は、学生自ら実習内容と医療機関を決定して行うフレキシブル実習です。僕は高齢化率が約42%に達する県内の山間地域の病院で実習しました。医療・介護・福祉など様々な分野が連携し、高齢者の暮らしを地域全体で支える「地域包括ケア」の重要性が叫ばれていますが、大学で学ぶだけではその制度の実態がよく見えません。そこで僕は、地域包括ケア病床をもつ病院を実習先として選びました。2泊3日の実習を通して、これからの医師は病院で診療を行うだけでなく、多職種と連携して地域のマネジメントに携わっていかなければならないと感じました。
また島根大の特徴として医学英語の教育体制が充実している点が挙げられます。eステーションという英語学習教室では英語授業やワークショップが行われ、eラーニングの設備も完備されています。英語学習支援室eクリニックではTOEICのセミナーや医学英語の勉強会が通年で行われ、学生なら誰でも参加できます。また選択制のアドバンスト・イングリッシュスキルコースでは、鑑別診断や論文輪読を英語で行います。5年次以降にはタイ・メルボルン・ワシントンなどでの海外研修を、自身で企画・立案して行うことが可能です。医学部全体が学生の主体性を尊重し、それを強力にサポートする環境を整えてくれていると言えると思います。

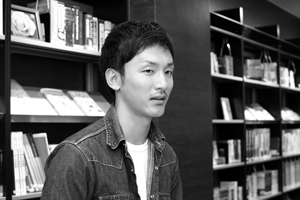
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
0853-23-2111



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:草場 鉄周先生
- Information:Autumn, 2015
- 特集:認知症があたりまえの時代
- 特集:目の前の人に向き合い、したいことを手助けする
- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ①認知症の人と関わるチームの姿
- 特集:ケース・スタディ 滋賀県東近江市永源寺地区 ②認知症の人の暮らしの実際
- 特集:ケース・スタディ 大分県由布市 認知症で困っている人に関わる
- 特集:人と人との関係が認知症の人を支える
- 特集:認知症と共生する社会へ 経済界・企業トップ×日本医師会役員対談
- 同世代のリアリティー:大学生のレンアイ事情 編
- チーム医療のパートナー:患者支援団体
- チーム医療のパートナー:患者家族
- 10年目のカルテ:放射線科 奥田 花江医師
- 10年目のカルテ:放射線科 永井 愛子医師
- 日本医師会の取り組み:医療事故調査制度の創設
- 日本医師会の取り組み:医師主導による医療機器開発への支援
- 医師の働き方を考える:離れた地で、ともに医師として働き続ける
- 医学教育の展望:「経験から学ぶ」環境で、学生を育てる
- Cytokine 集まれ、医学生!
- 大学紹介:千葉大学
- 大学紹介:東京慈恵会医科大学
- 大学紹介:島根大学
- 大学紹介:藤田保健衛生大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- FACE to FACE:岡田 直己×大沢 樹輝

