大学紹介
自治医科大学
【教育】地域社会でリーダーシップをとれる総合医育成
自治医科大学 医学教育センター長/教授 岡崎 仁昭
 自治医科大学医学部では、地域で求められる総合的臨床力を有し、他職種と連携して地域の医療・保健・福祉を構築し、実践し、維持するために必要な行動を取ることができること、そしてそのために必要な能力を向上させるべく、生涯を通じて努力する医療人を育成することをミッションとして掲げています。
自治医科大学医学部では、地域で求められる総合的臨床力を有し、他職種と連携して地域の医療・保健・福祉を構築し、実践し、維持するために必要な行動を取ることができること、そしてそのために必要な能力を向上させるべく、生涯を通じて努力する医療人を育成することをミッションとして掲げています。
本学は1年次から基礎医学の学習を始め、3年次には基礎臨床系統講義を終了します。共用試験(CBT/OSCE)を3年次終了時に実施することで、4年次から最大80週の診療参加型臨床実習を可能にしています。そのため、大学病院での実習に加えて診療所を中心としたCBL・県内拠点病院実習・都道府県拠点病院実習が可能です。また6年次には10ステーション臨床実習終了時にもOSCEを実施しており、成績優秀者に対し授業や試験を免除したうえで医師国家試験まで臨床研究実習を拡大できるfree-course student doctor制度を用意しています。このように、実習が充実しているのが本学の特徴です。また、1年次から6年次まで一貫した地域医療教育を行うことで、地域に根ざした医療者の育成にも取り組んでいます。
本学は高いストレート進級・卒業率(2013年度は93.6%)と医師国家試験合格率(2012~2014年度まで3年連続99.1%で全国第1位)を達成しています。全寮制を実施して仲間と共に学ぶ「協勉」の意識を積極的に推進しているほか、医学教育センター・学生生活支援センター等が学生をしっかりサポートするなど、きめ細かい学習支援体制がそうした成果を生んでいると言えます。
本学の総合医育成・地域医療教育は全国的に広がっている地域医療教育のモデルとなり、地域社会に貢献できるものと確信しています。
【研究】建学理念に立脚した展開研究の推進
自治医科大学 分子病態治療研究センター長/教授 古川 雄祐
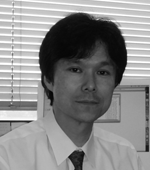 自治医科大学においては、建学の精神である「医学の進歩と地域住民の福祉の向上への貢献」を目標とした展開研究を推進しております。本学の特徴として、卒業生が全国各地で地域医療に従事しており、大学と密に連携した地域研究拠点が全国に形成されていることが挙げられます。その結果、地域バイアスのない数多くの臨床検体と患者情報を使用することが可能となり、高血圧や糖尿病などのコモンディジーズならびにB型肝炎や川崎病など我が国に多い疾患に関する新たな概念の提唱から新規治療戦略の開発へと成果を挙げております。一方でこのシステムは、特定地域に集中する疾患に関する情報や検体を、研究拠点である大学にフィードバックさせることも可能となります。実際、地域医療に従事する卒業生が希少な家族性神経疾患を発見、大学において分子生物学的解析を行い、発症のメカニズムを明らかにした実績があります。このような効果的なシステムが確立された背景には、文部科学省の戦略的研究拠点形成支援事業によって、学内の基礎医学と臨床医学の研究者を有機的に配置した研究拠点が構築されたことがあります。その結果、がん・炎症・生活習慣病などを対象とする集学的な研究が可能となり、非喫煙若年者の肺がんの原因となる新たな遺伝子変異の発見・パーキンソン病に対する遺伝子治療・心血管疾患における無菌性炎症の役割・動脈硬化進展のキーとなる酵素の同定・止血血栓の新たな仕組みの解明など、多くの先駆的業績に結実しました。とくに新規肺癌遺伝子の発見は、特異的阻害剤による治療成績の劇的な改善が示されており、肺癌治療のパラダイムを変えつつあります。このように、臨床への応用と福祉の向上を常に念頭におきつつ、高度な研究を推進しているのが本学の特徴であり、今後も地域医療のさらなる向上に貢献していきたいと考えております。
自治医科大学においては、建学の精神である「医学の進歩と地域住民の福祉の向上への貢献」を目標とした展開研究を推進しております。本学の特徴として、卒業生が全国各地で地域医療に従事しており、大学と密に連携した地域研究拠点が全国に形成されていることが挙げられます。その結果、地域バイアスのない数多くの臨床検体と患者情報を使用することが可能となり、高血圧や糖尿病などのコモンディジーズならびにB型肝炎や川崎病など我が国に多い疾患に関する新たな概念の提唱から新規治療戦略の開発へと成果を挙げております。一方でこのシステムは、特定地域に集中する疾患に関する情報や検体を、研究拠点である大学にフィードバックさせることも可能となります。実際、地域医療に従事する卒業生が希少な家族性神経疾患を発見、大学において分子生物学的解析を行い、発症のメカニズムを明らかにした実績があります。このような効果的なシステムが確立された背景には、文部科学省の戦略的研究拠点形成支援事業によって、学内の基礎医学と臨床医学の研究者を有機的に配置した研究拠点が構築されたことがあります。その結果、がん・炎症・生活習慣病などを対象とする集学的な研究が可能となり、非喫煙若年者の肺がんの原因となる新たな遺伝子変異の発見・パーキンソン病に対する遺伝子治療・心血管疾患における無菌性炎症の役割・動脈硬化進展のキーとなる酵素の同定・止血血栓の新たな仕組みの解明など、多くの先駆的業績に結実しました。とくに新規肺癌遺伝子の発見は、特異的阻害剤による治療成績の劇的な改善が示されており、肺癌治療のパラダイムを変えつつあります。このように、臨床への応用と福祉の向上を常に念頭におきつつ、高度な研究を推進しているのが本学の特徴であり、今後も地域医療のさらなる向上に貢献していきたいと考えております。
【学生生活】勉強も生活も楽しみながら、地域を牽引する医者へ
自治医科大学 医学部 5年 住吉 秀太郎
自治医科大学で最も特徴的な点として、都道府県の定員枠に分かれて入学し、卒業後にその都道府県で医師として規定年数勤務することで学費が免除になることが挙げられます。卒業後、学生はほぼ全員が各都道府県に戻り、9年間へき地医療等に携わるようになります。9年と聞くと長く感じますが、医学生として勉強していると、一人並みの医師になるのには10年近くかかることがわかってきます。むしろこの年数は自分を鍛え、医師として良いキャリアを積むのにはぴったりだと言えるでしょう。
自治医大では4年次から約2年にわたり病院実習を行います。この期間は他大と比べてもかなり長く、国際基準を満たすものです。他大だとマイナー科での実習が短いと聞きますが、自治医大では多くの科で2週間以上学ぶことができ、先生とも仲良くなれます。
大学には熱心な先生方が多く、授業も特色が強いです。薬理学の授業では基本的な実習を班で行い、その発表では先生方が半分、学生がもう半分の点数をつけるシステムになっているので、実験だけでなく発表の仕方や質問への対応も重要になってきます。
学生は基本的に6年間寮で生活します。寮には共有スペースとしてラウンジが10部屋ごとに用意されていて、ゲームや飲み会をしたり、試験前にはみんなで勉強を教え合ったりと自由に使えます。1年次には1年生だけで同じラウンジを、2年次以降は引っ越して他学年と共通のラウンジを使うようになるので関係が縦にも横にも広がり、とても居心地が良いです。また、BBSという組織を中心に1年生の生活の手助けもしていて、後輩への面倒見も良いです。勉強も生活も充実させたい人にはおすすめの環境が揃っていると思います。


〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1
0285-44-2111



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:岩田 健太郎先生
- Information:Summer, 2015
- 特集:医師と情報 漕ぎ出せ!情報の海へ
- 特集:「情報」を再定義する
- 特集:選択肢に関する情報
- 特集:患者に関する情報
- 特集:根拠に基づき、最良の意思決定を
- 特集:情報を公益につなげるために
- 同世代のリアリティー:好きなことを追いかける 編
- チーム医療のパートナー:救急救命士
- チーム医療のパートナー:臨床検査技師
- 地域医療ルポ:徳島県那賀郡那賀町|那賀町立上那賀病院 鬼頭 秀樹先生
- 10年目のカルテ:耳鼻咽喉科・頭頸部外科 有泉 陽介医師
- 10年目のカルテ:耳鼻咽喉科・頭頸部外科 宮里 麻鈴医師
- 医師の働き方を考える:女性の人権を守るために、性の正しい知識を伝える
- 医学教育の展望:学生が他の職種から学ぶ機会を作る
- 日本医師会の取り組み:臨床研修医の医師会費無料化
- 日本医学会の取り組み:医療チーム 学生フォーラムの歩み
- Cytokine 集まれ、医学生!
- 大学紹介:福井大学
- 大学紹介:自治医科大学
- 大学紹介:鳥取大学
- 大学紹介:大阪市立大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- FACE to FACE:西村 有未×池上 侃

