大学紹介
東北大学
【教育】幅広い視野とリサーチ・マインド
東北大学大学院 医学系研究科
医学教育推進センター 教授 加賀谷 豊

東北大学医学部医学科は、学生が国際化の時代に相応しい幅広い視野とリサーチ・マインドを持ち、主体的にキャリア形成できるよう強力に支援します。学生の主体的探求姿勢を促すため、3年次は20週間にわたり、希望する基礎・社会医学系の分野や海外の研究室(平成26年度は30名が海外留学)に所属し、フルタイムで研究できる制度を整えています。多くの学生がその後も研究を続け、成果を国際学会で発表したり国際的学術雑誌に掲載したりしています。文科省補助事業「世界で競い合うMD研究者育成プログラム」が、学生の基礎医学研究を支援します。これらにより、最近6年間で日本学生支援機構「優秀学生顕彰」を9人が受賞し、うち3人は学術大賞を受賞しています。また、3年次にネイティブ・スピーカーによる英語の少人数グループ学習を集中的に行うほか、全学年対象に課外でも同様の企画を提供するなど、スーパー・グローバル大学のトップ型に採択された大学に相応しい環境を誇ります。一方、医療技術の習得や医療行為を安全に実施するための学習にも力を注いでおり、日本有数の規模を誇るスキルスラボを授業で積極的に活用しています。平成26年度は延べ15,507人のスキルスラボの利用があり、うち6,639人を医学科学生が占めます。バーチャル型を含むシミュレータを用いたタスク・トレーニングから最先端の高機能患者シミュレータを用いた救急対応トレーニングに至るまで、多彩なプログラムを提供しています。
基礎医学や臨床医学で世界をリードする研究医、高度医療実施施設で先端医療や質の高い臨床教育に携わる医師、地域基幹病院で良質の医療を提供しつつ若手医師を育てる指導的な医師など、本学の卒業生のキャリアは多彩です。学生を特定の型にはめることなくキャリア形成をしっかり支援することを目指し、常に学習カリキュラムの改革に努めています。
【研究】基礎から臨床までバランス良く
東北大学大学院 医学系研究科 発生発達神経科学分野 教授 大隅 典子
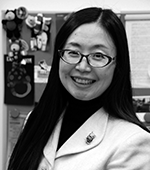
東北大学は1907年の開学以来、「研究第一」「門戸開放」「実学尊重」という3つの理念を掲げています。医学部・医学系研究科の歴史としては1736年の仙台藩明倫養賢堂にまで遡りますが、東北帝國大學医科大学として開設されたのが1915年。2015年で100周年を迎えました。東北大学の医学研究も上記の3つの理念に則っており、その特色として、基礎から臨床までバランス良く研究が行われていることが挙げられます。特に分子生物学、免疫学、脳科学などでは著名な研究者を輩出しており、小児の肺炎の原因として見つかった「センダイウイルス」は、現在ではiPS細胞への遺伝子導入などにも使われています。また病気を一つの臓器の問題としてではなく、分子から臓器に至る各階層においてネットワークとして捉える「ネットワーク・メディシン」という概念を打ち出し、代謝病やがんの研究を進めています。このような研究は、医学系研究科附属「創生応用医学研究センターART」という組織を軸にして進められています。さらに近年では、病気の原因を大規模に調査する疫学の伝統に基づき、東日本大震災後に「東北メディカル・メガバンク」という国家プロジェクトとして「ゲノム・コホート事業」も展開し、日本で最大規模の前向き健康調査をしています。グローバルな医学研究として多数の外国人留学生を受け入れており、特に新興再興感染症の医療と研究を東南アジアやアフリカ諸国と連携して進めています。さらに東北大学では医学と工学の連携が古くから進んでおり、日本で最初のCTや脳波計が開発されました。わが国で初めて「医工学研究科」が設置されたのも、このような歴史と実績に基づいています。現在では大学病院に附属する「臨床研究推進センターCRIETO」を中心に、創薬から医療機器開発まで、トランスレーショナルリサーチの観点から臨床研究を推進しています。
【学生生活】地域に開かれた大学で意欲的に学ぶ
東北大学 医学部 4年 中尾 茉実
東北大学には「研究第一」という理念があります。勉強したいと思っている人が好きなだけ学べる環境なので、1年生のころから先生にお願いして、自分が将来進みたい研究室に通わせてもらっている学生もいます。また、3年生の基礎医学修練の授業では、学生一人ひとりが研究室に配属されます。なかには、この時に留学して海外の大学で学ぶ人もいます。先生たちも、真面目に研究したい学生に対し熱心に指導してくださる方が多く、時に厳しくもありますが、意欲がある人にはおすすめの環境です。
私は、今年の10月9・10日に開催される医学祭の実行委員長を務めています。この医学祭は3年に1度開催されており、戦後すぐに第1回が行われて今回で23回目になります。医学祭は私たち医学生が日頃学んでいることを一般市民の方々に還元するためのイベントで、時代の移り変わりにともないコンセプトが少しずつ異なります。ここ数回は市民の方に医学部や医療をもっと身近に感じてもらえたらいいなという思いで開催されており、特に今回は小さいお子さんからご年配の方まで幅広く楽しめる内容にしたいと考えています。子供向けの企画、高齢者の方にとって身近な病気についての講演会や、シミュレーターを使った手術体験の実施も検討しています。
ただし、残念なことに、「とても真面目なイベントなんじゃないか」と思って敬遠する医学生がいるのも事実なので、今回は医学生の参加率を上げるための取り組みも行います。隔年開催でノウハウが少なく、オープンキャンパスと異なり広報や会計も含めて学生が主体となり運営するので、大変なことも多いですが、一人でも多くの医学生や市民の方が参加してくれる医学祭になるように頑張っていきたいと思っています。
※医学生の学年は取材当時のものです。


〒980-8575 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1
022-717-8006



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:蓮沼 直子先生
- Information:Spring, 2016
- 特集:臨床研修の実際 1年目研修医 密着取材
- 特集:密着取材レポート 市立函館病院 救急救命センター
- 特集:密着取材レポート 水戸協同病院 救急科
- 特集:密着取材レポート 東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科
- 特集:密着取材レポート 和歌山県立医科大学附属病院 ICU
- 特集:密着取材レポート 沖縄県立中部病院 呼吸器内科
- 特集:密着取材を振り返って
- チーム医療のパートナー:民生委員・児童委員
- 地域医療の現場で働く医師たち 第4回「日本医師会 赤ひげ大賞」表彰式開催
- 地域医療ルポ:鳥取県日野郡|日南病院 高見 徹先生
- 10年目のカルテ:病理診断科 市原 真医師
- 10年目のカルテ:法医学 本村 あゆみ医師
- 同世代のリアリティー:医師とお金 編
- 日本医師会の取り組み:日本医師会年金
- 医師の働き方を考える:女性医師の働きやすい環境作りは、すべての医師の働きやすさにつながる
- 医学教育の展望:学部時代から基礎医学研究の最先端に携わる
- 大学紹介:東北大学
- 大学紹介:日本医科大学
- 大学紹介:三重大学
- 大学紹介:琉球大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

