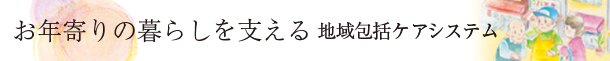
地域包括ケアシステムとは(前編)
地域包括ケアシステムはなぜ必要なのか、それはどのようにお年寄りの暮らしを支えるのか、考えてみましょう。

高齢化の時代に、何が必要か?
みなさんもご存知の通り、わが国の高齢化は世界に類を見ないスピードで進行しており、10年後の2025年には、75歳以上の高齢者の人口が全体の18.1%になると推計されています*1。人が制限なく日常生活を送ることができる年数の平均(健康寿命)は、男性70.4歳、女性73.6歳とされているため*2、75歳以上の方々の多くは何かしらの医療やケアを必要とするでしょう。しかし、平均寿命(男性80.2歳、女性86.6歳*3)と健康寿命の差である約10年を、ずっと病院や施設で過ごすのは現実的ではありませんし、多くの高齢者は住み慣れた自宅や地域で暮らしたいと考えています。では、どうしたらうまくいくのでしょう?
まず、健康寿命を延ばすという考え方があります。医療や介護が必要になる前に、運動・食事・生活習慣などに働きかける健康増進活動のほか、多くの人と関わり生きがいを持って生活できる環境作りも、健康寿命を延ばす効果があるとされています。「ピンピンコロリ」などと言われるように、生きている間はできるだけ健康に暮らせるような環境作りが求められます。 そして、残念ながら医療や介護が必要になった時のことを考えると、一人ひとりの希望に合った支援を受け、できるだけ自宅や地域で皆が支え合って暮らせるようにする仕組みが必要です。また、限られた医療・介護資源で多くの高齢者を支えていくにも、やはり様々な施設とそこで働く専門職が、協力し合わなければなりません。
このように、健康寿命を延ばし、医療や介護が適切に連携して暮らしを支えられるようにする仕組みが「地域包括ケアシステム」なのです。
地域包括ケアシステムとは
「地域包括ケアシステム」は、厚生労働省が2003年から推進している考え方です。厚労省は、高齢社会にあっては、「重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される」仕組みが必要だと述べています。
医師になるみなさんは、医療の現場にやってくる高齢者のことを「患者」として捉えると思います。しかしその人は、患者である前に、自立して生活を営むひとりの「生活者」であり、一時的に「患者」として医療機関を利用しているにすぎません。医療機関にやってくる人の疾患を治療することが重要なのは言うまでもありませんが、目の前の人を「患者」としてだけではなく「生活者」として捉えて、より良い暮らしができるよう働きかけることが、これからはより求められます。もちろん、医師だけの力で高齢者の生活を支えることはできませんから、医療関係者をはじめ、介護従事者や行政職員、地域の住民など、様々な関係者が互いに連携し、ネットワークを構築していくことが重要になります。これが地域包括ケアシステムの考え方です。
*2 厚生労働科学研究「健康寿命の指標化に関する研究」(平成25年度)
*3 厚生労働省「平成25年簡易生命表」
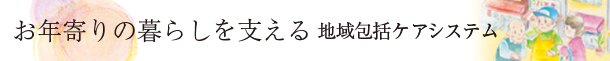
地域包括ケアシステムとは(後編)
システムを支える関係者
それでは、地域包括ケアを支えるのは、具体的にどのような関係者なのか見ていきましょう。まず、医学生のみなさんの最も身近にある医療の部分です。病状が急性増悪して、専門的な検査や手術が必要になったときには、急性期病院が対応します。一方、普段の生活では、かかりつけの診療所や地域の中小病院が外来治療を担当すること、あるいは医療機関に通えなければ訪問診療や訪問看護等によって、継続的な治療やケアを提供する必要があるでしょう。
介護サービスは、介護保険によって提供されます。デイサービスやショートステイなど、施設にやってくる高齢者に対してサービスを提供する場合もあれば、訪問介護のように、介護職員が自宅を訪問する場合もあります。
生活支援・介護予防とは、高齢者の日常生活のサポートや、高齢者の要介護度が悪化するのを防ぐために行われる活動など、主に行政や民間事業者、地域住民が担い手となる取り組みを指します。例えば、ボランティアが主催するサロンで行われるレクリエーションなど、高齢者が出て行って活動に参加するような形もあれば、民生委員など地域住民による見守りや、自分で食事を作るのが難しい高齢者に対する民間の配食サービスなど、自宅にいる高齢者に対して地域住民などが働きかけるような形も考えられるでしょう。
地域の実情に応じた形で
地域包括ケアシステムは、多くの地域ではまだ構築されつつある状態です。また、地域包括ケアシステムに決まった形はなく、むしろ、すでにある資源を活用し、地域ごとにより良いあり方を模索していくことが求められています。ここからは、地域包括ケアシステムは具体的にどのように機能しているのか、様々な地域における事例を紹介します。
高齢者や家族を支える
高齢者が地域で生活を続けるために、多くの場合は医療・介護サービスが必要となります。東京都板橋区では、高齢者や介護家族に対し、医療や介護に関してわからないことを気軽に相談できる窓口を設けています。
病院と地域をつなぐ
高齢者は、急性期病院を退院してから、すぐに元の生活に戻れるとは限りません。北海道の函館市医師会病院では、地域医療連携センターを設置し、患者がスムーズに退院できるようにサポートを行っています。
在宅医療を支える
在宅医療を必要とする高齢者に対して、24時間365日体制で医療を提供するのは、簡単なことではありません。福岡県の宗像医師会は、かかりつけ医が在宅医療を継続的に行うことができるよう、様々なサポートを行っています。
医療・介護従事者をつなぐ
医療機関・介護施設が効果的に連携するために、地域の医療・介護に関する情報を1か所に集約するという方法もあります。山形県の鶴岡地区医師会では、医療・介護従事者のための相談窓口を開き、連携を下支えしています。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:近藤 豊先生
- Information:April, 2015
- 特集:お年寄りの暮らしを支える 地域包括ケアシステム
- 特集:地域包括ケアシステムとは
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE01 高齢者や家族を支える(東京都板橋区)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE02 病院と地域をつなぐ(北海道函館市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE03 在宅医療を支える(福岡県宗像市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE04 医療・介護従事者をつなぐ(山形県鶴岡市)
- 特集:対談 地域包括ケアを担う一員として医師に求められることとは?
- 医学教育の展望:地域と共に医師を育てる仕組みを作る
- 同世代のリアリティー:自治体で働く 編
- チーム医療のパートナー:みさと健和病院 作業療法士
- チーム医療のパートナー:三重県立こころの医療センター 作業療法士
- 地域医療ルポ:滋賀県東近江市|小串医院 小串 輝男先生
- 10年目のカルテ:消化器内科 山田 哲弘医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 長島 多聞医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 橋本 神奈医師
- 医師の働き方を考える:信念と広い視野を持てば、働き方は選択できる
- 大学紹介:昭和大学
- 大学紹介:日本大学
- 大学紹介:神戸大学
- 大学紹介:山口大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- 医学生の交流ひろば:5
- FACE to FACE:山田 舞耶×金 美希

