大学紹介
山口大学
【教育】発見し・育み・形にする医の広場
山口大学 医学部 教務部委員長 法医学 教授 藤宮 龍也
 山口大学は、1815年に創設された長州藩の私塾「山口講堂」が源流であり、2015年には創基200周年を迎えます。明治維新の発祥の地にあり、「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」を大学の理念として、学生が自身の可能性を発見し、育て、チャレンジする場を提供することを心掛けています。医学部は1944年に設立され、70年の長い伝統を通じて、教育・研究・社会貢献の3本の矢により地域・世界の発展に貢献する医師養成の拠点として、数多くの医療人や医学研究者を輩出しています。
山口大学は、1815年に創設された長州藩の私塾「山口講堂」が源流であり、2015年には創基200周年を迎えます。明治維新の発祥の地にあり、「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」を大学の理念として、学生が自身の可能性を発見し、育て、チャレンジする場を提供することを心掛けています。医学部は1944年に設立され、70年の長い伝統を通じて、教育・研究・社会貢献の3本の矢により地域・世界の発展に貢献する医師養成の拠点として、数多くの医療人や医学研究者を輩出しています。
1年次には他学部の学生と交流しながら幅広い教養を身につける共通教育カリキュラムと、体験学習を取り入れた医学入門があり、電子シラバス・必携パソコンを駆使しながら医学の基礎を学ぶ2年次の臓器別統合型カリキュラム、 臨床医として身につけるべき知識・技能を習得する4年次カリキュラム、スキルス・ラボを活用し、県内全域の医療機関と連携しながら総合的診療能力を養う5・6年次臨床実習と、いずれも先進的で充実したカリキュラムとして高い評価を得ています。特に、3年次の自己開発コースや修学論文テュートリアルコースは最大半年と長期にわたり、学生が自ら企画・立案したプログラムを研究室や国内外で実践し、論文として形にするもので、医療人としての成長が期待されるコースです。さらに欧米・アジアの先端研究室での長期の研究留学や、僻地を含む地域の医療現場での実習、大学院の先取り研究医養成MD-PhDコースなど、ユニークな研究・臨床演習の機会も準備しています。山口大学はこれらの教育成果の達成を図るとともに、教育や課外活動を通じて学生との交流を図り、学生の個性を尊重して、学生生活が楽しく有意義なものになるように随所で学生支援を心掛けています。
【研究】地域から世界へ情報を発信する研究・教育拠点
山口大学 大学院医学系研究科長 消化器病態内科学 教授 坂井田 功
 山口大学大学院医学系研究科は、システム統御医学系専攻、情報解析医学系専攻、応用医工学系専攻、応用分子生命科学系専攻及び保健学専攻の特色ある5専攻から構成されており、専門分野を深めると同時に、専門の枠を越えた融合研究を活発に推進しています。
山口大学大学院医学系研究科は、システム統御医学系専攻、情報解析医学系専攻、応用医工学系専攻、応用分子生命科学系専攻及び保健学専攻の特色ある5専攻から構成されており、専門分野を深めると同時に、専門の枠を越えた融合研究を活発に推進しています。
中でも、医学と工学の融合を目指した応用医工学系専攻では、がんや循環器疾患の集学的治療を目指した先端医療器材の開発などを含む時代のニーズに対応できる人材を育成しています。また理学・工学・農学系との融合により学際的な教育研究の推進を目指す応用分子生命科学系専攻では、バイオインフォマティクスを駆使した分子レベルの病態や生命機能の解析、さらには化学合成及び先端バイオ技術による有用分子の臨床応用などのトランスレーション研究に貢献できる広い視野を持った人材を育成しています。
最重要課題である若手の人材育成については、若者が志を高く持つことができる教育・研究環境の整備に全力で取り組んでおります。
文部科学省の支援を受けた「アカデミックドクターの育成を目指した実践研究参加型医学教育の拡充プロジェクト」では、将来グローバルに活躍できる医療人を養成するために、短期の海外研究留学を積極的に推進し、毎年10名を超える医学生が欧米の一流ラボで研鑚を積んでいます。さらに学部在学中に、研究活動を行い、一部大学院単位の先取り履修を可能にしたSCEA/AMRAプログラムを導入し、卒後の初期研修プログラムから大学院での研究にスムーズに移行できるようなシステムを作りました。
維新の地・山口から、世界レベルで活躍する医療人を輩出するために、まさに教職員一丸となって日々の教育・研究指導にあたっています。
【学生生活】田舎こそのハングリー精神で積極的な交流
山口大学 医学部 4年 中西 俊就
同 3年 尤 暁琳
同 3年 佐伯 晋吾
佐伯:山口大学では、3年次に自己開発コースが始まります。半年間研究室に所属して、研究の基礎を学びます。先生の紹介で海外の大学に留学する人もいます。
中西:僕はアメリカのミネソタ大学に半年間留学して、膵がんのウイルス治療を研究しているラボで学びました。その研究室にはインドやブラジルなど世界各地の研究者が所属していたのですが、研究者同士が日常的にディスカッションを行っていたのが印象的でした。
尤:私たち3人が役員を務める学生自治会は、学生の要望を学校側に伝える役割を担っています。山大は2年次以降からキャンパスが変わるのですが、以前は部活動が終わった1年生を先輩がマイカーで送り迎えしていました。けれど部活が終わった後に往復2時間かけて送るのは危険だという意見が出て、自治会が交渉の末、送迎バスを運行させることになりました。
佐伯:山口大学の医学祭は学生が主体となり、3日にわたって行われるのですが、それも自治会が管轄しています。3日かけて医学祭をする大学は珍しいんじゃないかと思います。学内の県人会も出店を出したり、医学祭はかなり盛り上がりますね。
尤:大学の近くの飲み屋に行くと必ず誰かに会って、最初は5人で飲んでいたのに、いつの間にか20人くらいの飲み会になっていることもあります。お刺身が美味しいからお酒が進むんです(笑)。部活の先輩・後輩以外のつながりも強く、休日には角島や秋芳洞、錦帯橋など県内の名所を車で巡っています。
中西:都会の学生よりも情報に飢えている分、自分から動いてどんどん交流していこうっていう気質があります。エネルギッシュでハングリーな学生の多い大学だと思っています。
※医学生の学年は取材時のものです。

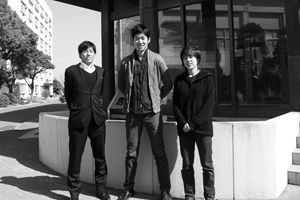
〒755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1
0836-22-2111



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:近藤 豊先生
- Information:April, 2015
- 特集:お年寄りの暮らしを支える 地域包括ケアシステム
- 特集:地域包括ケアシステムとは
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE01 高齢者や家族を支える(東京都板橋区)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE02 病院と地域をつなぐ(北海道函館市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE03 在宅医療を支える(福岡県宗像市)
- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE04 医療・介護従事者をつなぐ(山形県鶴岡市)
- 特集:対談 地域包括ケアを担う一員として医師に求められることとは?
- 医学教育の展望:地域と共に医師を育てる仕組みを作る
- 同世代のリアリティー:自治体で働く 編
- チーム医療のパートナー:みさと健和病院 作業療法士
- チーム医療のパートナー:三重県立こころの医療センター 作業療法士
- 地域医療ルポ:滋賀県東近江市|小串医院 小串 輝男先生
- 10年目のカルテ:消化器内科 山田 哲弘医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 長島 多聞医師
- 10年目のカルテ:消化器内科 橋本 神奈医師
- 医師の働き方を考える:信念と広い視野を持てば、働き方は選択できる
- 大学紹介:昭和大学
- 大学紹介:日本大学
- 大学紹介:神戸大学
- 大学紹介:山口大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- 医学生の交流ひろば:4
- 医学生の交流ひろば:5
- FACE to FACE:山田 舞耶×金 美希

