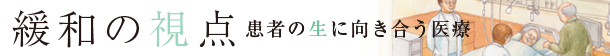
専門的緩和ケアの3つの現場
ホスピス・緩和ケア病棟 東京衛生病院(前編)
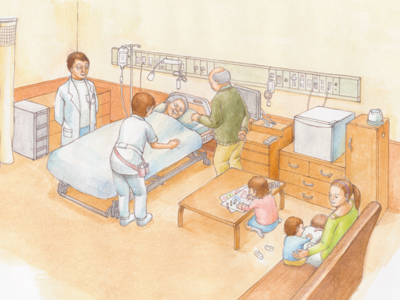
ホスピス・緩和ケア病棟とは
がん治療を続けていくと、残念ながら治癒する可能性がなくなる時期があります。抗がん剤治療や放射線治療の効果がなくなり、それ以上治療を続ければ副作用が患者さんの心身を蝕む場合も少なくありません。残された人生を苦痛なく穏やかに過ごしたいと望む患者さんのための場所が、ホスピスや緩和ケア病棟です。
とはいえ、ホスピスでは医療的な処置を全くしないというわけではありません。病状が急変する場合もあるため、がん末期の患者さんがどのような経過を辿って死に至るのかを知り、適切に対応する必要があります。入院したその日に亡くなってしまうケースもあるほどです。それでも、患者さんのつらさを和らげ、できる限りその人らしい最期を過ごしてもらうために様々なケアを行うのが医療者の役割です。
東京衛生病院の緩和ケア病棟
古くからホスピスの歴史を持つ東京衛生病院理事長の早坂先生に、ホスピスでの緩和ケアについてお話を伺いました。
「ホスピスの基本的な考え方は、患者さんにとって今一番よいことを、すべての側面から考えることです。もちろん、がんが治る可能性がある場合には治療は必要ですが、治らないとわかった場合には、積極的な治療を行わない方がよい場合も多い。あくまで患者さんの今の病状に対して一番よいと考えられる医療を提供しています。
ホスピスではほとんどの場合、最終的に命を助けることはできません。その分、亡くなるまでの過程に患者さんや家族が納得しない限り、必ず悔いが残ります。私たちは患者さんと家族が最後の時期によい時間を過ごせたと思えるように、通常の何倍もの時間をかけて、様々な職種が関わりながら、症状のコントロールや精神的なケア、家族のケアを行っています。
診断当初から治療に携わった医師であれば、患者さんと長い時間をかけてコミュニケーションがとれますが、ホスピスは最後の段階で引き継がれるため、短期間で信頼関係を築かなければならない難しさがあります。今後は、大学病院や地域の医療機関の主治医と早い段階からやり取りをし、患者さんと家族の背景を把握しておくことができればと考えています。」
精神的支柱としての宗教者の役割
東京衛生病院をはじめ、ホスピスや緩和ケア病棟をもつ病院には宗教的な背景があるところが多くあります。
「キリスト教系の病院は欧米の病院とつながりがあったため、緩和ケアの考え方を導入しやすかったのではと思います。
キリスト教には、『人間の命は神様から与えられたものであり、能力・状態によらず大切である』という思想があり、これは『死までの時間をいかによく過ごせるかを考えよう』というホスピスの理念に近いものがあります。そうした理念を組織として支えているのが、当院では牧師という存在なのではないかと私は思います。彼らはとても尊敬できる存在です。私たち医療者も、困ったことがあるときには牧師に相談に行くんです。死に向き合うのは大変なことだから、やはり様々な迷いや葛藤がある。そんなとき立ち返るのが理念であり、当院ではそれを牧師が体現し、精神的支柱になってくれているんだと思います。」
 私はずっと外科医として働いてきました。がんの患者さんを治療するなかで、どんなに手術をしても再発する患者さんに何度も出会い、「元気になってよかったですね」とニコニコしているだけでは済まない、再発する人のケアも重要だということが実感としてわかってきました。そして、歳をとってきて、外科医として長時間働くことが厳しくなってきた頃に、緩和ケアの分野に転向しました。「とにかく何とか命を助けたい」と思い、努力してきたことがベースとなり、今は何とか命を支えたいと思っています。
私はずっと外科医として働いてきました。がんの患者さんを治療するなかで、どんなに手術をしても再発する患者さんに何度も出会い、「元気になってよかったですね」とニコニコしているだけでは済まない、再発する人のケアも重要だということが実感としてわかってきました。そして、歳をとってきて、外科医として長時間働くことが厳しくなってきた頃に、緩和ケアの分野に転向しました。「とにかく何とか命を助けたい」と思い、努力してきたことがベースとなり、今は何とか命を支えたいと思っています。
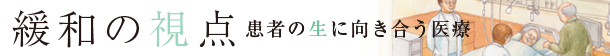
専門的緩和ケアの3つの現場
ホスピス・緩和ケア病棟 東京衛生病院(後編)
牧師
牧師部長・チャプレン
永田 英子さん
 不思議なもので、「牧師です」と言って伺うと、患者さんたちもストレートに、死ぬことや生きること、過去のこと、自分の死後のことなどについて話して下さいます。そこで出てくるのが、「なぜ」ということばです。なぜ自分は病気になったのか、何の意味があるのか、自分が生きている意味は何だろうという問い。私たちはそうしたことばに耳を傾け、時には時間をかけて話を聴きます。それは人を超えた存在への問いのように聴こえます。医療者とは違う側面からその人と出会い、共に悩み、共に平和をみつけることが役割だと思っています。この病院は宗教色の強い病院で、スタッフの3割がクリスチャンですが、クリスチャンでなければならないというわけではありません。ただ、「こころとからだのいやしのために、キリストの心でひとりひとりに仕えます。」という病院の理念をスタッフ全員が常に大事にしていることは、この病院の医療の質を支えていると思います。患者さんのためにスタッフと一緒に祈る機会があるのですが、みな同じことに悩み、どうしたらいいかを考えているんです。思いを共有できていることは、うれしいことですね。医療者も神の癒しの対象であることをいつも伝えるようにしています。
不思議なもので、「牧師です」と言って伺うと、患者さんたちもストレートに、死ぬことや生きること、過去のこと、自分の死後のことなどについて話して下さいます。そこで出てくるのが、「なぜ」ということばです。なぜ自分は病気になったのか、何の意味があるのか、自分が生きている意味は何だろうという問い。私たちはそうしたことばに耳を傾け、時には時間をかけて話を聴きます。それは人を超えた存在への問いのように聴こえます。医療者とは違う側面からその人と出会い、共に悩み、共に平和をみつけることが役割だと思っています。この病院は宗教色の強い病院で、スタッフの3割がクリスチャンですが、クリスチャンでなければならないというわけではありません。ただ、「こころとからだのいやしのために、キリストの心でひとりひとりに仕えます。」という病院の理念をスタッフ全員が常に大事にしていることは、この病院の医療の質を支えていると思います。患者さんのためにスタッフと一緒に祈る機会があるのですが、みな同じことに悩み、どうしたらいいかを考えているんです。思いを共有できていることは、うれしいことですね。医療者も神の癒しの対象であることをいつも伝えるようにしています。
看護師
緩和ケア認定看護師
中村 陽子さん
 緩和ケア病棟は、患者さんに寄り添うことを大切にし、そのことに時間をかけることができる環境だと思います。私たちは患者さんや家族がこれまでどのように生きてこられたのか、「その人らしさ」を大事にすることを心がけています。そして、からだや心のつらさに寄り添い緩和することで最期までその人らしく生きることを支え、「あの方らしい生き方だったな。」と思えるような看護を目指しています。患者さんが亡くなるのは私たちにとってもつらいことですが、ケアをしながらそれぞれの生き方や考え方を傍で感じられ、自分の人生の勉強になっています。みなさんすごく尊敬できる生き方をされていますし、「生きる」ことを考え、感じられる場所だと思います。
緩和ケア病棟は、患者さんに寄り添うことを大切にし、そのことに時間をかけることができる環境だと思います。私たちは患者さんや家族がこれまでどのように生きてこられたのか、「その人らしさ」を大事にすることを心がけています。そして、からだや心のつらさに寄り添い緩和することで最期までその人らしく生きることを支え、「あの方らしい生き方だったな。」と思えるような看護を目指しています。患者さんが亡くなるのは私たちにとってもつらいことですが、ケアをしながらそれぞれの生き方や考え方を傍で感じられ、自分の人生の勉強になっています。みなさんすごく尊敬できる生き方をされていますし、「生きる」ことを考え、感じられる場所だと思います。
ボランティアスタッフ
 東京衛生病院では患者さんのケアにボランティアの方がかかわっており、買い物に行ってくれたり、お花の水を代えてくれたりするそうです。一定の距離のある第三者とかかわることが、患者さんにとって癒やしになっています。
東京衛生病院では患者さんのケアにボランティアの方がかかわっており、買い物に行ってくれたり、お花の水を代えてくれたりするそうです。一定の距離のある第三者とかかわることが、患者さんにとって癒やしになっています。
(写真)ボランティアスタッフの手作りの品が並ぶ売店。売上はボランティアの活動費に充てられます。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生
- Information:October, 2014
- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療
- 特集:緩和ケアの基本的な考え方
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生
- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編
- チーム医療のパートナー:臨床心理士
- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士
- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)
- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生
- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師
- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師
- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる
- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成
- 大学紹介:順天堂大学
- 大学紹介:埼玉医科大学
- 大学紹介:岐阜大学
- 大学紹介:鹿児島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月

