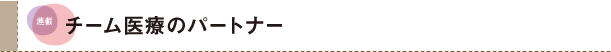
横浜市立大学附属市民総合医療センター(精神保健福祉士)
泉 桃子さん 渡邊 貴子さん
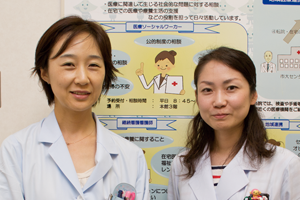
重度の精神疾患の患者さんの場合、経済的に困窮したり、退院後に自立した生活を送るのが難しかったりと、症状自体が治まった後も、社会的な困難が続くことがあります。患者さんが自分らしい生活を送るためには、医学的・臨床心理学的な治療に加えて、保健所を始めとする関係機関などの社会的サポートが不可欠です。精神保健福祉士(Psychiatric Social Worker, PSW)は、患者さんが自分らしい生活を送れるように各種社会資源の活用や調整を行う国家資格です。今回は横浜市立大学附属市民総合医療センターの泉桃子さんと渡邊貴子さんにお話を伺いました。
社会的な困難を軽減
PSWは病院内外の職種と連携し、患者さんの社会的な困難の軽減を図ります。ここで言う社会的困難とは、自身の身体的な変化によって生じるものや取り巻く環境の変化によって生じるものなど様々です。例えば患者さんが妊娠した時には、向精神薬などの服用を減量または中止することが多く、また産後には症状悪化のリスクが高まると言われるため、関係職種の支援が必要です。PSWは、院内の看護師や助産師、育児期の支援担当である保健所の保健師と連絡を取り、安心して出産・育児ができる環境を作っていきます。
「患者さんの状況は、疾患の重症度や家族・仕事の環境など、一つとして同じものはありません。これをやれば正解、というものがない所に難しさがあります。絶対的な正解がないなかで、より良い方針をその都度考えていく。一度退院し、再入院してくる患者さんもいますが、声をかけながら、信頼関係を積み重ねていくのがこの仕事の面白さなのかなと思います。」

患者さんの自己決定を尊重
精神疾患の患者さんのなかには、症状によっては、自身を傷つけたり、他者に危害をおよぼす可能性がある場合もあります。そのため、治療や保護のために本人の意思に反する入院を求められ、身体の拘束を受けることがあります。歴史的にも精神疾患患者の権利が不当に侵害された背景があるため、PSWは患者さんの人権や自己決定を尊重しなければならないと言います。
「退院後に生活する場所を決めるのも自己決定の一つです。家族との同居だけでなく、生活訓練施設やグループホームに移る選択肢もあり、それぞれのメリットとデメリットを十分に説明します。この時に大切なのは、患者さん自身が決定すること。私たちの意見を押しつけても、結果的に上手くいかないことが多いですから。たとえ失敗する可能性が高い決定をしても、私たちはそれを尊重して、患者さんを守るためのセーフティネットを用意しておくこともあるんですよ。」
※この記事は取材先の業務に即した内容となっていますので、施設や所属によって業務内容が異なる場合があります。



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生
- Information:October, 2014
- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療
- 特集:緩和ケアの基本的な考え方
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生
- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編
- チーム医療のパートナー:臨床心理士
- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士
- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)
- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生
- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師
- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師
- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる
- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成
- 大学紹介:順天堂大学
- 大学紹介:埼玉医科大学
- 大学紹介:岐阜大学
- 大学紹介:鹿児島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月

