大学紹介
埼玉医科大学
【教育】師弟同行で育つ優れた臨床医
埼玉医科大学 医学教育センター 生理学教授 渡辺 修一
 本学の建学の理念は、「1.生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成」「2.自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」「3.師弟同行の学風の育成」で、最も大切にしているのは優れた実地臨床医家の育成です。優れた臨床医には医学の基礎と臨床に関する豊富な知識と深い理解を基盤とした病気の診断・治療の力に加えて、患者さんが抱える家庭、職場、保健・福祉制度の悩みや困難にも共感して力になれる、人としての大きさが求められます。本学では1年生から「細胞生物学」と「人体の構造と機能」のユニットが始まり、学年が上がると「病気の基礎」「ヒトの病気」「社会と医学」を学んでいきます。5~6年生は臨床現場で学びます。臨床実習の最後の4か月は学生が臨床チームの一員として参加して学んでいく実践実習です。1~4年生には「良医への道」コースがあり医療面接、基本的臨床手技や臨床推論力を身につけていきます。「医学概論」で倫理・医療経済・行動科学等を学び、選択必修科目で広く教養も身につけます。
本学の建学の理念は、「1.生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成」「2.自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」「3.師弟同行の学風の育成」で、最も大切にしているのは優れた実地臨床医家の育成です。優れた臨床医には医学の基礎と臨床に関する豊富な知識と深い理解を基盤とした病気の診断・治療の力に加えて、患者さんが抱える家庭、職場、保健・福祉制度の悩みや困難にも共感して力になれる、人としての大きさが求められます。本学では1年生から「細胞生物学」と「人体の構造と機能」のユニットが始まり、学年が上がると「病気の基礎」「ヒトの病気」「社会と医学」を学んでいきます。5~6年生は臨床現場で学びます。臨床実習の最後の4か月は学生が臨床チームの一員として参加して学んでいく実践実習です。1~4年生には「良医への道」コースがあり医療面接、基本的臨床手技や臨床推論力を身につけていきます。「医学概論」で倫理・医療経済・行動科学等を学び、選択必修科目で広く教養も身につけます。
特色ある制度として交換留学と課外学習プログラムがあります。7か国10大学へ毎年20余名の学生が留学し、外国からの留学生が本学で学びます。課外学習プログラムは師弟同行そのもので、教員が用意した見学・体験・研究等に放課後・休暇中に参加します。もう一つ師弟同行として私達が誇りにしているのはアドバイザー制度です。学生約5名に対して教員1名がアドバイザーとなり、食事を共にして語り合い、いろいろな相談に乗るものです。また学生支援室では、学業や生活での不安・悩み・困難に所属の教員がチームとなって相談に応じ、対応します。
「師弟同行」の学風の下、みなさんと共に学び、質の高い国際水準の医学・医療を実践できることを楽しみにしています。
【研究】研究マインドを育てる卒前卒後教育
埼玉医科大学 医学研究センター長 免疫学教授 松下 祥
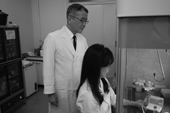 本学の建学の理念は「教育」の項で紹介しましたが、その中の、「自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」は研究活動と深い関係にあります。本学では研究マインドを醸成するため、平成11年から課外学習プログラムを実施しています。このプログラムには1年生から参加可能で、春休み・夏休み・通年の放課後を利用して研究室に出入りし、研究を体験できます。基礎医学系の教室のみならず、臨床医学系や国際レベルの最先端研究が行われているゲノム医学研究センターでも学生を受け入れています。さらに、平成25年度入学の医学部1年生が4年生になる28年度から、研究医枠のコ-スがスタートします。本コースでは、学部生の段階から基礎系の研究室で研究活動を経験するとともに、「海外研究体験留学制度」を利用し、提携先の大学でも研究体験ができます。学部4年生から大学院博士課程4年生までの7年間は奨学金が支給され、博士号取得後は本学で助教として採用されますが、本学で一定年限以上の研究活動を行えば返済免除となります。
本学の建学の理念は「教育」の項で紹介しましたが、その中の、「自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」は研究活動と深い関係にあります。本学では研究マインドを醸成するため、平成11年から課外学習プログラムを実施しています。このプログラムには1年生から参加可能で、春休み・夏休み・通年の放課後を利用して研究室に出入りし、研究を体験できます。基礎医学系の教室のみならず、臨床医学系や国際レベルの最先端研究が行われているゲノム医学研究センターでも学生を受け入れています。さらに、平成25年度入学の医学部1年生が4年生になる28年度から、研究医枠のコ-スがスタートします。本コースでは、学部生の段階から基礎系の研究室で研究活動を経験するとともに、「海外研究体験留学制度」を利用し、提携先の大学でも研究体験ができます。学部4年生から大学院博士課程4年生までの7年間は奨学金が支給され、博士号取得後は本学で助教として採用されますが、本学で一定年限以上の研究活動を行えば返済免除となります。
初期研修医プログラムとして「研究マインド育成自由選択プログラム」があります。本プログラムでは、初期臨床研修を行いながら社会人大学院生として研究(基礎や臨床)を行います。研修の空き時間を利用して1年次には大学院の講義などを受け、2年次の自由選択時期からより専門的な研究を行うことも可能です。なお、研修開始時には大学院入試に合格しておく必要がありますが、この入試の中でも最難関の外国語試験は、学部3年生から受験できます。実際、多くの学生が合格しています。本学の研究面でのもう一つの特徴は、特許を産学連携に活用していることです。知的財産収入は国内単科系医科大学の中ではトップです。みなさんと共に研究できる日を心から楽しみにしています。
【学生生活】医療系学生との議論からチーム医療を学ぶ
埼玉医科大学 医学部 5年 有川 滋久
埼玉医科大学のカリキュラムで特徴的なのは、4年次に用意されたIP演習という多職種連携の実習だと思います。埼玉県立大学の看護・作業療法・理学療法などの学生と一緒にチームを組んで、県内の病院で実際に患者さんと関わる実習です。僕のチームが受け持ったのは脳出血の患者さんで、リハビリを行いながら今後どのようにご自宅にお帰りいただくかを議論しました。4年の段階だと、医学生よりも他の医療系学生の方が医療現場について詳しいので、そのなかで発言するのは大学でのディスカッションよりも緊張します。この実習を通してわかったのは、僕たち医学生は疾患に着目するけれど、他の職種が見ているものは時として違うということ。例えば看護の人たちは、普段の生活で患者さんが困っていることをいかに解決するかを考えていて、理学の人は理学の人で違う観点を持っている。同じ患者さんを見ていても、捉え方が違うんだと学びました。
生活面では、僕はSAT(Saitama Academic Team)という勉強会サークルに所属しています。SATでは、医学部の授業で学んだことだけでなく、メンバーの関心領域に合わせて自由に勉強します。例えば漢方に興味がある学生がチームを組んで一緒に勉強したり、病院見学に行ったりして、最終的にメンバーの前で発表することもあります。僕は臨床推論の勉強会をやっています。症例を教科書や論文から探してきて、後輩にどんな疾患なのかを推論してもらい、最後に簡単な解説をする形です。もちろん授業で学ぶ内容も大切ですが、こうやって自分たちの関心に沿った内容を能動的に勉強することが、将来役立つはずだと思っています。
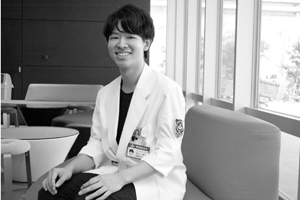

〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
049-276-1109



- No.44 2023.01
- No.43 2022.10
- No.42 2022.07
- No.41 2022.04
- No.40 2022.01
- No.39 2021.10
- No.38 2021.07
- No.37 2021.04
- No.36 2021.01
- No.35 2020.10
- No.34 2020.07
- No.33 2020.04
- No.32 2020.01
- No.31 2019.10
- No.30 2019.07
- No.29 2019.04
- No.28 2019.01
- No.27 2018.10
- No.26 2018.07
- No.25 2018.04
- No.24 2018.01
- No.23 2017.10
- No.22 2017.07
- No.21 2017.04
- No.20 2017.01
- No.19 2016.10
- No.18 2016.07
- No.17 2016.04
- No.16 2016.01
- No.15 2015.10
- No.14 2015.07
- No.13 2015.04
- No.12 2015.01
- No.11 2014.10
- No.10 2014.07
- No.9 2014.04
- No.8 2014.01
- No.7 2013.10
- No.6 2013.07
- No.5 2013.04
- No.4 2013.01
- No.3 2012.10
- No.2 2012.07
- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生
- Information:October, 2014
- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療
- 特集:緩和ケアの基本的な考え方
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟
- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生
- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生
- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編
- チーム医療のパートナー:臨床心理士
- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士
- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)
- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生
- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師
- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師
- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる
- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成
- 大学紹介:順天堂大学
- 大学紹介:埼玉医科大学
- 大学紹介:岐阜大学
- 大学紹介:鹿児島大学
- 日本医科学生総合体育大会:東医体
- 日本医科学生総合体育大会:西医体
- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!
- 医学生の交流ひろば:1
- 医学生の交流ひろば:2
- 医学生の交流ひろば:3
- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月

